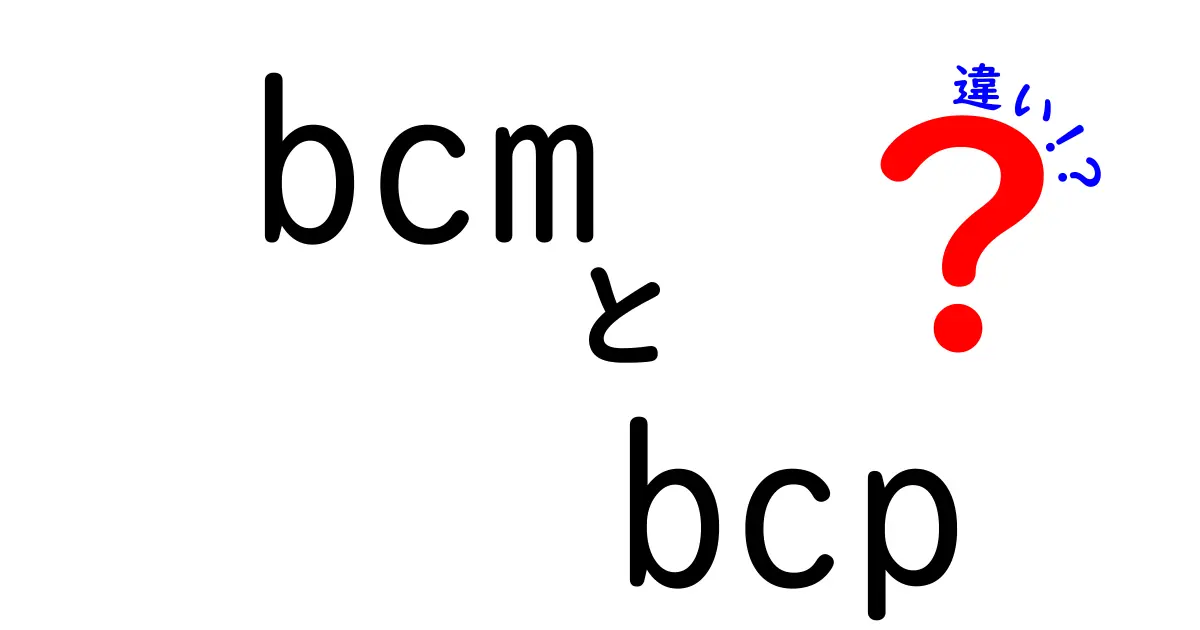

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
bcmとbcpの違いをわかりやすく解説
BCMとBCPは、災害やトラブルに強い組織を作るための考え方の名前です。BCMは枠組みであり、組織全体の危機管理の仕組みを指します。
この枠組みの中にはリスクの洗い出し方、重要な業務の影響を測る方法、復旧の優先順位を決める考え方、訓練や演習の実施、そして継続的な見直しの手順が含まれます。
一方でBCPは具体的な復旧計画そのものです。どのくらいの時間でどの資源を使って何を再開するか、緊急時に誰が何をするのかを明確に書き出した実務文書です。
BCMとBCPはお互いを支え合う関係にあり、BCPはBCMの成果物としての実行計画であり、BCMはBCPを生み出すための組織の仕組みと考えると分かりやすいです。
この違いを理解しておくと、学校の部活動や部長が指示を出すときにも混乱が減り、緊急時の判断が速くなります。
以下の章では、両者の基本と、日常生活で役立つ考え方を中学生にもわかる言葉で詳しく解説します。
bcmとは何か?基本を押さえよう
まずBCMの意味をしっかり押さえましょう。BCMは「危機が起きてもビジネスを続けるための仕組み全体」をつくることです。リスクの洗い出しや影響分析、回復戦略の設計、訓練と演習、見直しと改善などを順番に組み合わせて、一度始めると終わらない永遠の課題のように見えるかもしれません。実際には、最初は小さな目標から始め、徐々に全体へと広げていくのが現実的です。
学校や部活の例で言えば、試合が中止になっても次の大会に間に合わせるための「代替日程の用意」や「連絡手段の確保」などが“BCMの第一歩”です。
BCMの実務では、組織の「重要な業務」を洗い出す作業がとても大切です。たとえば部長が決断を下す際、すぐに相談する人、代替の連絡手段、試合運営の核となる人の役割分担などを決めておくと、急なトラブルでも混乱を避けられます。これらの準備ができていれば、他の部員が何をしていいか迷う時間を減らし、緊急時にも落ち着いて行動できるようになります。
bcpとは何か?計画と復旧の意味
次にBCPについて詳しく見ていきましょう。BCPは「具体的な復旧手順を書いた計画書」です。ここには誰が、いつ、何を、どの順序で動くかが、実際の場面を想定して整理されています。たとえば停電が起きた場合の連絡の取り方、代替の教室を使うタイミング、資料のバックアップを取り出す順序、外部協力企業との連携方法などが含まれます。
この計画はただの紙ではなく、訓練や演習を通して現場の人が自然に実行できるように作られています。
BCPの良い点は、実際の災害が起きても「何を優先して再開するか」がわかる点です。たとえば、成績管理システムが停止してしまった場合に、まずは出席と連絡の確認を戻してから、次の段階で授業資料の再配布を行う、という具合です。こうした段階的な復旧手順は、時間軸を意識して動くことの大切さを教えてくれます。
bcmとbcpの違いを日常の例で理解する
ここまでで学んだ「枠組み」と「計画」の違いを、身近な例で見てみましょう。学校の遠足で天気が崩れたとき、BCMの視点では、まず「安全を最優先にするための全体のルール」を確認します。集合場所を変更する、連絡網を整備する、代替日を決めるなどが該当します。
一方でBCPの視点は、天候の変化に応じて具体的な行動手順に落とし込みます。例えば“屋内での活動に切り替える場合の学級の動線”“荷物の受け渡し方法”“保護者への連絡の具体的な順序”などを明確にしておくのです。
このようにBCMとBCPは連携して機能します。BCMがなければBCPはただの紙切れになり、BCPがなければBCMは現場で役に立つ行動指針を生み出しません。両者をうまく組み合わせると、学校のような小さな組織でも、急なトラブルに対して落ち着いて対応できるようになります。
最後に覚えておきたいのは、BCMとBCPは「終わりのない改善プロセス」であるということです。新しい情報や新しいリスクが生まれるたび、見直しと訓練を繰り返す必要があります。
これを日常の習慣として取り入れれば、緊急時でも冷静に判断し、被害を最小限に抑える力が身につきます。
ある日の放課後、友だちとベンチに座ってBCPの話をしていた。彼は『BCPって何のためにあるの?』と聞いた。僕はBCPを日常の“約束事”と例えるといいと答えた。災害が起きても授業を止めずに続けるには、まず誰が何をするかを決め、次に必要な道具や連絡網をそろえる。この準備こそがBCPの核心であり、事前の訓練が効いてくる瞬間だ。話が進むにつれて、彼も自分の部活の準備に生かせると気づき、2人で長話をした。いつ起きるか分からない非常時に備える気持ちは、実は日々の授業や活動をより丁寧にする力にもなるのだ。





















