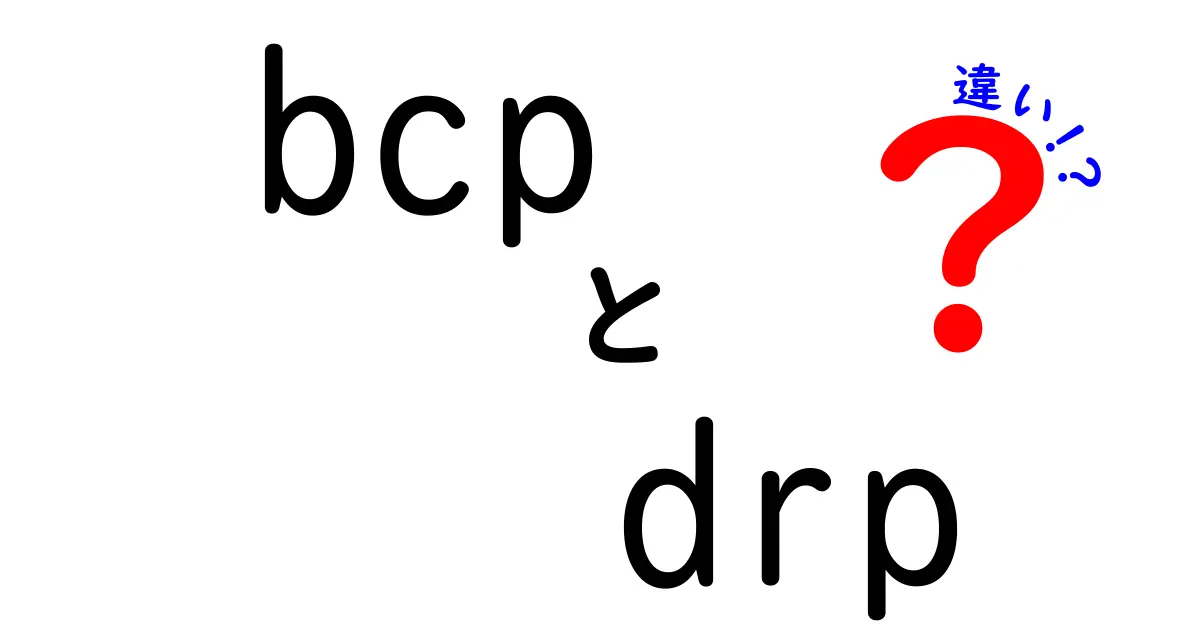

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
bcpとdrpの基本を理解しよう
BCPは「Business Continuity Plan」の略で、日本語では「事業継続計画」と訳します。大きな災害やトラブルが起きても、会社や組織が“業務を止めずに続けられる状態”を作るための設計図のことです。具体的には、重要な人材や情報、設備をどう守るか、どう動くかを事前に決めておくことが含まれます。DRPは「Disaster Recovery Plan」の略で、日本語では「災害復旧計画」と訳します。ITの部分を中心に、サーバーやデータベース、ネットワークなどのコンピュータ系の復旧をどう進めるかを決める計画です。BCPとDRPは密接に関係していますが、焦点と目的が少し異なります。
一言でいうと、BCPは「仕事を続けるための準備全般」、DRPは「ITを元の状態に戻すための具体的な復旧手順」です。両者を組み合わせると、地震や停電だけでなく、パンデミックやサイバー攻撃といった想定外の事態にも対応しやすくなります。次のセクションでは、それぞれの役割をもう少し詳しく見ていきます。
bcpの目的と役割
BCPの目的は、組織が大きな障害にぶつかっても「誰が、何を、どの順番で、どう動くか」を決めておくことです。人材の配置、業務の優先度、外部パートナーとの連携、情報のバックアップと共有方法など、幅広い要素を含みます。中学生にも分かるように例を出すと、学校の行事が突然中止になっても、生徒や先生がすぐに別の方法で代替案を実行し、授業の継続を保つ仕組みを作る感じです。
実務では、影響度分析(どの業務が止まると全体にどんな影響が出るかを評価する作業)を行い、優先度の高い業務を先に守る計画を作ります。これにはコミュニケーション手順、代替の勤務場所、重要データの保護方法、外部の協力先との連絡網が含まれます。
BCPは「人と手順と施設と情報の総合的な守り方」を示す地図のようなもので、日常の業務の中に自然に組み込まれるべきものです。ここで大切なのは、計画を作るだけでなく、定期的に訓練して現場で使える状態にしておくことです。
drpの目的と役割
DRPは、ITシステムの復旧を最重要視して設計される計画です。社内のサーバー、データ、アプリケーションを、障害発生直後から元の状態までどの順で、どのくらいの時間で戻すかを決めます。RTO(復旧時間目標)やRPO(復旧時点の目標データ量)といった指標を設定し、どのバックアップが有効か、どの場所に台数を用意するか、どのようにバックアップデータを取り出すかが具体的に決まります。
この計画の目的は「ITの停止時間を最小化すること」と言い換えられます。たとえば、学校のネットワークが落ちた場合、どのサーバーをすぐにオンラインに戻すか、データは最新の状態にどう保つか、誰がどのデータを扱うのかを事前に決めておくのです。
DRPはBCPの一部として位置づけられることが多く、IT部門と事業側が連携して作成します。崩れたITの仕組みを速やかに回復させるための実務的な手順と道具を明確にするのがDRPの役割です。
bcpとdrpの違いを具体的な例で見てみよう
具体例として、地震が起きたときの対応を想像してみましょう。
BCPなら、事業を止まらずに、重要な機能を別の場所で動かす、代替手段を使うといった全体の動きを決めます。人材の配置、連絡方法、顧客への影響を最小化する作業順序などを含みます。
一方、DRPはITの復旧手順に絞って考え、サーバーを立て直す順序、バックアップデータのリスト、どのデータセンターを使うか、アプリをどの順で再開するかを具体的に決めます。
このように、BCPは「全体の流れ」を、DRPは「ITの戻り方」を、それぞれ別々にまたは一緒に設計します。以下の表でも違いを視覚的に整理します。
実務での作成手順とポイント
実務でBCPとDRPを作る手順は、まず現状の把握から始まります。業務の重要度を分析し、影響範囲を決め、優先度をつけます。次に、どんな災害が起きてもどう動くかの“手順”を文書化します。ここでは、連絡網、代替拠点、データのバックアップ場所、復旧の順番を具体的に書きます。訓練を定期的に行い、現場の声を反映して改善することが大切です。
具体的なポイントとして、関係部署との協力、現実的な代替案の設定、情報の統制、文書の最新性、そして「誰が何をいつ確認するか」のチェックリストを作ることが挙げられます。
また、表計算ソフトやクラウドツールを使って、RTO・RPO・責任者を一覧化すると管理が楽になります。以下の表は、BCPとDRPの要素を整理した簡易版です。
| 要素 | BCPの例 | DRPの例 |
|---|---|---|
| 目的 | 業務継続 | 復旧 |
| 主な対象 | 人・プロセス | IT・データ |
| 指標 | 優先度・連絡 | RTO・RPO |
ねえ、BCPとDRPの違い、どう伝える?簡単に言うと、BCPは「もし何か大きな事が起きても仕事を続けるための全体設計」、DRPは「ITを元に戻す具体的手順」です。つまりBCPが地図、DRPが地図の上に描く道順みたいな感じ。2つは別物だけど、学校のイベントを成功させるためにはどちらも必要です。普段の授業や部活動にも活かせる考え方なので、将来ITの仕事を目指す人にも役立ちます。
前の記事: « ガソリン代の値段の違いを徹底解説 地域別の価格差と節約のコツ
次の記事: cfp ghg 違いをわかりやすく解説:中学生にも伝わるポイント »





















