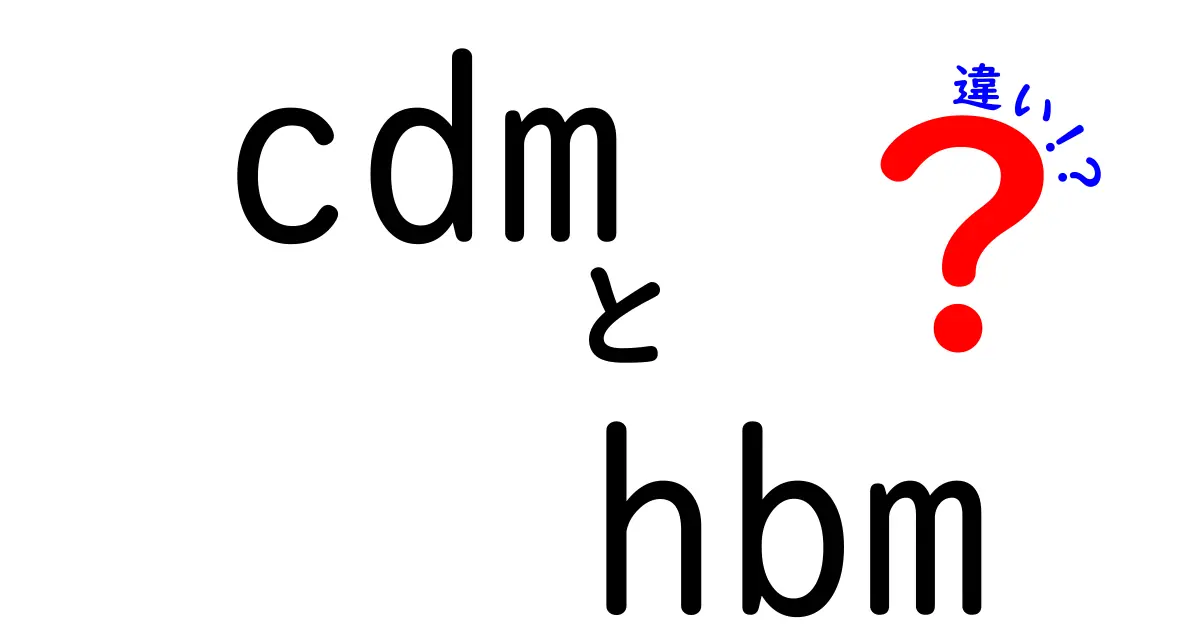

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CDMとHBMの基本を知ろう
CDMとはCommon Data Modelの略で、データの意味を標準化するための設計図のようなものです。企業や組織が持つさまざまなデータを、同じ言葉で表現できるようにする仕組みです。例えば顧客という概念は、名前・電話番号・住所などの属性を含み、別のシステムでは同じ意味を別の名前で表現することがありますが、CDMではその意味を統一します。
CDMを使うと、アプリ同士がデータをやり取りするときに、意味がずれることが減り、分析やレポートの精度も上がります。
要点 データの中身を揃えることが目的です。
HBMとはHierarchical Bayesian Modelの略で、データを階層的な枠組みで推定する統計モデルです。小さなサンプルでも共通の情報を取り入れて推定を安定させるための手法です。例えば学校ごとに成績データがあるとき、各学校の成績を独立に見るのではなく全体の傾向を共有して各学校の成績を推定します。これにより観測値が少ない学校でも過剰にばらつくことを防げます。
実務では教育医療マーケティングなどデータが階層的に分かれている場面でよく使われます。
使い分けの考え方 CDMはデータの表現と交換の標準化、HBMはデータからの推定・予測と不確実性の表現を目的としています。
実務での使い分けと具体的なケース
実務の現場ではCDMとHBMは同時に使われることが多く、それぞれの役割をはっきり分けることが成功の鍵になります。
CDMはデータ基盤を整えるための土台作りで、優れたデータガバナンスと良好なデータ品質を作ります。統一された定義により、データの取り込みやクレンジングが迅速になります。
HBMは分析の道具です。大量のデータを前提にすることもありますが階層を作って少ないデータを補うことができ、モデルの予測区間を明示できます。
実例として、ある企業がCDMで顧客の基本情報を標準化した後、HBMを使って地域別の購買傾向を推定する、といった流れが挙げられます。これにより新しいプロモーション施策の効果を地域ごとに予測でき、意思決定が速くなります。
- ポイント1: 使い分けの基本は役割の違いを理解すること
- ポイント2: データ品質と標準化は最初の投資として重要
- ポイント3: 階層の例として地域やクラスなどの比較が理解を深める
放課後、データサイエンス部の話題で HBM の話をしていた。友達は「階層ってどういうこと?」と困惑していたが、私は実例で説明した。学校ごとの成績データを一つの大きな物語として見ると、全体の傾向と各学校の違いを同時に味わえる。HBMはその“大きな物語の地図”を作る道具だと伝えると、彼も「なるほど、データの束がバラバラに見えなくなるんだね」と納得してくれた。CDMの話も合わせて、データの意味をそろえることが最初の一歩だと強調した。





















