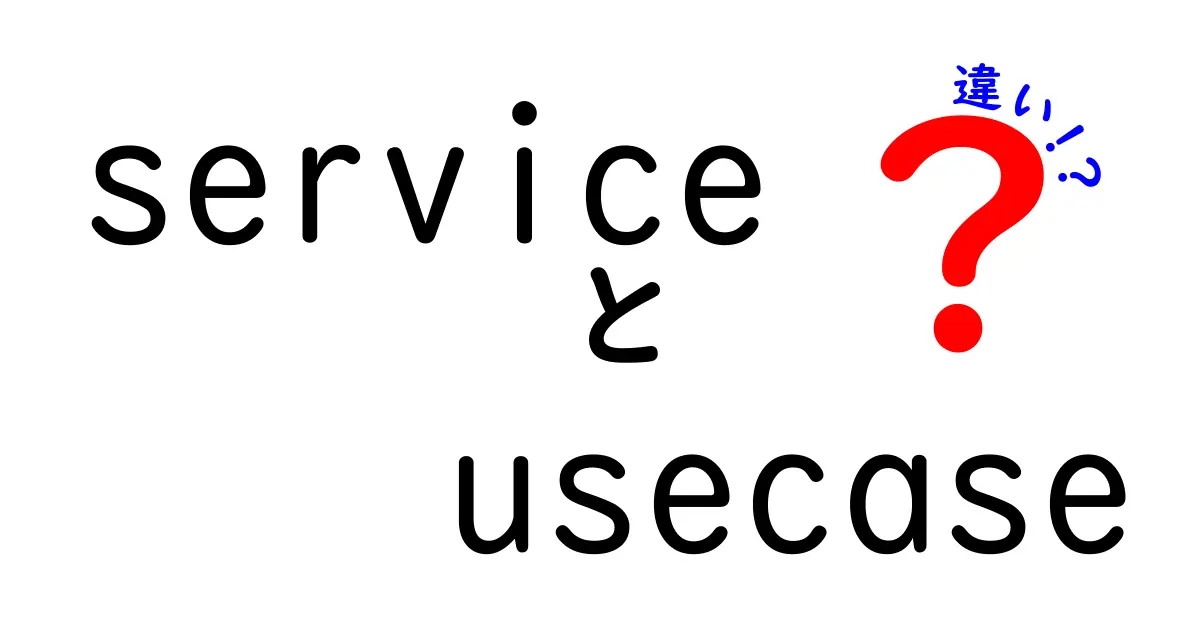

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サービスとユースケースの基本的な違い
サービスは、外部に向けて提供される機能の集合を指します。システムが実際に“何をできるか”という能力の総称であり、設計は全体の体験や信頼性、保守性を見据えた機能の配置と連携を考えます。例えばオンラインストアの決済機能、商品検索、通知機能などが一つのサービスとして組み合わさって動くと理解すると分かりやすいです。
このときの重要ポイントは、誰が使うかに関わらず、提供される機能の範囲と品質を決めることです。
次にユースケースは、特定のユーザーが達成したい目的を、具体的な手順や状況とともに描くストーリーです。「この人は今何をしたいのか」「どういう状況でどう行動するのか」「最終的にどの価値を得るのか」を明らかにします。ユースケースは、サービスの使われ方を現実的な場面で語るための道筋であり、機能の組み合わせを現場のありさまに落とし込む道具です。
この二つを混同しやすい理由は、実務での会話の中で「この機能があれば何とかなる」という発言が、同時に「この機能を使ってこういうことを実現するにはどういう流れが必要か」というユースケースの視点にも繋がってしまうからです。
結局のところ、サービスは“何ができるか”を定義し、ユースケースは“どう使って何を達成するか”を定義すると覚えるとシンプルです。
違いを実務で活かすには、まず要件を分解して両方の視点を分けて整理します。要件を機能レベルで洗い出すのがサービス、ユーザーの目的と行動の流れを描くのがユースケースです。さらに、設計段階で両方を対応づけると、機能が現場の目的にどう貢献するかが見えやすくなります。
実務での使い分けと注意点
プロジェクトでは、最初にサービスの範囲を決め、次にユースケースを作成します。アーキテクチャの上ではサービスは境界を示す契約、ユースケースはタッチポイントとユーザーの行動の連続性を示すシナリオとして扱います。
この組み合わせにより、機能追加が起こっても“顧客の目的にどう結びつくか”を検証しやすくなります。例えば新しい決済機能を追加する場合、サービスとしての範囲は決済関連の機能全体、ユースケースとしては「顧客が商品を選び、カートに入れ、決済を完了するまでの一連の流れ」を描く、といった形です。
ただし、混同を避けるために全員が共通の定義を持つこと、用語が現場の会議で揺れやすい場では、議事録に具体的な定義と例を付けることが重要です。
また、ドキュメントの目的を明確化することも大切です。サービス設計書は機能横断のガイドとして、ユースケースは開発者の実装指針として機能します。適切なツールとテンプレートを用いて、両方を並べて見せると理解が深まります。
ユースケースという言葉、実は“誰が何をするか”のストーリーを描くことに近いんだ。私は初めてこの概念を知ったとき、ゲームの攻略ルートみたいだなと思いました。つまり、主人公が何を目標に、どの順番で動くべきかを決めれば、迷わず進めるわけです。業務の場でも同じ発想で、ユースケースを描くと機能をどう使うかの“具体的な使い方”が見えるようになります。最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れると仕様が揺らぎにくくなり、作業の優先順位づけにも役立ちます。例えば、ショッピングの流れを一つのユースケースとして描けば、決済の安定性や遅延時の対応策まで連携して考えられるようになります。短い会話の中にも、使い勝手や価値の伝わり方が自然と現れます。





















