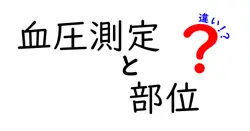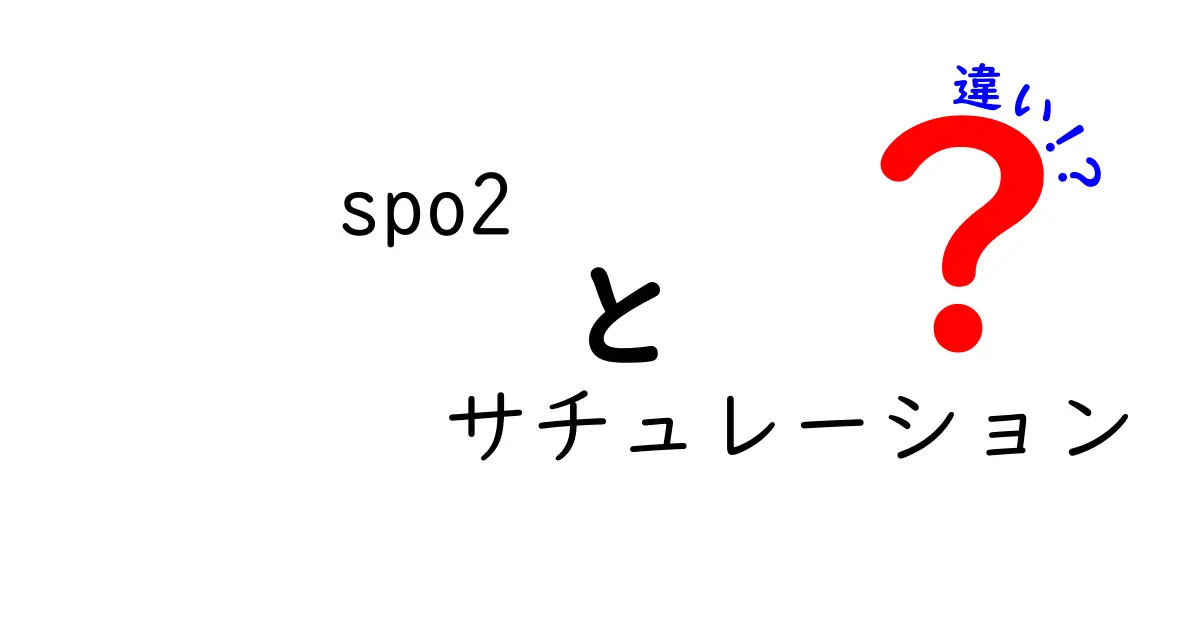

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
spo2とサチュレーションの基礎知識
この二つの言葉は似ているようで意味が少し異なります。SpO2は英語の血中酸素飽和度の略で、パルスオキシメトリという機器が推定する値です。サチュレーションは血液中のヘモグロビンが酸素で飽和している割合を表す広い概念であり、SpO2はこの飽和度のひとつの指標として使われます。つまりSpO2はサチュレーションの一部を示す数値です。
SpO2は動脈血酸素飽和度の概算であり、血液ガス検査で得られるSaO2とは別物です。SaO2は動脈血の酸素結合の正確な割合を示す指標で、臨床では動脈血採血を行って測定されます。SpO2は非侵襲的で繰り返し測定が容易という長所がありますが、厳密にはSaO2と同じ意味にはなりません。
機器の原理は、指先や耳たぶに光を当て、血液中のヘモグロビンの酸化状態の違いによる光の吸収の差を読み取るというものです。このため測定条件が整っていないと誤差が生じやすくなります。指の動き、ネイルポリッシュや濃い色、皮膚の色素沈着、低温状態などが影響します。さらに高度が高い場所、赤血球数の異常、一酸化炭素やメトヘモグロビンが多いとSpO2の読みが正確でなくなることがあります。こうした点を理解せずに数字だけを見て判断すると、適切な対応が遅れることがあります。
このふたつの違いを日常生活で理解しておくことは、安全に過ごすうえでとても大切です。
例えば風邪や発熱で呼吸が苦しくなったとき、スポーツの練習中に酸欠のリスクを見極める際、SpO2の変化がどこまで本物の飽和度の変化なのかを見極める練習になります。
また高所で生活する人や登山をする人は酸素の取り込み方が変わるため、SpO2の値を単独で判断するのではなく、SaO2や身体の感覚と組み合わせて判断することが重要です。
「SpO2」と「サチュレーション」の違いとは何か
ここでは、SpO2とサチュレーションの関係をもう少し具体的に整理します。サチュレーションは血液中のヘモグロビンが酸素をどれだけ結合しているかを指す広い概念で、SaO2やSpO2を含む言葉です。SpO2はこのサチュレーションのうち、パルスオキシメトリで非侵襲的に推定される数値を指します。つまりサチュレーションという大枠の中の一つの指標がSpO2です。これを覚えると、病院の説明や機器の表示を正しく読み解きやすくなります。
以下のポイントを押さえておくと、測定値を正しく解釈できます。
1) SpO2は“近似値”であり、SaO2の代わりにはなりません。
2) ネイルポリッシュ、指の動き、寒さ、低流量の測定条件は値に影響します。
3) CO中毒やメトヘモグロビン血症があるとSpO2が実際より高く見える場合があります。
4) 高地ではSpO2の低下が起きやすく、逐次の変化を追うことが大切です。
現場での測定のポイントと誤解を防ぐコツ
現場でSpO2を使うときには、いくつかのコツがあります。まず測定部位を安定させ、指に力が入らないようにリラックスさせること。次にネイルポリッシュがある場合は外してもらう、暗い場所でなく直射日光を避ける、動きが少ない状態で測定する、という基本を守ると誤差を減らせます。正しい解釈のコツは、数値だけを見ず、体感や呼吸の有無、血圧の状態、患者の病歴を合わせて判断することです。必要であればSaO2の検査や血ガス検査を補助として使い、臨床判断の材料を増やすと安心です。