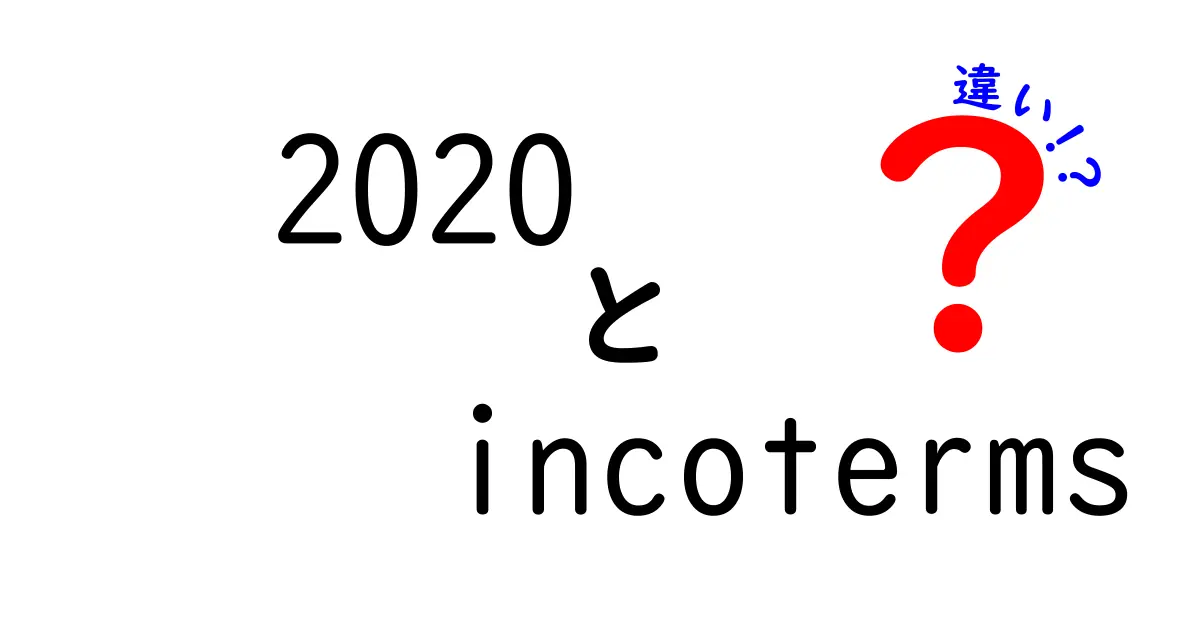

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
2020年版 Incotermsの違いを徹底解説
ここでは世界の貿易ルールの中で「Incoterms(インコタームズ)」の2020年版の違いを、初心者にも分かるように丁寧に解説します。Incotermsは売り手と買い手の責任範囲、費用の分担、危険の移転点を定める国際ルールです。2020年版では、DAT→DPUの名称変更、輸送段階ごとの責任範囲の明確化、保険の扱いの整理などが特徴として挙げられます。貨物を海外へ出荷する際には、契約書の条項と実務の運用が一致しているかを確認することが大切です。この記事では、11種類のIncotermsの基本的な違いと、現場での選び方のコツを、できるだけ分かりやすく紹介します。
1. 2020年版と以前のIncotermsの主な違い
まずは基礎を整理します。2020年版での大きな変化は三つです。第一に、DATという用語が
ここで重要なのは、「どのIncotermを使うか」だけでなく「そのIncotermの具体的な適用方法を契約書にどう落とすか」という点です。例えば、同じCIFでも保険の最低補償額や適用される条項の細かな条件を契約書に盛り込むことで、予期せぬトラブルを減らすことができます。実務では、輸出入の国・地域、貨物の種類、輸送モード、頻繁な取引相手の有無などを総合的に考慮して最適なIncotermを選ぶことが大切です。
2. 11のIncotermsとその使い分けの要点
以下の11種のIncotermsは、どの場面で使われるかが異なります。それぞれの「リスク移転の時点」「費用負担の範囲」「輸出入の手続きの責任」を整理しておくと、契約書の作成や実務の発注・手配がスムーズになります。
このセクションでは、表とともに実務に直結するポイントを長く説明します。まず代表的なものから順に整理します。
(表は後述の表をご参照ください)
この表は実務での基礎となる違いを一目で把握するのに役立ちます。どのIncotermを選ぶかは、貨物の性質、輸送方法、納期、リスク許容度、コスト管理の方針によって決まります。表を参照しつつ、契約書には各条項の適用範囲と責任を明記することが重要です。
3. 実務での選び方と注意点
実務でのIncotermsの選択には、以下のポイントを順番に確認することが有効です。第一に、輸送モードと港・空港の有無を確認します。海運だけなのか陸・空・海の混載なのかで適切なTermが変わります。第二に、費用の分担と納期を見極めます。どこまでを売主が負担し、どこから買主が負担するのかを契約書に正確に記載します。第三に、保険の有無と補償内容を確認します。特にCIF/CIPなど保険の有無は大きな差になります。第四に、輸出入手続きの責任範囲を整理します。輸出許可や輸入通関の手続きは誰が担当するのかを事前に決めておくとトラブルを回避できます。最後に、現場の実務での柔軟性を考え、必要に応じて追加条項を契約書に組み込むことをおすすめします。
4. よくある誤解とQ&A
よくある誤解としては、「同じFCAでも国や輸送方法が変わればリスクが大きく変わる」という点」、また「EXWは最も安全・楽な条件だと思われがち」という認識です。実際にはEXWは売主の義務が最も少なく、買主の作業負担が大きくなります。別の誤解は、「CIFは必ず保険がつく」という点です。保険の範囲や適用条件は契約次第で変わるため、条項をよく確認しましょう。実務での質問例としては、輸出国によって必要な書類が異なる場合や、港湾の取り扱い手順が変わる場合などがあり、その都度条項を見直すことが重要です。
まとめ
2020年版のIncotermsは、DATのDPUへの名称変更をはじめ、リスク移転のタイミング・費用負担の整理、保険の扱いの明確化など、現代の国際貿易に即した改定が加えられました。11種のIncotermsを状況に応じて正しく選択し、契約書に具体的な運用条項を落とすことが、トラブルを避け、納期どおりの輸送を実現する鍵です。これから貿易を始める人も、すでに取引を進めている人も、Incotermsの基本を理解して実務に活かしましょう。
ある日の放課後、友達のミナミと私は学校の図書室で Incoterms 2020 の話をしていた。ミナミは『海外に物を送るとき、誰がどんな責任を負うかって難しそう』と言った。私は彼女に、まず何を輸送するのか、どのモードで運ぶのか、到着地はどこかを一緒に考えることを提案した。たとえばEXWなら売主の義務は最小限で、買主が全て自分で手配する。逆にDDPなら売主がほとんど全てのコストと手続きを肩代わりする。こうした違いを表で見比べるだけでも、取引相手との契約書に落とすべきポイントが見えてくる。私たちは一緒に、11種のIncotermsがどんな場面で適用されるのか、どんなリスクがどこで移るのかを、シンプルな例を交えつつ具体的に考えた。練習として、実在の商品Aを例に、EXWとFCAとDDPを比較する演習をしてみると、条項の違いがぐっと身近に感じられた。こうした理解を深める作業は、将来の貿易の関係者として非常に役立つと私は感じた。最後に、いちばん大事なのは「契約書に書くこと」。頭の中だけで終わらせず、具体的な輸送経路・費用・保険の条件を文書化すること。それが、安心して物を動かす第一歩になる。





















