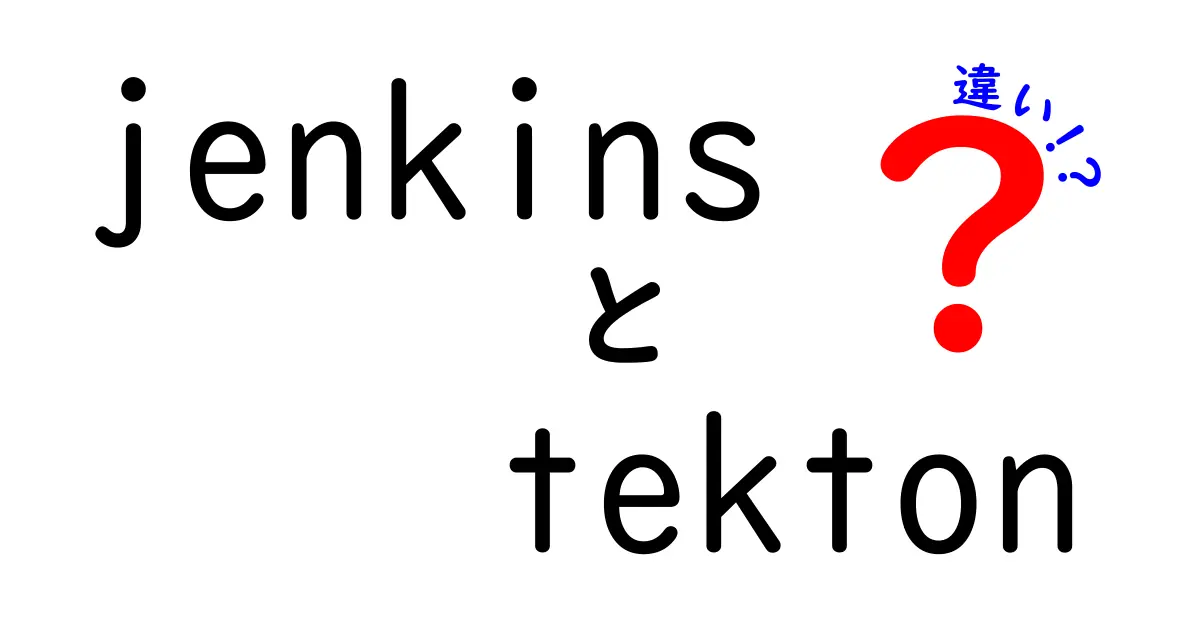

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:jenkinsとtektonの基本と違いの全体像
この二つのツールは、ソフトウェアを作るときの「自動化の仕組み」を願う人にとって、ほぼ欠かせない存在です。しかし、設計思想や使い方は互いにかなり違います。
Jenkinsは長い歴史を持つ自前サーバー型のCI/CDツールで、プラグインを追加して機能を拡張します。多くの企業で既に導入実績があり、さまざまな環境に対応します。
一方、 TektonはKubernetes上で動く、CRDベースのCI/CDツールです。パイプラインの要素はリソースとして定義され、Kubernetesの仕組みと深く結びついています。
この章では、両者の基本的な位置づけ、アーキテクチャの違い、何が得意で何が難しいのかを整理します。強調したいのは、両者は「目的は同じでも使い方の前提が異なる」という点です。
最適な選択は、你の運用環境と求める自動化の粒度に依存します。
技術的な違いを詳しく比較するポイント
ここでは、実際の使い分けで押さえるべきポイントを、分かりやすく整理します。
まず前提となるのは「実行場所」と「パイプラインの定義方法」です。
Jenkinsは外部サーバーとして動き、プラグインとGroovyベースのJenkinsfileでパイプラインを定義します。これは、非Kubernetes環境でも柔軟に動かせる一方、プラグインの品質に依存する側面もあります。
TektonはKubernetesネイティブで、TaskやPipelineといったリソースを組み合わせてパイプラインを構築します。リソースとして管理されるため、クラスタの権限・RBAC・ネームスペースの境界が自然と組み込まれます。
この先には、拡張性と運用の負荷、再現性とセキュリティの観点が続きます。
Jenkinsは豊富なプラグイン群で多様な要件を満たしますが、プラグインの管理と互換性維持が課題になることがあります。
Tektonは機能の分解が明確で、Kubernetesと連携しやすい反面、「全てを自分たちで組む」設計が必要になることがあります。
最後に、パイプラインの再現性とセキュリティを見ていきます。
Tektonはクラスタ全体のリソースとして扱われ、再現性と分離が高い設計になります。Jenkinsはジョブごとの実行環境の独立性をどう確保するかがポイントです。
この表から、両者のアプローチの根本的な違いが見えてきます。
結論として、「短期的な実装の柔軟性を重視するならJenkins、長期的なクラスタ運用と再現性・分離を重視するならTekton」が分かりやすい判断基準です。ただし、実務では両方を併用するケースも増えてきています。例えば、既存のJenkinsジョブを徐々にTektonへ置き換える、あるいは特定の新規パイプラインのみTektonで実行するといった段階的な移行も現実的です。
どちらを選ぶにしても、組織の技術レベル、運用体制、セキュリティ要件をよく考慮して決めることが重要です。
ある放課後の会話。友だちがTektonを「Kubernetesの部品を組み立てるレゴみたいなもの」と説明してくれた。私は「Jenkinsのプラグインの数は豊富だけど、時に依存関係が重くなるよね」と返す。Tektonは最初は難しく感じても、Kubernetesの世界に慣れてくると、パイプラインの部品を組み替える感覚で新しい自動化を作れる。お互いの良さを認めつつ、現場の要件に合わせて使い分けるのが賢い選択だと気づく。結局、道具よりもゴールと運用の設計が大事だと実感した。





















