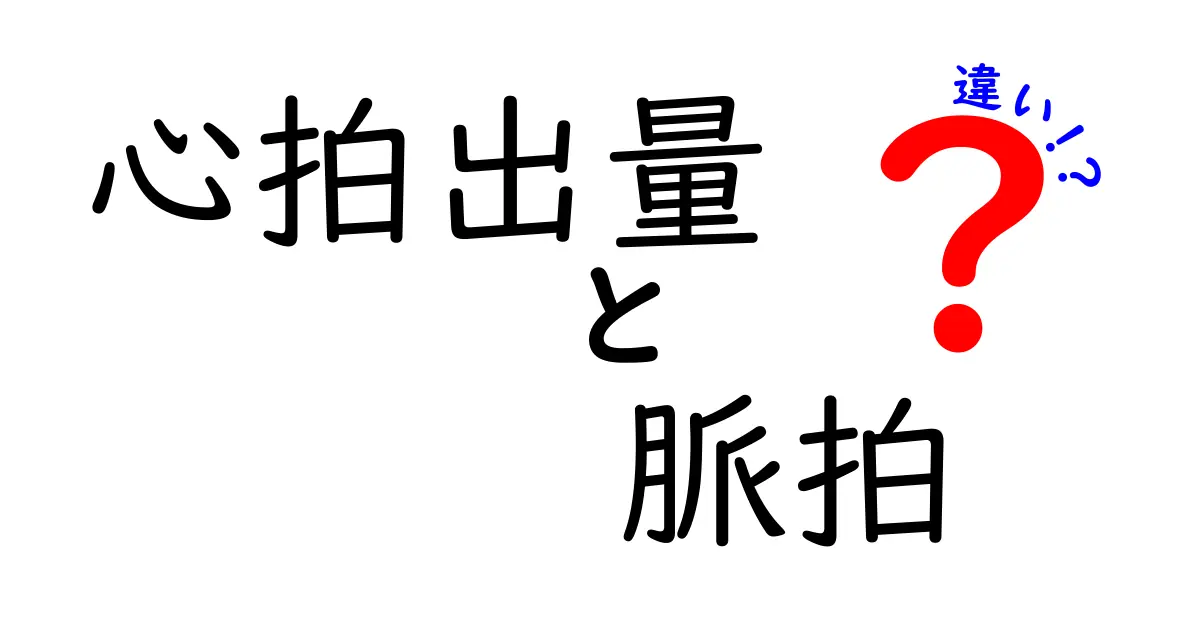

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
心拍出量と脈拍の違いを徹底解説
心臓は私たちの体の中心で鼓動を続けるポンプの役割を担っています。心拍出量と脈拍という言葉は、どちらも心臓の動きを表しますが、意味するところは異なります。まず脈拍は1分間に心臓が打つ回数、つまり心臓のリズムそのものです。これを知ると、運動中の快適さや安静時の状態をざっくり判断できます。次に心拍出量は1分間に送り出される血液の量のことを指します。SVは1回の拍動で送り出される血液量、HRは1分間の拍動数です。これらを掛け合わせるとCOと呼ばれる1分間の血液総量が出ます。
この二つは密接に関係しています。運動を始めると、体は筋肉へ酸素を届けるためにCOを増やす必要があり、HRが上がるだけでなく SV が変化してCOを増やす方法を選ぶことがあります。若い人と高齢者ではSVの変化のしかたが少し違うこともあり、同じ運動量でもCOの増え方には個人差があります。こうした点を理解しておくと、体の反応を観察して適切なペース配分を考える手助けになります。最後に、日常生活での指標として正常な安静時の脈拍や運動時の変化を見る習慣を持つと、自分の体調管理に役立つことがあります。
心拍出量とは何か
心拍出量は、1分間に心臓が送り出す血液の総量のことです。SVとHRの掛け算で求められ、COと呼ばれることもあります。SVは1回の拍動で送り出される血液量で、個人差があります。安静時には約70mL前後ですが、運動をすると筋肉が酸素を必要とするためSVが増え、同時にHRも上がります。結果としてCOは数値として上昇します。
心拍出量が増えると、体はより多くの酸素と栄養を筋肉へ届けることができます。反対に、心臓の収縮力が弱いとSVが低下し、COも低くなることがあります。前負荷と後負荷、そして収縮力といった心臓の状態を左右する要因がCOに影響します。これらを理解すると、運動の強度を自分の体調に合わせて調整しやすくなります。運動不足の人は安静時HRは低めですが、長時間の作業や暑さでHRが上がることがあります。体温が上がると心臓へ血液を送り出す努力が増え、COの変化を感じやすくなるのです。
脈拍とは何か
脈拍は心臓の拍動の回数を指す数値です。1分間に心臓が何回鼓動するかを表します。安静時にはだいたい60〜100回/分が標準と言われますが、年齢、性別、体力、気温、ストレスなどで変化します。練習を積んだ人は安静時の心拍数が低めになる場合が多く、体が効率よく血液を循環できるようになります。脈拍を測るときは、手首の動脈や首の動脈を触れて数を数えます。緑色の指の腹で優しく押さえ、数えるのがコツです。速さが変わる理由には、体は酸素を多く運ぶ必要があると感じるとき、交感神経が働きHRを上げるためです。逆に休んでいるときは副交感神経が優位になりHRは下がります。脈拍だけを見て判断するのは難しいですが、COと合わせて考えると、体の疲れ具合や回復のサインを読み解く手掛かりになります。
今日は心拍出量についての小ネタを話します。走るときに呼吸が乱れやすいと感じることがありますが、それは心拍出量が増える局面で血液が全身に行き渡る練習をしている証拠です。心拍出量は「ただ速く打つ」だけでなく「強く押し出す力」が大事で、それがSVの増加につながります。心拍数だけを見て急いで判断するのではなく、SVの変化とどう連携してCOがどう上がるのかを考えると、トレーニングの効率が変わります。友だちとスポーツの話をするとき、COが増えると「体が前へ進むパワーを感じる」という感覚になることがあります。
次の記事: アセチルコリンとコリンの違いとは?中学生にもわかる徹底解説 »





















