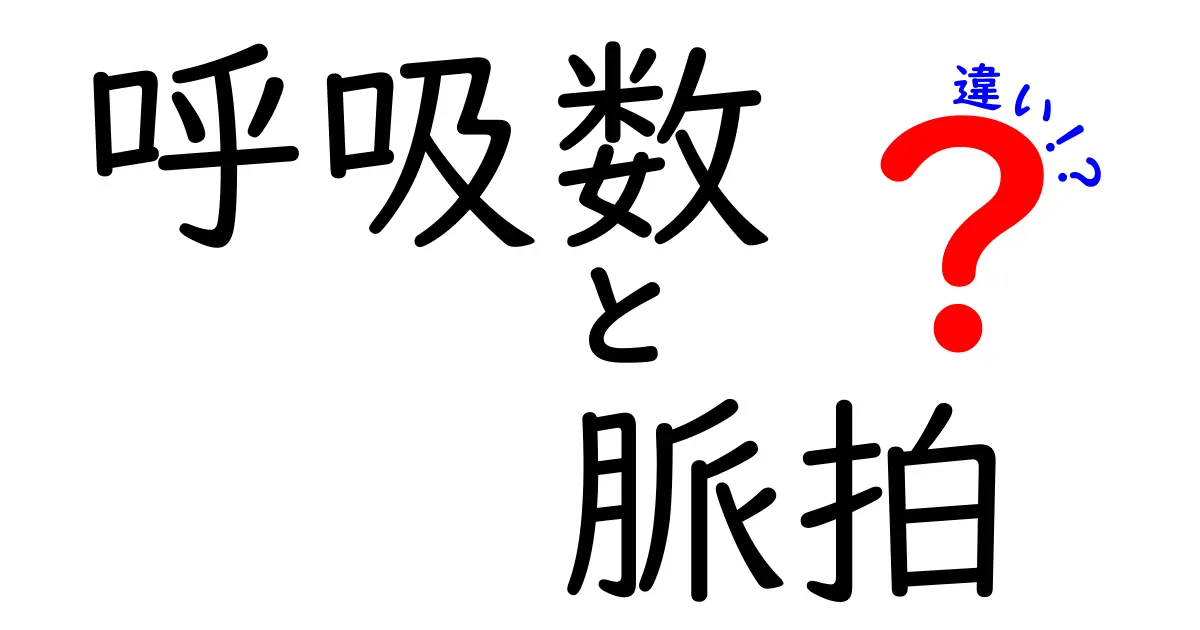

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
呼吸数と脈拍の違いを理解するための基本ガイド:体のリズムが伝える信号を読み解くコツ、測り方のポイント、日常生活での活用法、そして年齢別の目安をやさしく解説します。呼吸数は肺の換気の回数を意味し、脈拍は心臓が作る拍動の速さを表します。これらは似ているようで異なる体の仕組みを映す鏡ですが、体調が変わるとどんな兆候が現れやすいのか、運動後・睡眠不足・ストレスなどの場面でどう変化するのかを、専門用語を避けて身近なたとえ話を使いながら丁寧に説明します。さらに、身近な道具での測り方、家庭や学校での観察のコツ、そして年齢別の一般的な目安を、図解的に理解できるように整理します。学級の授業だけでなく、毎日の健康チェックにも活かせる実践的な内容です。
まずは基本を押さえましょう。呼吸数とは1分間に肺が動く回数のことです。体がエネルギーをたくさん使うときや、緊張しているとき、風邪や発熱があるときなどには自然と増えることが多いです。
一方、脈拍は心臓が収縮して血液を全身へ送る「鼓動」の速さを表します。安静時にはおよそ60〜100回/分で推移しますが、運動後やストレスを感じているときには上がることがあります。これら二つの指標は、体がどう動いているのかを示す“別々のサイン”であり、それぞれの変化には原因があるのです。
次に測り方のコツです。呼吸数は、静かな場所で1分間、胸や腹部の動きを目視または手で触れて数えます。脈拍は手首の橈骨動脈や首の頸動脈を指で軽く押さえ、同じく1分間数えます。測定するタイミングは、安静時・運動後・就寝前など複数の場面で比較すると、体の反応がよく見えます。急に数が大きく変わるときは、体が“今この瞬間どう感じているのか”のサインかもしれません。
ここからは年齢別の目安をざっくりと整理します。表を使うと分かりやすいので、以下の表を参考にしてください。
最後に、日常生活での活かし方です。呼吸数と脈拍の変化を毎日ちょっとしたメモに残しておくと、体調の小さな変化にも気づきやすくなります。疲れがたまって眠りが浅い日には、呼吸が浅く早くなることがある一方、深呼吸を取り入れると心拍の乱れが整いやすくなることがあります。睡眠前の就寝儀式として深呼吸を取り入れるのもおすすめです。体のリズムを知ることは、病気の早期発見にも役立つシンプルな方法です。ここで紹介したポイントを日頃の健康チェックに取り入れ、異常を感じたときには無理をせず医療機関に相談しましょう。
補足:測定の注意点とよくある誤解
測定には「静かな状態であること」「同じ場所で測ること」「1分間きちんと数えること」が大切です。
緊張や寒さ、激しい運動の直後には数値が変わりやすく、短い時間だけの測定では正確な判断が難しくなります。子どもだけでなく大人にも多い誤解として、「数が多いほど体調が良い、少ないほど悪い」と考えることがあります。しかし呼吸数と脈拍の適正範囲は「安静時と活動量」「年齢・体格」で変わるため、単純に大小を比較するのはNGです。複数の場面で変化のパターンを観察し、必要に応じて医療機関へ相談するのが安全です。
放課後、友だちと呼吸数について雑談してみた。呼吸数は1分間に呼吸が何回起きているかを示す指標だけど、運動後や緊張時はすぐに増える。脈拍は心臓の鼓動の速さを表す別の指標で、呼吸数と一緒に体の状態を見せてくれる。僕が気づいたのは、同じ呼吸数でも、走ってからすぐと休んでからでは感じ方が違うこと。呼吸を深く整えると心拍が落ち着くこともある。こうした雑談を通じて、数えるだけでなく、体が何を伝えようとしているのかを想像する力がつくんだ。





















