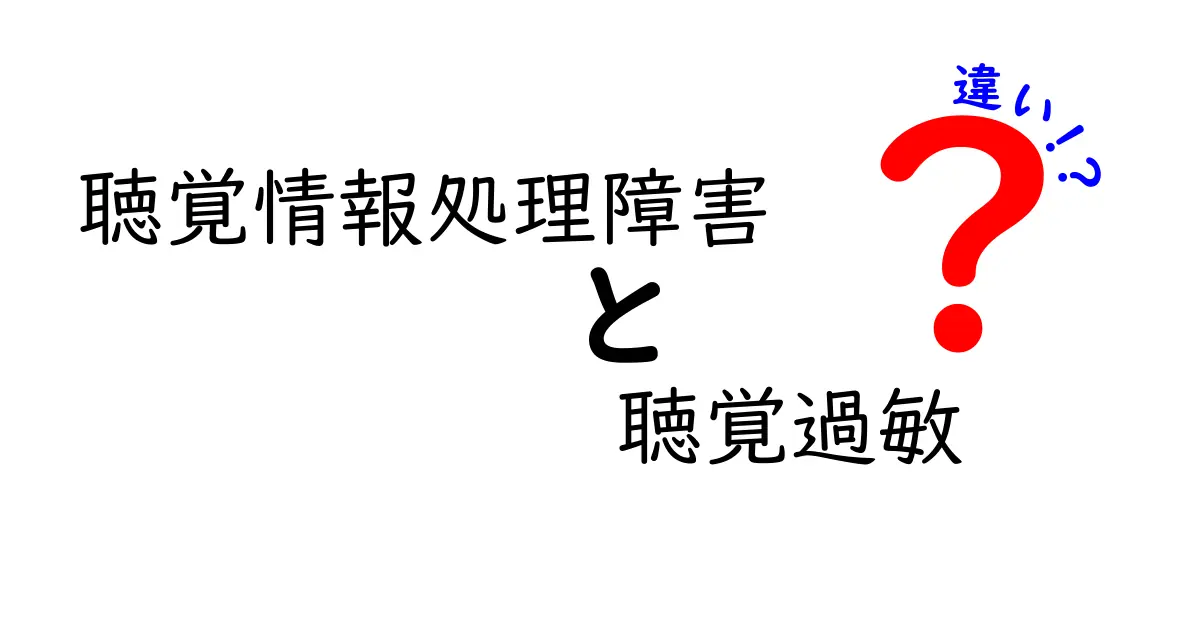

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
聴覚情報処理障害と聴覚過敏の違いを知るための基礎知識
聴覚情報処理障害は耳の音そのものが聞こえにくいのではなく、脳が音を整理し意味づけする過程で困難が生じる状態です。
この特徴は学校の授業や日常の会話で特に目立ち、同じ音量の話し声が混ざってしまい、要点がつかめない場面が生まれやすくなります。
思考の連携がうまくいかないと、聴覚情報を言語として処理する力が追いつかず、理解の遅れや指示の取りこぼしが起き、学習のリズムが崩れやすくなります。
原因は単純に耳の器官の病気ではなく、脳の聴覚情報処理のネットワークの発達や統合が影響していると考えられ、遺伝的素因や環境要因の影響も指摘されています。
診断には専門家による評価が必要で、音の聞こえ方自体に異常がない場合が多いのが特徴です。治療というよりは適切な環境設定と学習支援を組み合わせることが大切で、音の刺激を減らす工夫や視覚情報との組み合わせによる補助が有効です。
また周囲の理解も重要であり、授業中の指示を短く区切って伝える、重要なポイントを黒板と口頭の両方で示すといった工夫が役立ちます。
聴覚情報処理障害とは何か
この障害は子どもだけでなく大人にも起こります。特徴としては授業中の話し声が混ざって理解が遅れる、指示を受け取るのが難しくなる、音源の整理が苦手で会話の相手の言葉を正確に拾いにくい、読み書きの学習が影響を受ける、周囲の音が多い場所で集中が続かないといった現象が挙げられます。脳の聴覚情報処理のネットワークの働きが強く関係しているため、環境音の多い場所での困難さが顕著になるのが特徴です。日常生活では友人との会話をスムーズにするための補助として視覚情報の活用、授業での指示を短く区切る、音声以外の手がかりを増やすといった支援が有効です。診断後は個別の学習支援計画に合わせて、家庭と学校が連携して環境を整えることが重要になります。
聴覚過敏とは何か
聴覚過敏は音そのものが過剰に大きく感じられる状態で、通常は感じないはずの細かな音が痛みや強い不快感を伴って聴こえることがあります。これは耳の器官の問題というより脳の音の感受性の調整が崩れている結果として起こることが多く、日常の生活音や教室の換気扇の音、電車の走行音などが耐え難く感じられる場面が増えます。支援の基本は音の刺激をコントロールしつつ、徐々に音の環境に慣れる訓練を少しずつ取り入れることです。ノイズキャンセリング機能付きの耳栓やヘッドホンの活用、静かな場所での休憩、視覚情報の追加といった対策が役立ちます。痛みや強いストレスを感じる場面を減らすためには、学校と家庭が協力して生活リズムを整え、過度な刺激を避けつつ、必要な音を正しく聞き取る工夫が大切です。
生活場面での見分け方と支援のコツ
聴覚情報処理障害と聴覚過敏は似た場面にも現れることがありますが、日常の対応は異なります。授業中のトラブルを減らすには指示を箇条書きで渡す、視覚的な補助資料を増やす、静かな場所での休憩を入れるといった工夫が有効です。聴覚情報処理障害がある人には音を分離する訓練や、注意の焦点を言語以外の手がかりで支援する方法が適しています。聴覚過敏の人には音の刺激を段階的に増やす"階段的 exposure"を専門家の指導のもと実施することが効果的です。さらに家庭では音の環境を調整すると同時に、子どもの感情表現を受け止めることが大切です。具体的には日課表を共有し、ストレスを感じた時の対処法を事前に話し合い、必要時には休憩の合図を決めておくと安心感が生まれます。
ねえ聴覚過敏の話、最近友だちとした雑談なんだけどさ。音が大きくなると急に頭が痛くなる感じ、教室の換気扇の音が響くだけで集中力が飛ぶ。私は最初それをただのわがままだと思ってたんだけど、実は体に起きる防衛反応の一種だったみたい。音が過剰に処理されると体が疲れ、耳が張り裂けそうになる。だから友だちの話をゆっくり聴くためには静かな場所を選ぶとか、イヤホンで音を緩和するとか、そういう配慮が必要なんだと知った。話の途中で耐えられなくなると、言葉より先に自分の体が出してしまう。そんな時は深呼吸をして一旦休む。周囲の人が理解してくれると、本人はまた次の音に向けて一歩踏み出せる。こうしたちょっとした配慮が、学校生活を楽にしてくれるんだと感じた。
前の記事: « 前庭と半規管の違いを徹底解説!耳のバランスを決める2つの仕組み





















