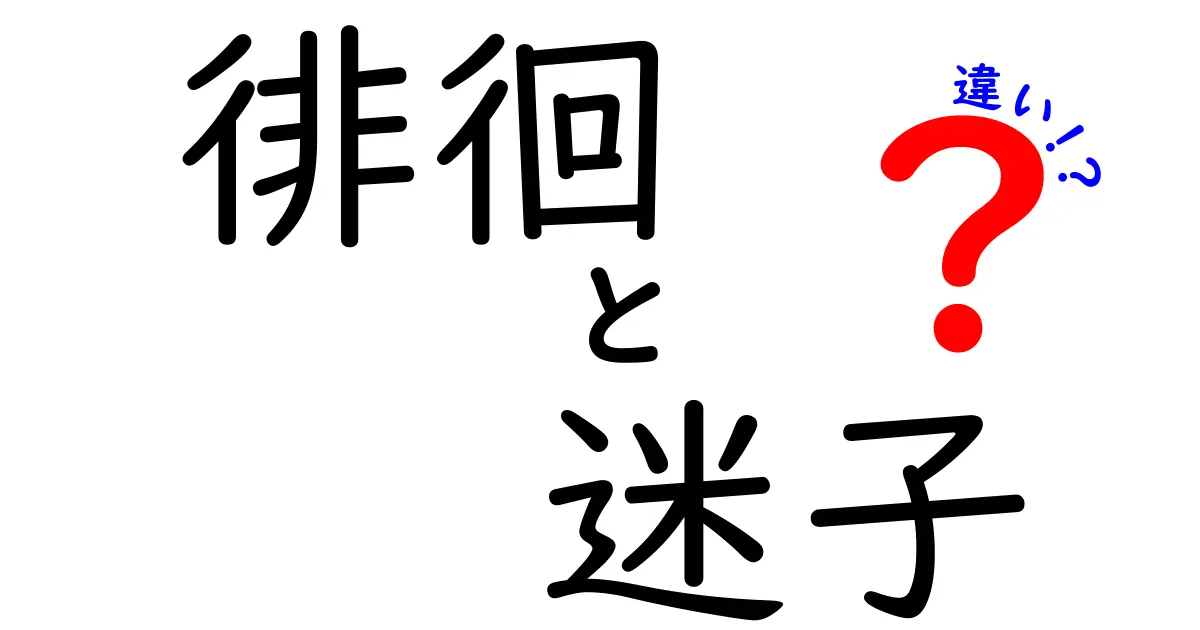

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
徘徊と迷子の基礎知識
徘徊と迷子は日常で混同されがちな言葉ですが、意味や背景には大きな違いがあります。徘徊とは、認知機能の低下や混乱を背景に、特定の目的を持たずに周囲を歩き回す行動を指すことが多いです。高齢者の認知症の初期や中期で見られることが多く、同じ場所を行き来する、部屋から部屋へ移動する、扉の前で足を止めるといった動きが特徴です。
この動きには本人の”出口や安全な場所を探す”という内的な動機が潜んでいることがありますが、安全を確保する介入が必要になる場面が多いのも特徴です。対して迷子は、特定の目的地を見失い、現在地と目的地の関係性が断たれてしまった状態を指します。目的地の喪失・方向性の混乱が主体で、子どもや経験の浅い場所での移動時に顕著になることが多いです。迷子の人は住所や家の場所を思い出せず、近くの大人に頼ったり、道を尋ねたりする場面が多く見られます。
ここで重要なのは、徘徊と迷子の背景が異なる点です。徘徊は内的な混乱と不安が背景にあるとされ、自己の安全を確保するための無意識的な動きとして現れることが多いです。迷子は外部刺激や環境の影響を受けつつ、目的地を見失った状態であるため、外部支援を受けやすい場面が多いのです。徘徊と迷子はしばしば同時に起こることもあり、見分けが難しくなる場合がありますが、背景を理解すると適切な対応が見えてきます。
この知識は家族、学校、地域での見守り方を決める際の基本になります。徘徊と迷子を正しく区別することで、本人の安心感を保ちながら素早い安全確保が実現します。
違いを見分けるサインと事例
現場で「徘徊か迷子か」を判断するには、いくつかのサインを観察することが有効です。以下のポイントを意識すると見分けやすくなります。
徘徊のサインとしては、同じルートを繰り返す、時間帯によって動き方が変わる、目的地が特定しにくく、会話の内容が断片的である、周囲の刺激に反応して歩き回る、自己を落ち着かせるための行動(服を整える、手を握るなど)がある、などが挙げられます。こうした行動は認知機能の低下と結びつくことが多く、本人が「ここに居場所を見つけたい」という欲求によって生じることが多いです。
迷子のサインは、目的地の喪失が中心で、現在地を思い出そうとするが思い出せない、道を尋ねる、住所や名前を伝えられない、家族と離れた場所で不安を強く訴える、道順の再現が難しい、などが見られます。迷子は外部環境の影響を受けやすく、場所が人混みだったり新しい建物だったりすると混乱が深まることがあります。
具体的な事例として、学校の校外学習中に子どもが「帰り道がわからない」と言い出す場合は、迷子の可能性が高いです。一方で、高齢者が同じ公園内を同じ道を何度も往復する場合は徘徊の可能性が高いと判断されることがあります。状況を一度に判断しようと焦らず、周囲の人と協力して状況を把握することが大切です。
見分けが難しいケースも多いので、安全第一で対応し、専門家の助言を求めることが重要です。
実生活での見分け方と対策
実生活では、徘徊・迷子の両方に対応するための基本ルールを決めておくとスムーズです。まずは落ち着いて話しかけることが大切です。焦って怒鳴ったり追いかけたりすると本人の不安が増し、状況が悪化することがあります。名前を呼び、相手の目を見て穏やかな声のトーンで接してください。次に、現在地と目的地のヒントを探ります。徘徊なら「ここは学校の正門の前か」「この広場で待っていてほしい」といった具体的な指示が有効です。迷子であれば「今ここはどこですか」「あなたの家はどこですか」といった質問を使い、住所や連絡先を思い出す手がかりを引き出します。
対応の基本は三つです。第一に安全確保。危険な場所(道路、階段、車の近くなど)から離し、近くの大人や警察に助けを求めます。第二に情報収集。本人の名前・自分の住所・連絡先・家族の連絡先などを把握します。第三に周囲の協力。学校や地域の連絡網、保護者会、地域包括支援センターなどへ連絡します。
予防策としては、身元を示すIDカードや連絡先を身につける、写真を定期的に更新しておく、家の鍵や建物のセキュリティを見直す、外出時には同行者を確保する、などが挙げられます。学校や自治体と連携して「徘徊・迷子対策マニュアル」を作成しておくと、緊急時の対応が迅速になります。以下の表は、徘徊と迷子の場面別の対応を簡潔に整理したものです。場面 徘徊の対応 迷子の対応 屋外で発生 安全確保、周囲の人に協力を依頼、警察へ連絡 現在地の確認、家族への連絡、警察へ連絡 自宅内で発生 危険箇所の排除、声掛けで落ち着かせる 居場所の特定、同居人や学校へ連絡 連絡先が分からない場合 写真付きIDカードの提示を促す 最寄りの公共施設へ誘導、警察へ相談
徘徊と迷子の違いを理解し、適切な対応を準備しておくことは、家族や教育現場での安全を高めます。
最後に、地域社会としての協力体制を整えることも重要です。地域の見守り活動、学校・自治体の連携、医療・介護の専門家のアドバイスを受けることで、より安全な環境を作ることができます。
まとめと学び
徘徊と迷子は似ているようで背景が異なり、対応の仕方も変わってきます。徘徊は内的な混乱と不安が背景にあることが多く、安全な居場所を求める動きが中心です。一方、迷子は目的地の喪失や方向感覚の混乱が中心で、現在地を把握する手がかりを探す場面が多いのです。現場では、落ち着いて話す、現在地と目的地を確認する、周囲の協力を得る、そして必要に応じて警察や自治体の支援を求める、という三本柱を軸に対応します。適切な対策を日頃から準備しておくことで、万一の事態にも迅速かつ安全に対応できるようになります。最後に、家族や学校、地域が協力して、本人の安心と安全を最優先に考えることが大切です。
小ネタ: 私が子どもの頃、徘徊と迷子の違いについて祖母と話したことを思い出します。祖母は「徘徊は心の中の地図がズレているようなもの。目的地がなくても歩くことで自分を安定させようとするんだ」と言い、迷子は「今いる場所が突然わからなくなってしまう瞬間の不安さ」と説明してくれました。その言葉を聞いてから、私は現場で子どもと高齢者に接するとき、彼らの心の地図を一緒に探すことの大切さを意識するようになりました。徘徊と迷子を分けて考えることは、ただの言葉の違いではなく、相手の心と安全を守る実践的な手がかりになるのです。だからこそ、私たちは状況を観察し、落ち着いた対応と周囲の協力を組み合わせていく必要があるのです。





















