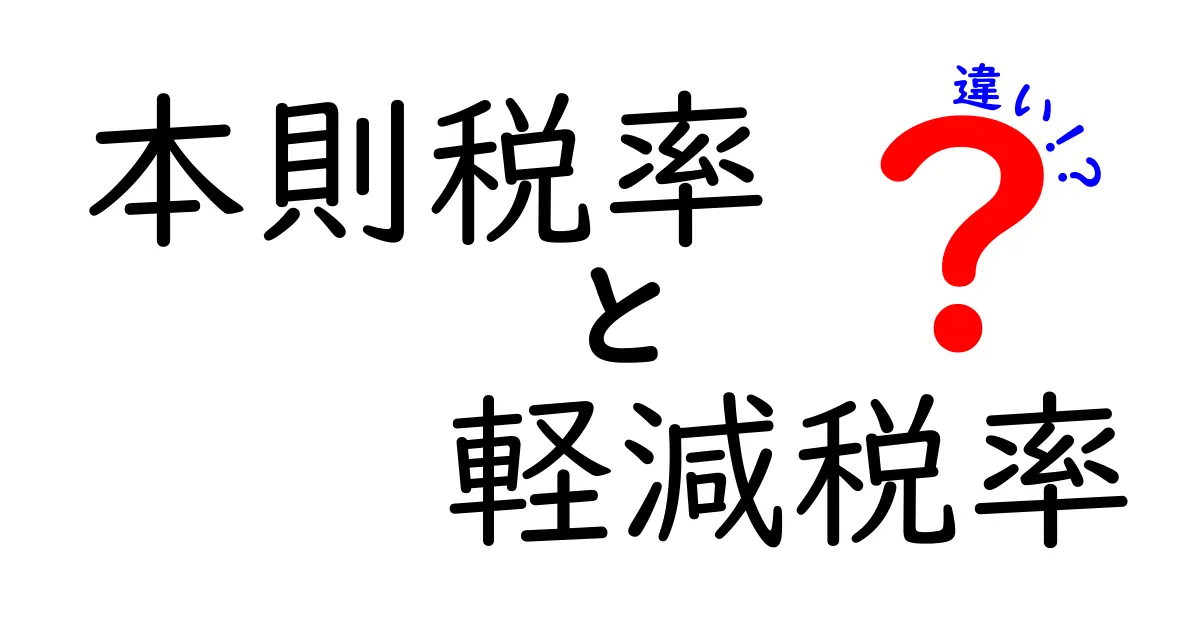

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
本則税率と軽減税率の基本的な違いとは?
日本の消費税には、本則税率と軽減税率という2つの税率があります。
本則税率は普段私たちが買い物で支払う基本的な税率で、2024年現在は10%となっています。
一方で、軽減税率は特定の品目に対して、消費者の負担を少なくする目的で導入されているもので、8%の税率が適用されます。
この制度は生活に密着した食品などの価格を抑えるための施策であり、税率が異なることにより、消費税がより公正かつ分かりやすくなっています。
本則税率は、基本的にすべての商品やサービスに適用されますが、軽減税率は主に飲食料品や新聞など、私たちの生活に欠かせないものに限られています。
つまり、同じ消費税でも商品によっては税率が違うことを理解しておくことが大切です。
消費者としては、買い物の中でどの品目が軽減税率の対象なのか、判別するポイントを知っておくと便利です。
このように、本則税率と軽減税率は目的や対象品目が異なるため、しっかり理解しておくことで納得しやすくなります。
本則税率と軽減税率の具体的な対象品目とその違い
本則税率(10%)は基本的にすべての商品とサービスに適用されますが、軽減税率(8%)の対象は限られています。
わかりやすく下の表にまとめました。
| 税率 | 対象商品・サービス | 特徴 |
|---|---|---|
| 本則税率10% | ・外食(飲食店での食事) ・酒類全般 ・嗜好品全般 ・日用品(食べ物以外) ・サービス全般 | ほとんどの取引に適用され、標準的な税率 |
| 軽減税率8% | ・飲食料品全般(酒類と外食を除く) ・定期購読の新聞(週2回以上発行) | 生活必需品に対して適用され、消費者負担を軽減 |





















