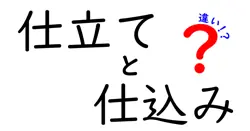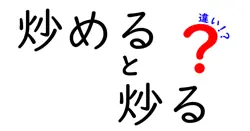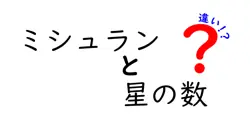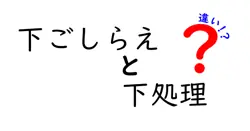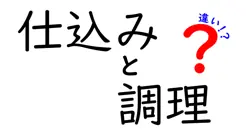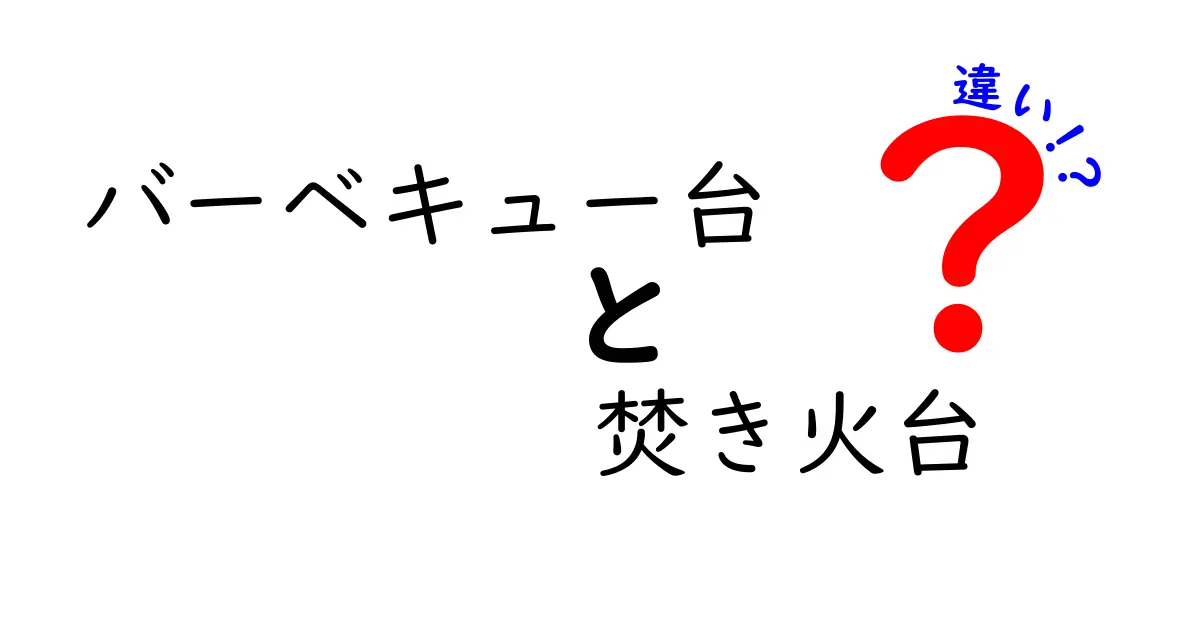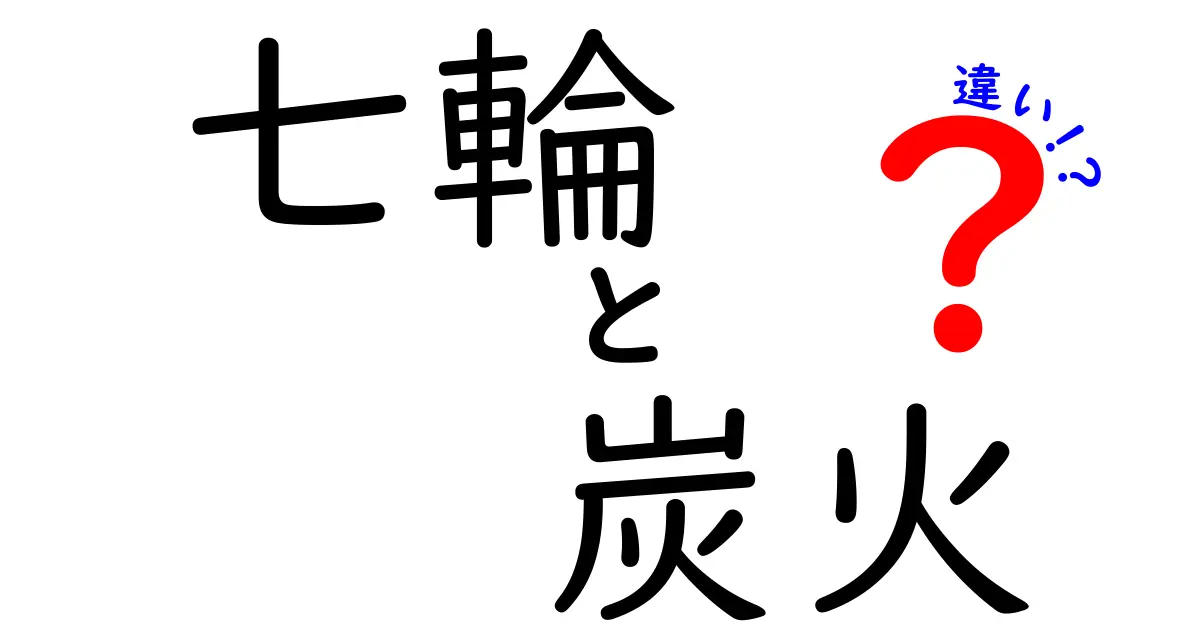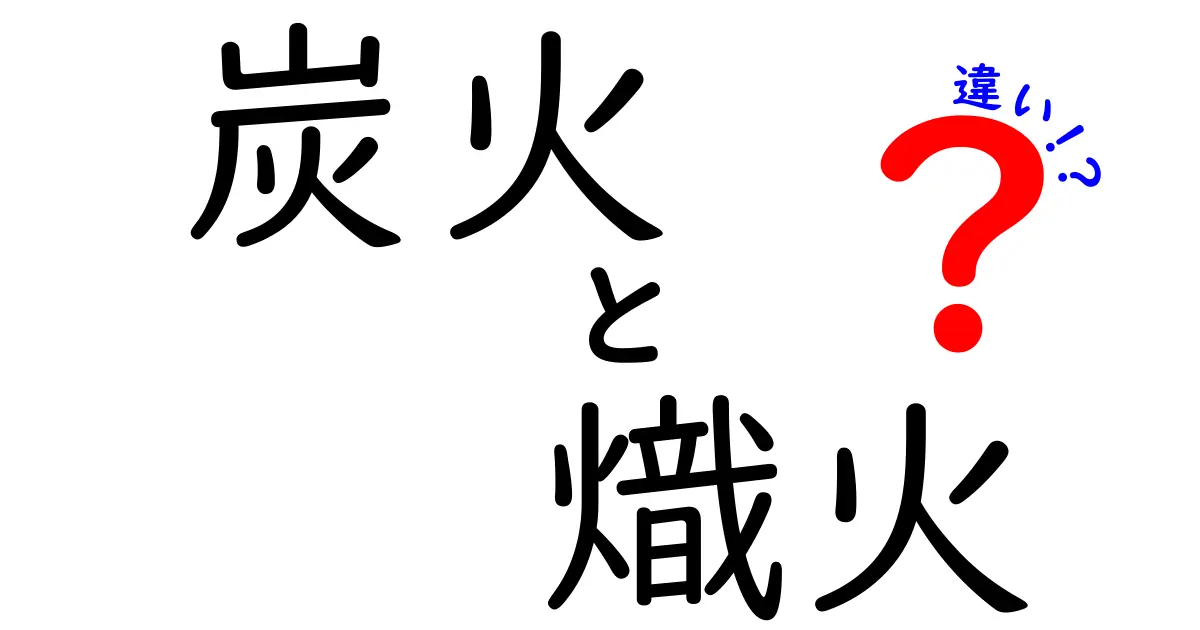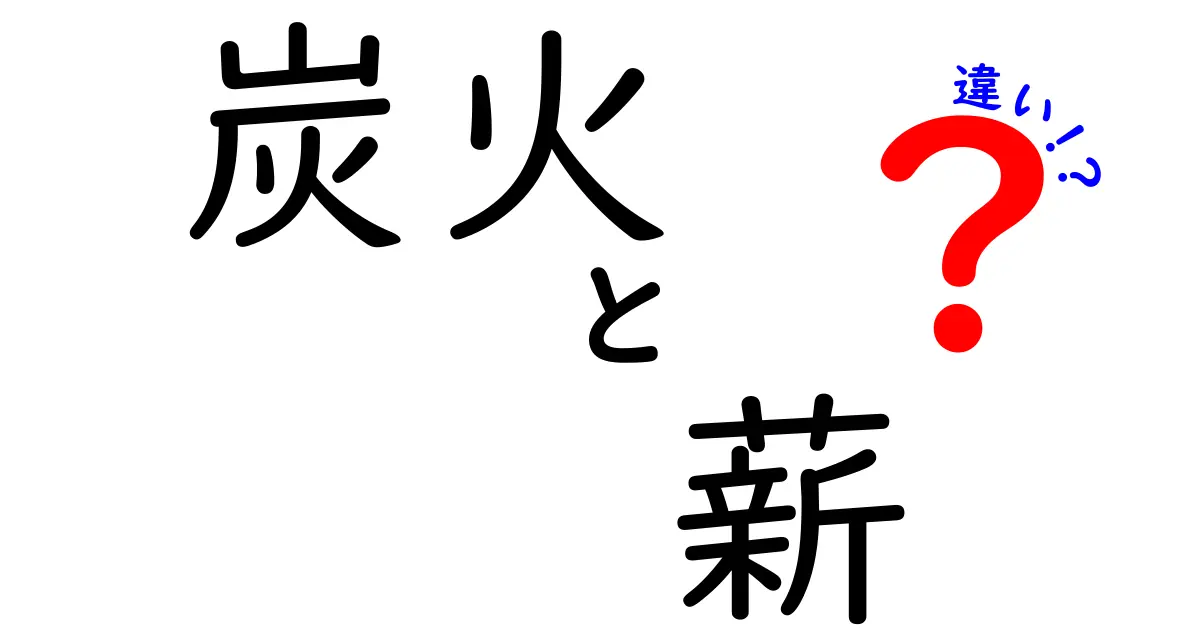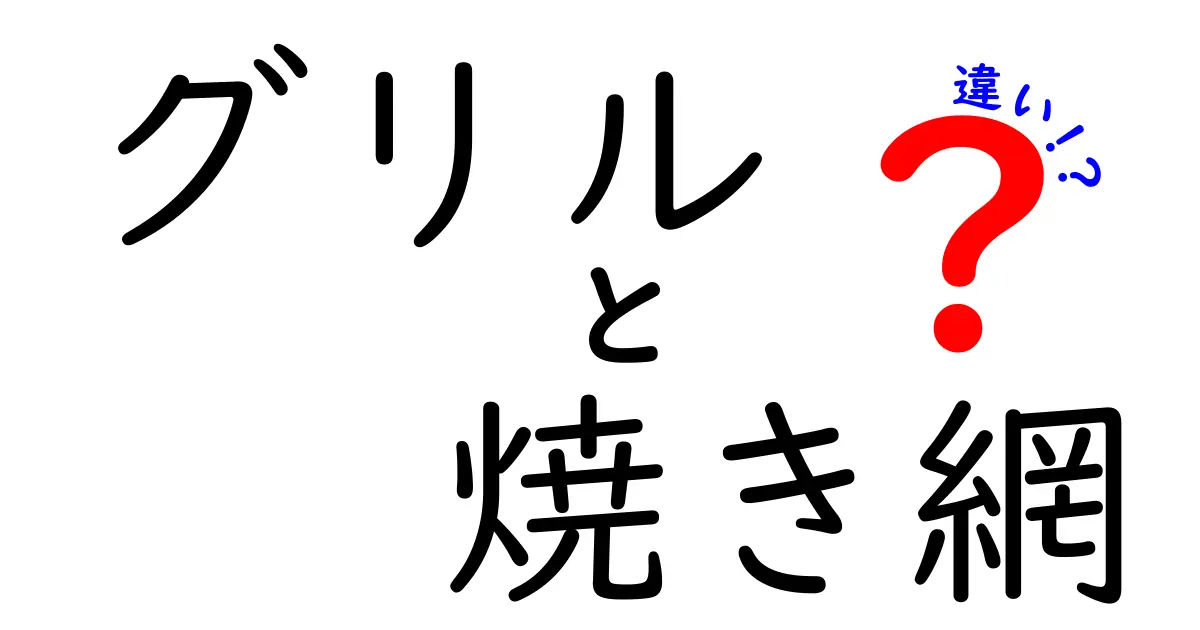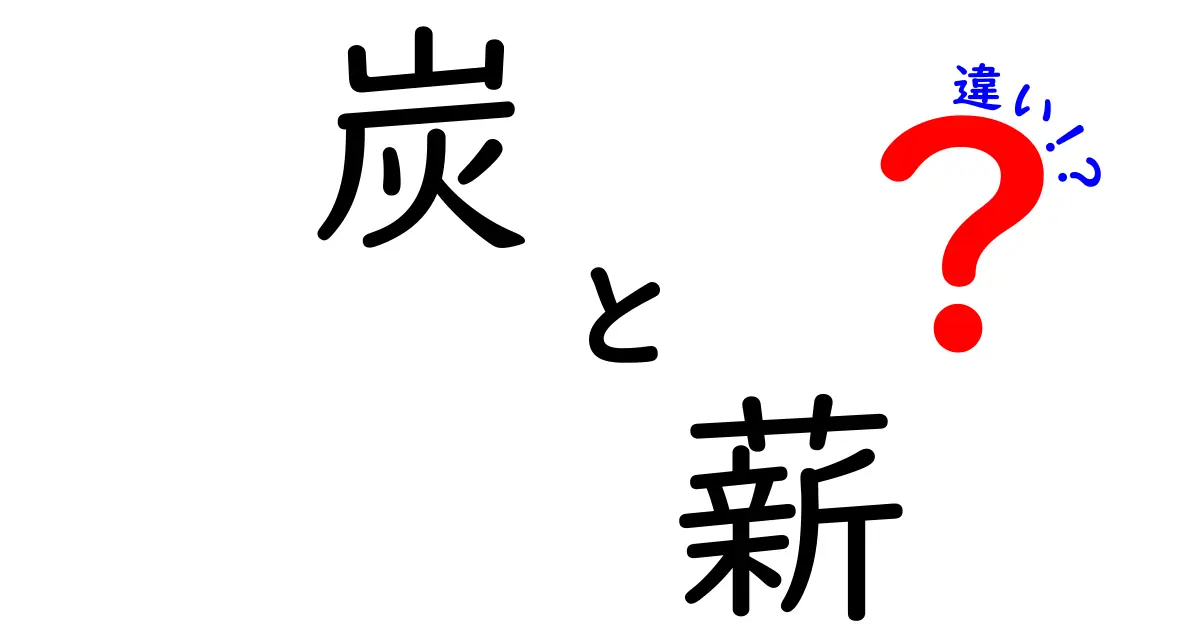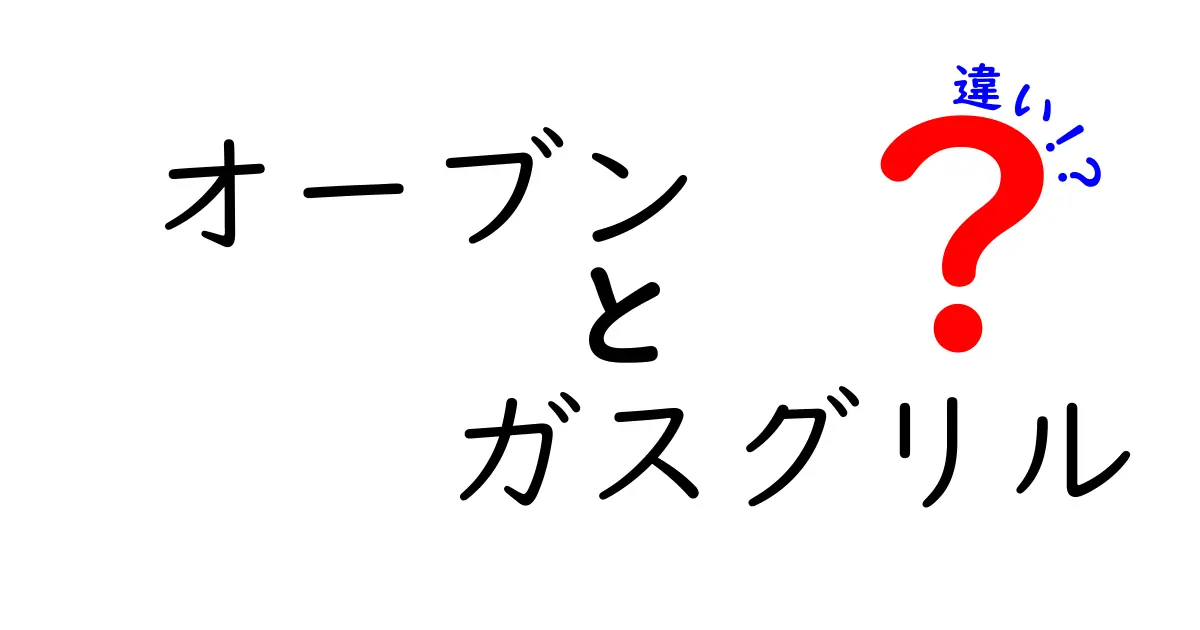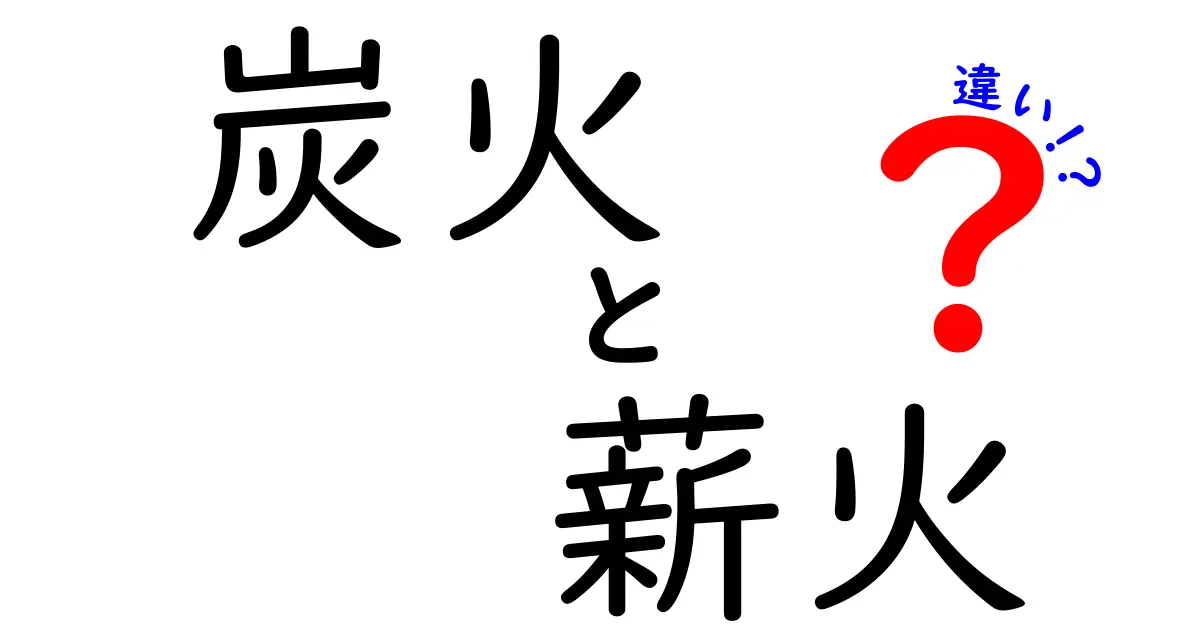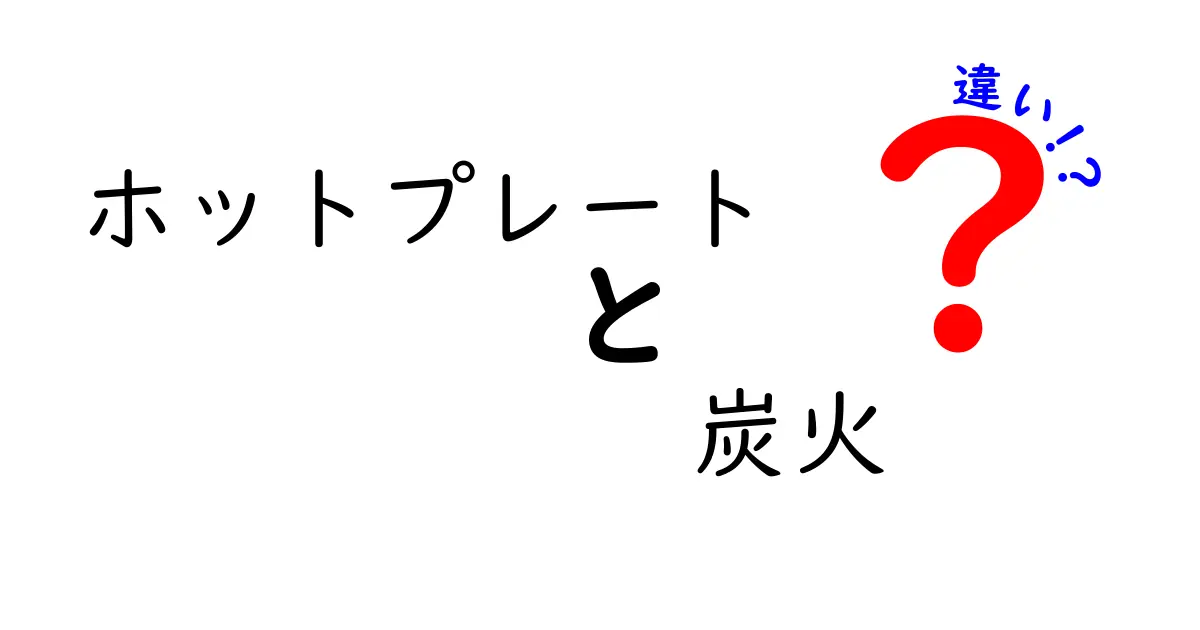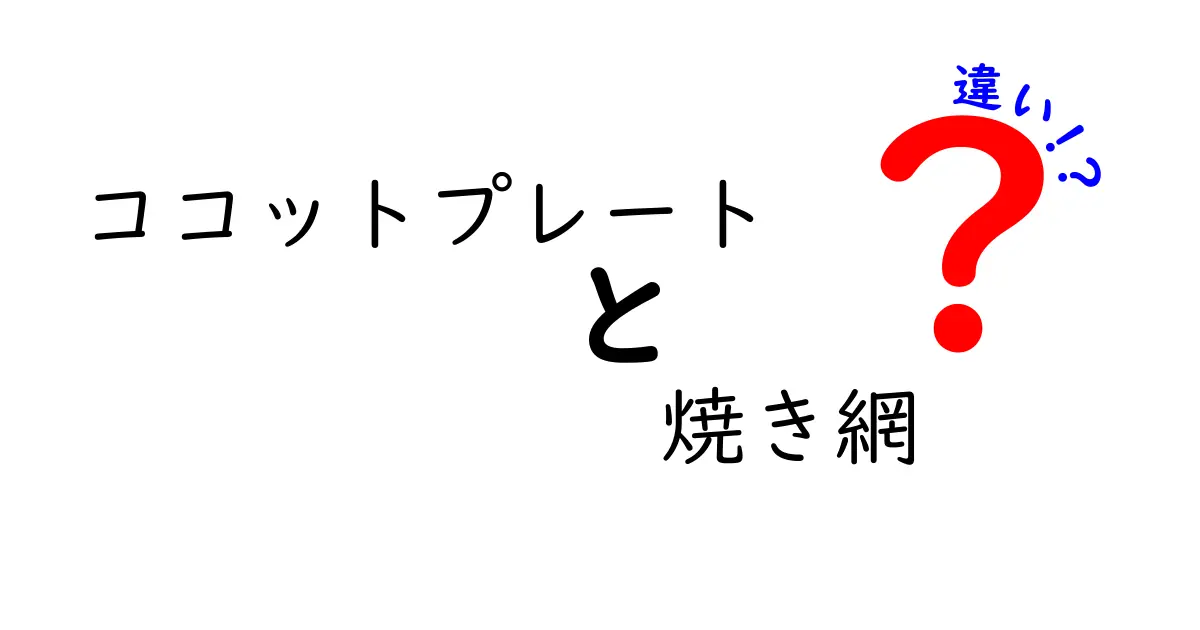

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ココットプレートと焼き網の違いを押さえる基本ポイント
日常の料理でよく登場する「ココットプレート」と「焼き網」。どちらを選ぶかで仕上がりや焼き時間が大きく変わります。まず理解してほしいのは、それぞれの“役割”と“調理の仕方”が異なることです。
ココットプレートは、表面だけを焼くことではなく、素材ごとに出る水分を閉じ込めたり、ソースを衣の中まで行き渡らせるように設計されています。
これに対して焼き網は、熱を直に食材の表面に伝えることで焼き色や香ばしさを生み出す道具です。
この違いを理解することが、失敗を減らし、食材の良さを引き出す第一歩になります。
次に、用途の観点から見ると、ココットプレートは「煮る・蒸す・蒸し焼き・汁を保つ」場面に向いています。
例えば、鍋代わりに使って煮込み料理の汁を遠ざけすぎず、煮物のうま味を閉じ込めたいときに活躍します。
また、オーブンでの加熱にも適しており、耐熱性のある素材ならオーブン料理やオーブン間の保温にも使えます。
一方の焼き網は、グリルや魚焼きグリル、焼きパンなど、表面を香ばしく焼くことが重要な場面で力を発揮します。
肉の表面をカリッと焼く、野菜の表面の水分を閉じ込める、魚の皮をパリっと焼くなどが得意です。
ポイントとしては、「目的が何か」を最初に決めることです。
汁を保ちたいのか、表面の焼き色をつけたいのか、それによって使い分けが変わります。
また、素材選びも重要です。
ココットプレートは陶磁器系や耐熱ガラスなどが中心で、重さがある分、安定性が高い反面取り扱いに注意が必要です。
焼き網は金属製が多く、熱伝導が早い反面焦げつきやすい素材もあります。
この特徴を踏まえて、使い方のコツを覚えることが大切です。
表現のコツとしては、食材の水分と脂のバランスを意識しましょう。
ココットプレートでは“蒸らす時間”を意識して、汁がこぼれない程度に食材を配置します。
焼き網では“高温での短時間焼き”を基本に、裏返すタイミングを見極めると香ばしさが安定します。
ここからは、具体的な違いを一目で比較できる表を用意します。下の表を参照してください。
表のとおり、二つの道具は似ているようで違う強みを持っています。
日常の料理で迷ったときには、まず「何を一番重視するか」を決めましょう。
香ばしさを優先したいなら焼き網、ジューシーさや汁の旨味を守りたいならココットプレートを選ぶのが基本です。
実践の場面別のおすすめ
家庭での普段使いなら、ココットプレートは「煮込み系とオーブン料理の両立」
、焼き網は「魚・肉・野菜の香ばしさ重視」の場面で力を発揮します。
もし2つが手元にあるなら、同じ食材でも仕上がりの違いを体感するのが一番の学習方法です。
実際の料理での使い分けのコツをもう少しくわしく見ていきましょう。例えば鶏の煮込みを作るとき、ココットプレートを使えば汁を煮詰めすぎず、野菜の旨味と鶏肉の脂を適度に保つことができます。
一方で同じ鶏肉を焼くときには焼き網を選ぶと、表面がパリッと香ばしく仕上がり、脂の多い部位でも余分な油が落ちやすくなります。
このように、工程ごとに器具を切り替えると、ひとつの食材でも違う表情を引き出せます。
友人と台所の棚を整理しているとき、ココットプレートの話題が出ました。私は『煮込みにも使えるけど、香ばさも出せる不思議な道具だね』と話し、友人は『それぞれの特性を生かす使い分けが大事だよ』と返しました。ココットプレートは蒸し焼きや汁の保持が強みで、素材の旨味を内部に閉じ込める設計です。一方の焼き網は表面を直接熱にさらして香ばしい焼き色を作るのが得意。実際に使ってみると、肉の脂が落ちにくいココットで煮込み、焼き網で仕上げの香ばしさを足すと、同じ食材でも別の魅力が出ることを実感します。次の休日、両方を使った実践実験をして、友達と結果をシェアする計画を立てました。