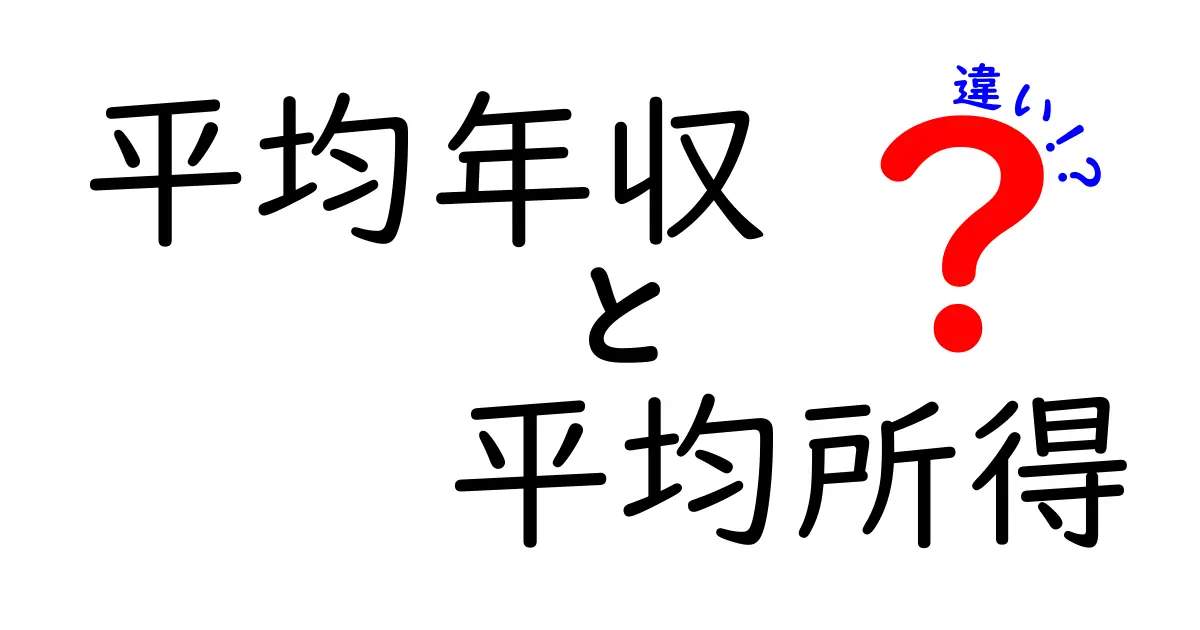

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
平均年収と平均所得の違いとは?
日本で働く人々の収入を考えるとき、「平均年収」や「平均所得」という言葉をよく耳にします。
しかし、この2つの言葉は似ているようで、実はまったく意味が違います。
まずはそれぞれの言葉の意味をはっきり理解することが大切です。
平均年収とは、会社や個人が1年間に得る総収入の平均額を指します。これは給与だけでなく、ボーナスや残業代、各種手当も含まれています。
一方、平均所得は、収入から税金や社会保険料などの支払いを差し引いた後の手取りの金額の平均を指します。つまり、実際に自由に使えるお金の平均額です。
このように、平均年収は総収入の平均、
そして平均所得は手取りの収入の平均と覚えると理解しやすいでしょう。
実際の数字を見てみると、例えばある業界の平均年収が500万円でも、税金や保険料が引かれた後の平均所得は約350万円から400万円程度となるケースが多いです。
この違いを知っていると、収入の実態を正しく把握できるため、生活設計や貯蓄の計画にも役立ちます。
なぜ平均年収と平均所得が違うのか?その理由を解説
平均年収と平均所得に差が生まれるのは、税金や社会保険料などの支払いがあるからです。
給与収入だけで考えると単純に高い金額に見えますが、実は社会保険料(健康保険・年金など)や所得税、住民税が引かれるため、手元に残るお金は減ります。
また、平均年収は総支給額であるため、会社から受け取る全ての報酬が含まれているのに対し、平均所得は手取り額ベースとなるため、実際に使えるお金の額を示しています。
さらに、所得控除や各種手当の有無でも差が生じ、年収が高くても税金が多く引かれる人や、逆に控除で税金が少ない人もいるため、平均所得は個々人の支払い状況によって異なります。
つまり、「稼いでいる総額」だけでなく、「実際に使えるお金」がどうなるかを考える上で平均所得の数字が重要になるのです。
平均年収と平均所得の違いを表で確認しよう
| 項目 | 平均年収 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 意味 | 1年間の総収入(給与・賞与など含む) | 税金・社会保険料を差し引いた後の手取り金額 |
| 金額のイメージ | 高い(例:500万円) | 低い(例:350万~400万円) |
| 計算方法 | 総支給額の平均 | 支給額から税金等を差し引いた平均 |
| 使いみち | 求人や昇給などの目安 | 家計や貯蓄計画の参考 |
この表を見ると、どちらの数字が何を表しているかがはっきり見えてきますね。
会社探しや給料交渉する際には「平均年収」も大切ですが、
生活費の計画や節約を考えるときは「平均所得」のほうがリアルな数字として役立つ場面が多いといえます。
まとめ:違いを知って賢くお金の計画を!
ここまでの説明をまとめると、
平均年収は、1年間に稼いだ総収入の平均で、
平均所得は、そのうち税金や保険料を差し引いた手取りの平均ということになります。
どちらも収入を表す大事な指標ですが、使う場面や目的に応じて使い分けることがとても重要です。
例えば家計を考えるときは、使えるお金の平均である平均所得を基準にすると現実的な見通しが立てやすいです。
一方で、キャリアアップや転職の際の給与交渉では、平均年収の数字が参考になることが多いでしょう。
ぜひこの違いを知って、日常生活や将来のプランを賢く立ててくださいね!
お金の話はちょっと難しいと感じるかもしれませんが、基本を押さえておくと誰にでもわかりやすくなります。
今回の記事が皆さんの役に立てばうれしいです。
「平均所得」と聞くと、単に収入のことだと思いがちですが、実は税金や社会保険料を引いた後のお金という意味です。
たとえば、平均年収が同じ500万円でも、住む場所や家族構成、控除のしくみが違うと、実際にもらえる所得はかなり変わるんです。
だから「収入が同じでも手元に残るお金は違う」ということを頭に入れておくと、貯金や生活設計のトラブルを避けやすくなりますよ。
身近なところでの違いを考えると、もっとお金のことに興味が湧いてくるかもしれませんね!
前の記事: « 「大都市圏」と「都市圏」の違いとは?中学生にもわかる簡単解説!





















