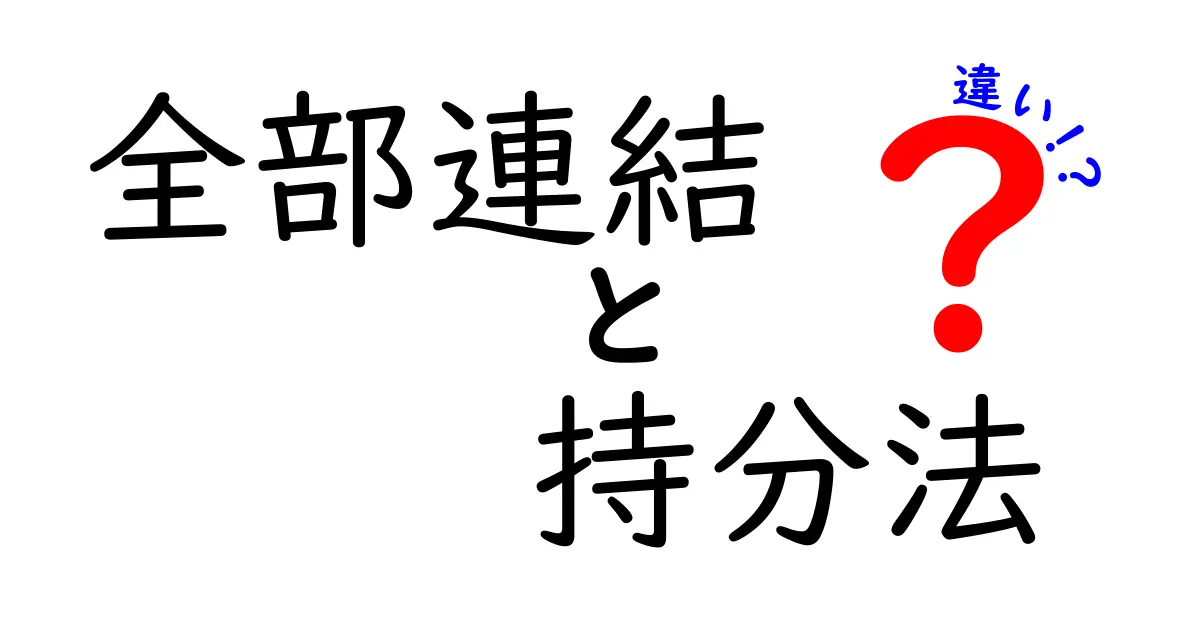
全部連結と持分法って何?基礎から丁寧に解説
会計の世界でよく出てくる言葉の中に、全部連結と持分法があります。どちらも企業がグループで活動するときの報告方法に関する話ですが、聞きなれないと難しく感じるかもしれません。今回は、全部連結と持分法の違いを中学生にもわかりやすく解説していきます。
まず、全部連結とは親会社が持っている子会社をすべて一つの企業のように扱って、売上や資産、負債などを合算して財務諸表にまとめる方法です。一方、持分法は親会社が関連会社に対して持っている出資比率に応じて、利益や資産の一部を財務諸表に反映するやり方です。
この2つは企業グループの規模や関係性によって使い分けられますが、何がどう違うのかを詳しく理解すると、会計の仕組みがもっと身近に感じられるでしょう。
全部連結の特徴とメリット
全部連結は親会社が子会社の株式を50%以上持っていて、実質的に支配している場合に使います。つまり、完全に自分たちのグループとして子会社の経営や資産を把握していると判断されるときです。
この方法の特徴は、すべての子会社の資産や負債、売上や費用を親会社のものと一緒に計算することです。そのため、企業グループ全体の実態がはっきりとわかりやすい財務諸表になります。
また、連結決算によって重複した利益や取引を消す処理が行われ、グループ全体の正確な利益が把握できます。例えば、親会社が子会社に販売した商品による利益は、グループ外への販売がない限り、グループ全体の利益に含めません。これによって数字が二重に計上されるのを防ぎます。
持分法の特徴とメリット
一方の持分法は、親会社が関連会社の株式を20%以上、50%未満持っている場合によく使われます。この場合、親会社は関連会社に大きな影響力を持っているものの、完全に支配しているわけではありません。
持分法は、親会社が関連会社の利益や損失に対して持ち分の割合に応じた金額を財務諸表に計上する方法です。例えば、親会社が30%の持ち分を持つ関連会社が100万円の利益を出したら、親会社の財務諸表には30万円の利益がプラスされます。
この方法では、関連会社の資産や負債は合算せず、利益だけを取り込むので、グループ全体の経営実態は少し異なりますが、影響力の大きい会社の利益を反映できる点がメリットです。
全部連結と持分法の違いを表で比較!
まとめ:違いを押さえて適切に会計処理しよう
全部連結と持分法は、企業グループの関係性や影響力の度合いに応じて使い分けられる会計の方法です。
全部連結は親会社が子会社を支配している場合に子会社の全ての数値を計上し、グループ全体の正確な財務状況を見せます。
一方、持分法は関連会社の利益を持分に応じて反映する方法で、支配していないが影響力のある会社の利益を部分的に反映します。
これらの違いを理解することで、財務諸表の見方がわかり、企業の実態をより正確に把握できるようになります。会計に興味がある人やビジネスを学び始めた人にとって、基本を押さえておくことはとても大切です。
ぜひ今回の解説を参考にして、全部連結と持分法の違いをしっかり理解してくださいね!
持分法って聞くと難しそうですが、実は「関連会社の利益の一部だけを取り込む」というシンプルな考え方なんです。実は、持分法は企業が自分の子会社を完全には支配していないけど、ある程度経営に関与している時に使われます。ここで面白いのは、関連会社が赤字でも親会社の損益に影響するし、利益が増えたらその分も反映される点。子会社のように全部の資産や負債を合算しないため、親会社の財務状況を正確に把握できて、会計の調整をきちんとしているんですね!
前の記事: « 自己株式と自社株式の違いとは?初心者でもわかるポイント解説!



















