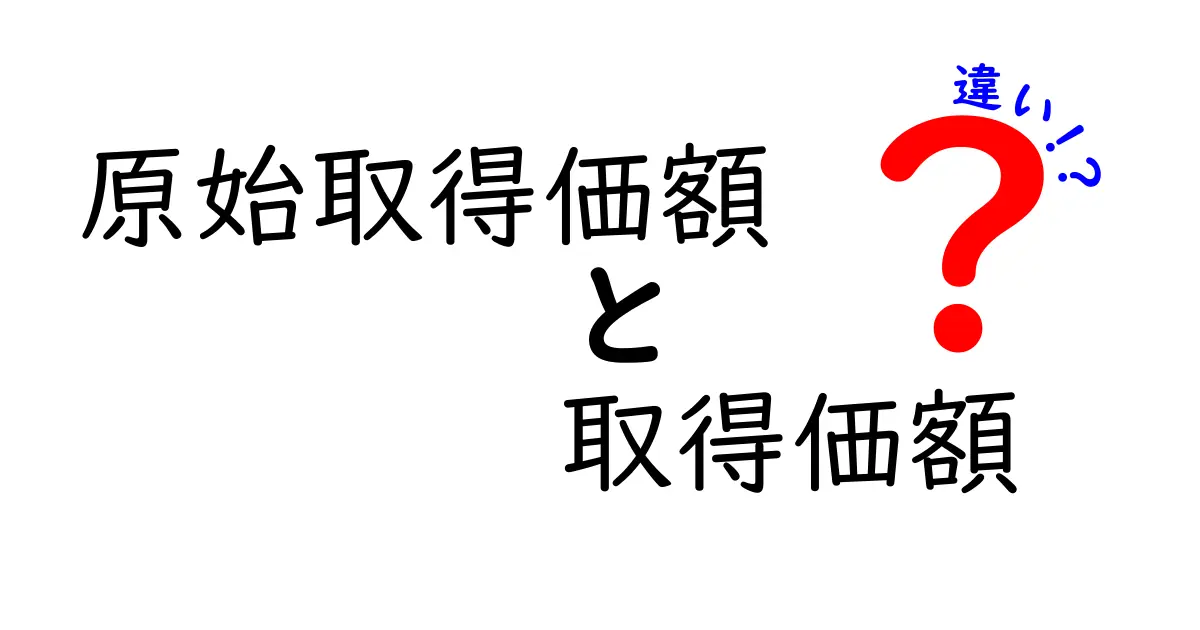
原始取得価額と取得価額は何が違うの?基礎から理解しよう
原始取得価額と取得価額は、どちらも会計や税務の場面で使われる言葉ですが、実は少し意味が違います。
まず、原始取得価額とは、不動産や車、機械などの「資産を最初に取得した時の購入価格」のことを言います。つまり、新品を買った時の価格がこれにあたります。
一方で、取得価額は、原始取得価額をもとに、購入後にかかった費用や改良費などを加えたり、逆に減価償却などで価値が減った分を差し引いた金額のことです。
要するに、原始取得価額は「最初の購入価格」、取得価額は「現在の資産の価値」を示す言葉として区別できます。
この違いは、資産の管理や税務申告で非常に重要なポイントになるため、しっかり理解しましょう。
なぜ原始取得価額と取得価額を区別するのか?その重要性と目的
原始取得価額と取得価額を区別する理由は、資産の価格が時間とともに変わるためです。
例えば、会社が機械を買ったときの原始取得価額は100万円だったとします。しかし、使っていくうちに機械の価値は少しずつ減少しますし、修理や改良を加えれば価値が増すこともあります。
このため、取得価額は原始取得価額から、修理費用や改良費用を足したり、減価償却といって経年劣化による価値の減少分を引いたりして計算されます。
税法上や財務諸表で正確に資産の価値を表すためには、この区別が必要です。
正確な評価がなければ、税金の計算や経営判断が誤ってしまう可能性があるため、会計処理において基本中の基本となっています。
原始取得価額と取得価額の違いをわかりやすく表で比較!
まとめ:原始取得価額と取得価額の違いを押さえて正しい会計知識を身につけよう
この記事では「原始取得価額」と「取得価額」の違いについて説明しました。
ポイントは次の通りです。
- 原始取得価額は資産を最初に買ったときの価格
- 取得価額は原始取得価額を元に修理費や改良費を足し、減価償却を差し引いた最新の価値
- この違いを理解することで、資産の適切な評価や税務申告ができる
どちらも難しい言葉ですが、一度理解するとビジネスや会計の勉強で非常に役立ちます。
ぜひ日常の経済活動の中で意識してみてください。
会計でよく使われる「原始取得価額」ですが、実は意外と知られていないのが『なぜ変わらないのに重要なのか』という点です。
原始取得価額は最初に資産を買ったときの価格で、これが会計や税務のスタートラインになります。そして、この価格を基に、修理費や減価償却費を加減して「取得価額」が決まるんです。
つまり、原始取得価額は資産の“元の姿”をはっきり示す役割があるんですね。これはまるで家の設計図のようなもの。設計図がなければ修理や改築も正しくできないですよね? 会計の世界でも同じことが言えます。



















