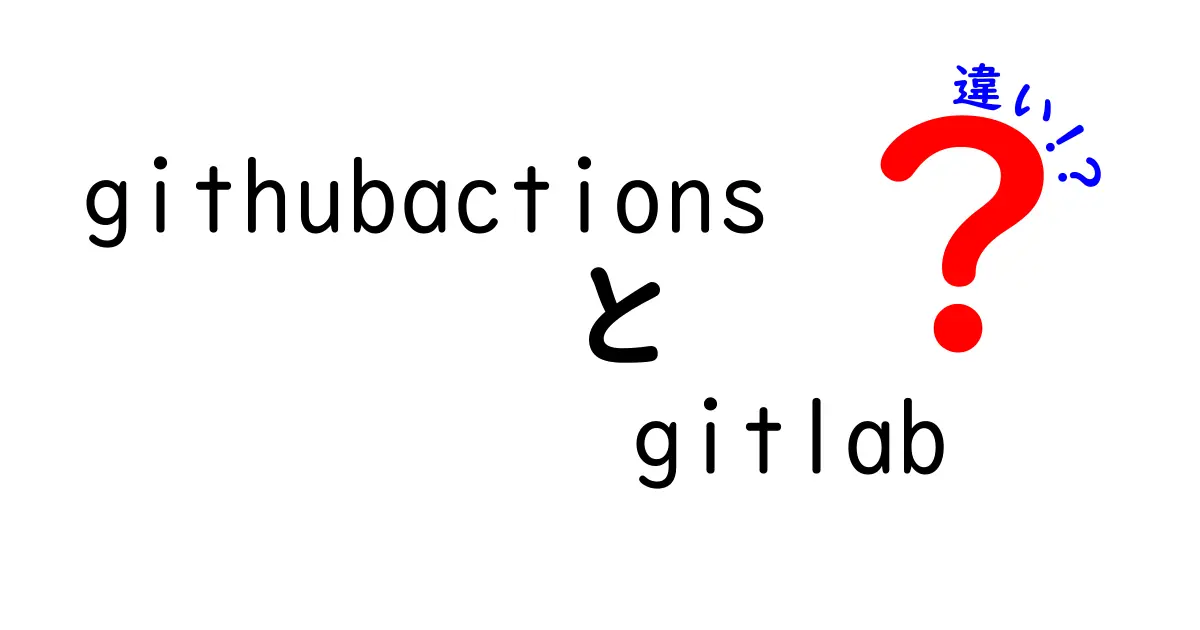

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
GitHub ActionsとGitLabの違いを徹底解説して、初心者にも分かりやすい比較ガイドを作る理由
この章では、まずそもそも“CI/CDとは何か”という基本の話から始めます。CI/CDは開発の流れを自動化して、コードをテストし、ビルドし、デプロイまでを効率化する仕組みです。
ところが、実際には提供しているツールやエコシステムが異なると、日々の運用や学習コスト、拡張性に大きな差が生まれます。
特に、GitHub ActionsとGitLab CIは、それぞれが人気の高い選択肢ですが、使う場面や組み合わせるツールが変わると、成果物の品質や開発速度にも影響します。
このガイドでは、初心者の視点で基本的な違い、実際の機能の差、料金の考え方、ケース別の選び方を、写真のように“見える化”して紹介します。
1) 仕組みとエコシステムの違い:何がセットで動くのか
まず大前提として、GitHub ActionsはGitHubのリポジトリと深く結びついています。
ワークフローはYAMLで記述され、リポジトリのイベント(push、pull request、スケジュールなど)に応じて自動的に走ります。
アクションと呼ばれる再利用可能な部品を組み合わせて、ビルド・テスト・デプロイを一連の流れとして組み立てます。
対してGitLab CIはGitLabのエコシステム全体と統合され、パイプラインとジョブ、ステージという概念で運用します。
GitLabはリポジトリだけでなく、課題管理、コードレビュー、モニタリングまでを一つのプラットフォームで提供する点が大きな特徴です。
この違いは「どこに強みを置くか」という点に直結します。
もしリポジトリとCIを切り離して別のサービスを使いたい場合は、連携が必要になる場面も出てきます。
また、セルフホスティングの選択肢も両者で異なり、組織の要件次第で自前のサーバーで走らせることができます。
この点を理解しておくと、将来の拡張性を見据えた選択がしやすくなります。
2) 機能の差と使い勝手:どの作業が楽になるのか
機能面の差は大きく、実務での“使い勝手”にも直結します。
GitHub Actionsは、直感的なUIと豊富な公式アクションのエコシステムが魅力です。
新しいアクションを見つけて組み込むのが簡単で、学習コストが比較的低い点が初心者には大きいメリットです。
また、ワークフローのトリガーが柔軟で、イベントベースの自動化が得意です。
一方、GitLab CIはCI/CDの基盤が統一されている点が強みです。
パイプラインの可搬性や、ジョブ間の依存関係・条件分岐、
ビルドキャッシュ、アーティファクトの管理など、複雑なワークフローを一元的に扱いやすい設計になっています。
UIの好みによっても分かれますが、両者とも規模が大きくなるにつれて、複数ブランチ・複数環境の管理が難しくなる点には注意が必要です。
また、セキュリティ周りの機能は両者とも強化されてきており、秘密情報の取り扱い、承認フロー、監査ログなどの機能を活用することで、安心して自動化を進められます。
自動テストの実行速度やキャッシュの挙動、失敗時のリトライ設定、アーティファクトの保存期間など、細かな差異を理解しておくと、再現性の高い開発環境を作りやすくなります。
実際の使い勝手は、個人の好みとチームのワークフロー次第で変わります。体験談を聞くときには、同じ規模のプロジェクトでどの程度の頻度で失敗・成功が出るのか、どの機能を最初に導入したのか、を具体的に聞くと良いでしょう。
3) 料金・運用の現実:コストと運用の現実を見極める
料金の観点では、どちらも「無料プラン」が存在しますが、適用範囲や制限が異なります。
GitHub Actionsの無料枠は、ユーザーごとに割り当てられた「分」単位の実行時間と、月間の並行実行数が設定されています。
個人開発や小規模チームには十分な場合が多いですが、企業規模になると長時間のビルドや大量の並行ジョブが必要になる場面も出てきます。
また、追加のミニッツは有料になりますが、料金プランを組み合わせて使い分ける運用が一般的です。
GitLab CIは、CE(Community Edition)/ EE(Enterprise Edition)の違いがあり、セルフホスティングを選べば自前のインフラで走らせられるため、コストの見通しが立てやすいという利点があります。
特に大規模な組織やセキュリティ要件が厳しい場合、ランニングコストと人件費を含めて総合的に判断することが重要です。
クラウド版のランニングコストは、実行時間・並行ジョブ・ストレージ容量などの要素で決まります。
実務では、人員の能力・運用体制・サポート体制も大きな要因です。
学習コストを抑えつつ運用を始めたい場合は、まずは無料枠での試用から始めて、どの程度の時間を投資すれば成果が出るかを把握しましょう。
4) ケース別の選び方:こんなときはどちらを選ぶ?
ケース1:あなたの開発がGitHubにすでに強く結びついている場合、GitHub Actionsは自然な選択肢です。リポジトリとCIが同じ場所にあるため、設定の一貫性が生まれ、学習コストも低くなります。
ケース2:コード管理だけでなく課題管理・CI/CD・リリース管理を一括で運用したい場合はGitLabが有利です。機能が一元化されており、組織全体のワークフローを統合しやすいです。
ケース3:セルフホスティングの要件が強い企業や、オンプレミスのセキュリティポリシーが厳しい場合は、GitLabのCE/EEを活用して自前の環境で回すのが現実的です。
ケース4:小規模なオープンソースプロジェクトで、外部のアクションを活用して迅速に自動化を始めたい場合、GitHub Actionsのエコシステムが特に力を発揮します。
このように、目的・規模・運用体制を整理してから選ぶと、将来の拡張にも耐えられる設計になります。最後に、実際の導入前には小さなパイロットを行い、失敗と学習を記録しておくと、組織内の合意形成がスムーズになります。
まとめ表:GitHub Actions vs GitLab CIの要点
| 観点 | GitHub Actions | GitLab CI |
|---|---|---|
| エコシステムの強み | GitHubリポジトリとの統合が最強。アクションの再利用性が高い。 | コード管理・課題管理・CI/CDを一元管理しやすい。 |
| 使い勝手 | 直感的なUIと豊富な公式アクションが魅力。 | 複雑なパイプラインも管理しやすいが学習コストはやや高め。 |
| 料金・運用 | 無料枠あり。規模が大きくなると計画が必要。 | セルフホスティングの選択肢が強み。大規模運用に向く。 |
| 適したケース | GitHub中心の小〜中規模プロジェクト、速やかな自動化を求める場合。 | 組織全体を統合して運用する場合、セキュリティ要件が厳しい企業。 |
良い選択は、実際の開発現場での挙動を見て決めることです。まずは小さなパイロットを実施し、作業の自動化がどれだけ楽になるか、失敗時の対応がどう変わるかを体感してください。
友だちとカフェでGitHub Actionsについて話していたら、彼はこう言いました。『GitHub Actionsは、まるで日常の作業を「流れ」として自動化してくれる機能が詰まっているね。パパッと設定しておけば、テストもビルドもデプロイも、あとは結果を待つだけ。GitLabは別の話題だけど、もしチーム全体でコード以外も一元管理したいなら、GitLabの方が合う場面が多いかもしれない』と。私はこう返しました。『それぞれの強みを知って、状況に応じて使い分けるのが最適解だよ。小さなチームならGitHub Actionsの手軽さが強みだし、組織全体で厳格な運用が求められる場合はGitLabの統合性が役立つ』と。実はこの話、単なるツールの話ではなく、開発現場での“働くリズム”をどう整えるかということに近い。結局は、何を自動化したいのか、誰がどこまで管理するのか、どの程度のセキュリティが必要なのか、そんな質問に答えられる選択肢を持つことが最も大切だと気づいた。
次の記事: エメゴジとジラの違いを徹底解説!ファンが語る混乱と正解 »





















