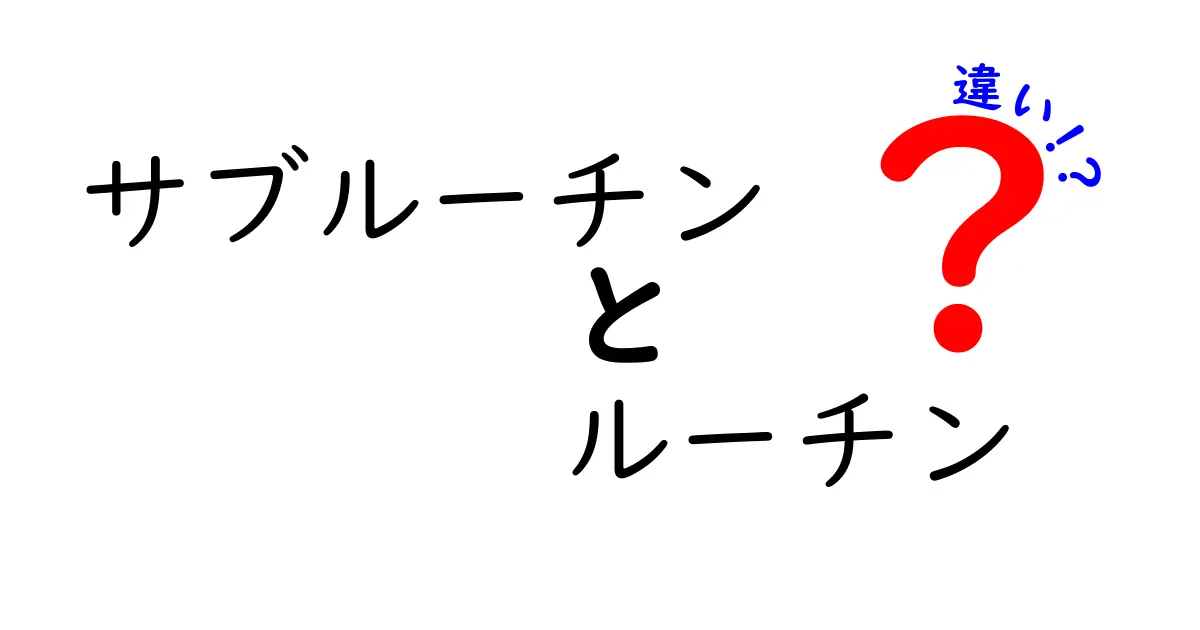

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サブルーチンとルーチンの基本をとらえる
このsectionではサブルーチンとルーチンの基本的な違いを、できるだけ分かりやすく中学生にも伝わる言葉で解説します。サブルーチンはプログラミングの世界における独立した処理の単位であり、名前のとおり「呼び出して再利用できる小さな機能」です。処理をひとつのまとまりとして切り分け、必要なときに何度でも実行できるのが特徴です。呼び出す側は処理の流れの途中でその機能を使い終わると元の場所に戻ります。これが再利用性と可読性の向上につながり、コード全体を見やすくします。
一方でルーチンは日常の言葉としても使われる語で、作業の連続的な流れや決まった手順を指します。プログラミングの文脈では、サブルーチンと同様に機能のまとまりを意味することが多いのですが、場面に応じて「日課的な動作」や「手順の集まり」という意味合いが強くなることがあります。
ここでの重要なポイントは両者の関係性です。サブルーチンはコードの中の機能単位、ルーチンは作業や手順のまとまりというイメージで覚えると混乱を避けやすくなります。次の段落では具体的な特徴を並べて比べます。
なお実務の現場では、言葉の使い方が組織や言語仕様で微妙に異なることがあります。そのためドキュメントを読むときは、>その文脈での意味を確認する癖をつけるとよいでしょう。
以下の表はサブルーチンとルーチンの代表的な違いを短くまとめたもので、頭の中の整理にも役立ちます。
この表を見れば、サブルーチンはコード設計の観点での部品、ルーチンは作業の流れ全体を指すという基本がつかめます。
実際のプログラミングではサブルーチンが関数やメソッドとして具体的に実装され、ルーチンは設計上の概念や作業プロセスとして語られることが多いです。
次のセクションではサブルーチンの特徴と使いどころを詳しく見ていきます。
ねえねえ、サブルーチンとルーチンの違いについて友達と話していたんだけどさ、結局のところ「コードの部品」と「作業の流れ」っていう分け方が、一番分かりやすいんだと思う。サブルーチンは名前の通り呼び出して使う機能のまとまり、だから何度でも再利用できて、他の部分のコードをずっとすっきりさせてくれる。ルーチンは日課みたいなもので、作業の連続性を表す言葉として捉えると理解が早い。こうやって両方の意味を結びつけておくと、プログラムの設計図が頭の中に自然と描けるようになるんだよね。
前の記事: « FDMとSLAの違いを徹底解説!コスパと精度の両立を目指す選び方





















