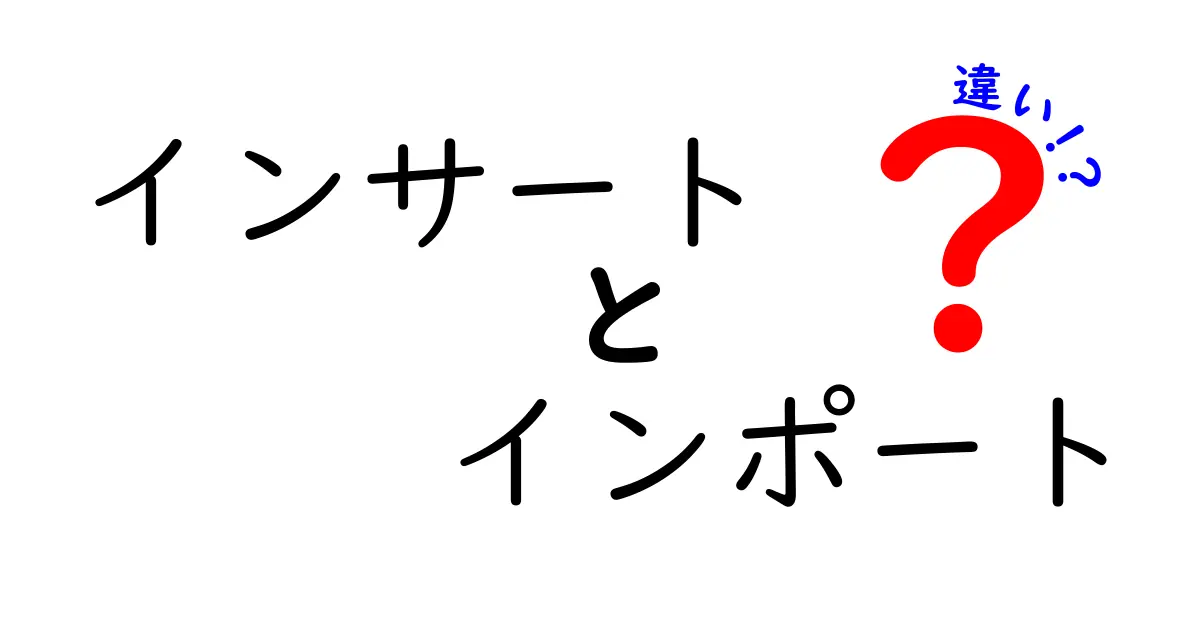

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インサートとインポートの違いを徹底解説!中学生にも分かる3つのポイント
みなさんは日常の言葉としてのインサートとインポートの意味を混同することがあるかもしれません。けれど、ITの世界ではこの2つは「どこに」「何をするか」が違います。
インサートは 挿入という動作で、すでにある場所に新しいデータを加えることを指します。データベースの表に新しい行を追加する時や、文書の末尾に新しい段落を入れる時などが典型です。対して インポートは
外部の情報を自分の環境へ取り込む動作を指します。ファイルを読み込んだり、別のプログラムの機能を自分のプログラムで使えるように取り込んだりする時に使います。学習の過程では、挿入と取り込みの操作が混ざってしまうことがあるので、文脈を確認することが大切です。実際のコードや手順を見ながら覚えると、どちらを使えばよいかが自然と分かるようになります。例えば、SQLでは新しいデータを表に入れる時はINSERT文を使い、Pythonでは他人が作った機能を使いたい時にimportで取り込みます。このような例を覚えると、言葉の意味のズレに気づきやすくなります。
記事の後半では、日常の場面での映像的な例と、プログラミングの現場での実際の使い方を対比していきます。
インサートとインポートの違いを生活の中の例えで理解しよう
日常の例えとして、ノートに新しいページを追加する操作はインサートに近いです。もう一つの例は、海外の友だちからもらったレポートを自分のパソコンに取り込んで使えるようにする操作はインポートです。これらの感覚は、テキストを編集する場面やソフトウェア開発の現場で実感としてつかむことができます。学生や初心者にとって大切なのは、何が「場所を変えるのか」、何を「取り込むのか」という2つの視点です。コードの例では、テーブルに新しい行を挿入するには INSERT、外部ファイルをプログラムに読み込むには import を使います。これを頭の中で整理するだけで、意味の混同がぐっと減ります。 また、実務ではインポートを忘れてしまうと、必要な機能が動かず困ることがあります。その時、まずどの外部リソースを使っているのかを確認する癖をつけると良いでしょう。
友達とプログラミングの話をしていて、インサートとインポートの違いについて雑談しました。最初は同じ言葉に聞こえますが、実は使う場面が全く違います。私たちは日常的に、ノートに新しいページを追加するのをインサート、外部のレポートを自分のノートへ持ち込むのをインポートと説明すると会話がスムーズになります。挿入は“その場所に新しい要素を置く行為”で、取り込みは“外部のものを自分の場へ持ってくる行為”です。プログラムの世界ではこの二つを明確に使い分けることで、コードが見違えるように読みやすくなります。





















