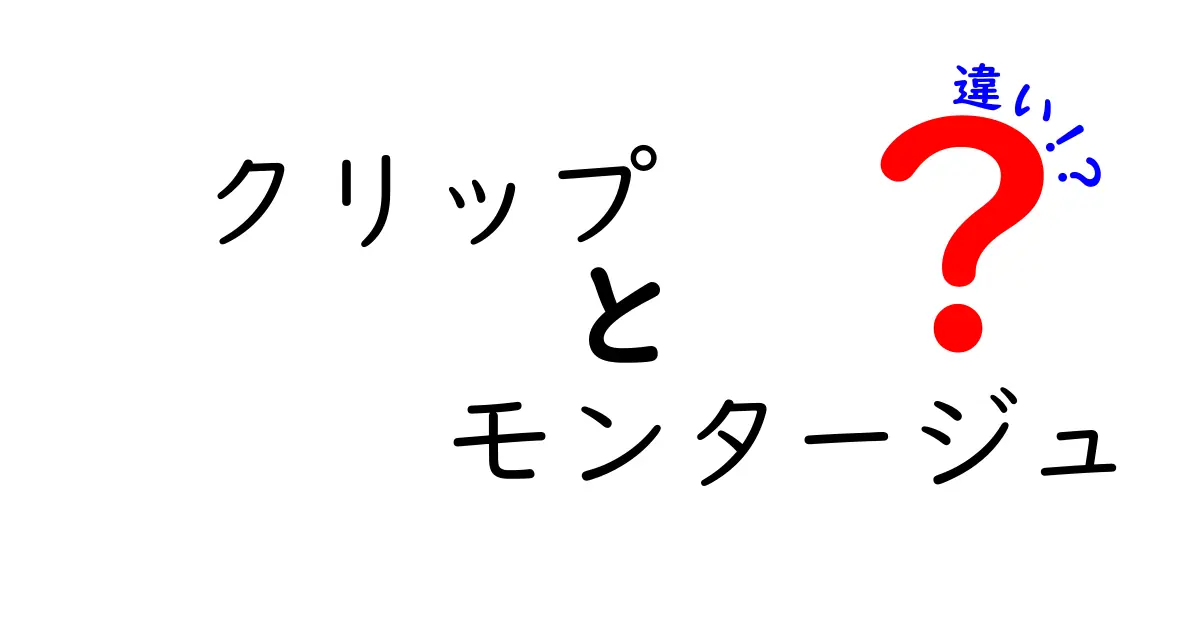

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クリップとモンタージュの本質的な違いをわかりやすく解説
クリップとモンタージュは動画編集の現場で頻繁に使われますが、初めて学ぶ人には同じに見えることも多いです。ここでは二つの概念の根本を分かりやすく整理します。
まず重要なのはクリップは一つの映像の断片を指す小さな単位であり、個々の素材として切り出されます。長さや内容は変えられますが、意味はその時点の映像自体に依存します。これに対してモンタージュは複数のクリップをつなぎ合わせて新しい意味や感情の流れを生み出す編集の技法です。モンタージュはテンポとリズムを使い、音楽やセリフの周波数と合わせて視聴者の心に訴えるための設計が求められます。
この二つの違いを理解することは編集の設計図を描く第一歩です。クリップは素材の集合体であり、モンタージュはその素材を使って意味を作る作業であるという基本を押さえておきましょう。ここからはそれぞれの役割をもう少し詳しく見ていきます。
クリップとモンタージュの関係性を知ると作業の順序も明確になります。企画時点での目的がはっきりすれば、どのクリップをどの順番で並べるべきかが見えやすくなり、編集の手戻りを減らせます。さらに、視聴者の反応を想定して長さや切り方を決めることが大切です。
この章の要点は二つです。素材であるクリップを尊重しつつ、それらを組み合わせて新しい意味を生み出すのがモンタージュだという点と、初心者でも実践しやすい基本の考え方を身につけることです。
クリップとは何か(1つの映像の断片)
クリップは動画制作の現場で最小単位として扱われる映像の一部分です。出来上がりの作品の中で一つの撮影シーンや一瞬の映像を指すことが多く、始まりと終わりのタイミングを切り出して順序を変えたり、長さを短くしたりします。
編集ソフトではこのクリップをタイムラインに並べ、全体の流れを作っていくのが基本です。
クリップは単体で意味を持つこともありますが、多くの場合は文脈を補う素材として使われ、別のクリップと組み合わせて意味が生まれます。
覚えておきたい点はクリップは素材の一部であり、編集の目的が決まっていない段階では多すぎても意味が薄くなること、不要なクリップは削る勇気が必要だということです。
モンタージュとは何か(複数のクリップをつなぎ意味を作る編集手法)
モンタージュは複数のクリップを順番につなぎ合わせて新しい意味や感情の流れを作る編集の技法です。
短い時間の中で複数の出来事を連関させ、視聴者にこの一連の出来事はこういう意味だと理解させます。
映画の歴史ではメッセージを重ねるためのリズム作りとして用いられてきましたが、現代の動画でも音楽やセリフのテンポに合わせて素材を切り替えることで視聴者の集中を保ちやすくします。
モンタージュのやり方にはいくつかの方向性があり、メトリックモンタージュ(映像時間でリズムを作る)、音響モンタージュ(音と映像の連携を重視する)、アイデンティティモンタージュ(象徴的な映像を並べる)などがあります。
これらを使い分けるコツは、伝えたい感情や情報の重心をどこに置くかを最初に決めることです。
実務での使い方とコツ
実務の現場ではクリップとモンタージュを組み合わせて作品の骨格を作ります。まずは企画段階でストーリーボードを描き、必要なクリップの数を把握します。次に素材を整理し、走るテンポや話の展開を想定してタイムラインに並べます。
切り替えのタイミングは視聴者の視線の移動を考慮して決め、不要な間を削ることが重要です。
音楽のリズムを活かすならメトリックモンタージュの考え方を取り入れ、合う場所でクリップを短く切る練習をします。
学習のコツは、まずは短い動画の中で一つの意味を作る練習を繰り返すことです。
大切なのは視覚と聴覚の連携を意識すること、そして編集の意図を常に言語化することです。
モンタージュという言葉を日常の会話に置き換えると、たいへん身近なものになります。僕らが映画や動画で“この場面はこういう意味だろう”と感じるのは、瞬間の映像だけでなく音楽のテンポや切り替えの速さが組み合わさって生まれるからです。友達と一緒に動画を作るときは、同じ場所の違う時間を並べると視点が変わって新しい気づきが生まれます。モンタージュは単なる映像の連結ではなく、観る人の想像力を手助けする編集の道具です。だからこそ、どの場面をどの順で出すのかを話し合い、リズムと意味を同時に設計する練習を繰り返す価値があります。編集は技術と感覚を同時に磨く遊びです。僕はそう思います。





















