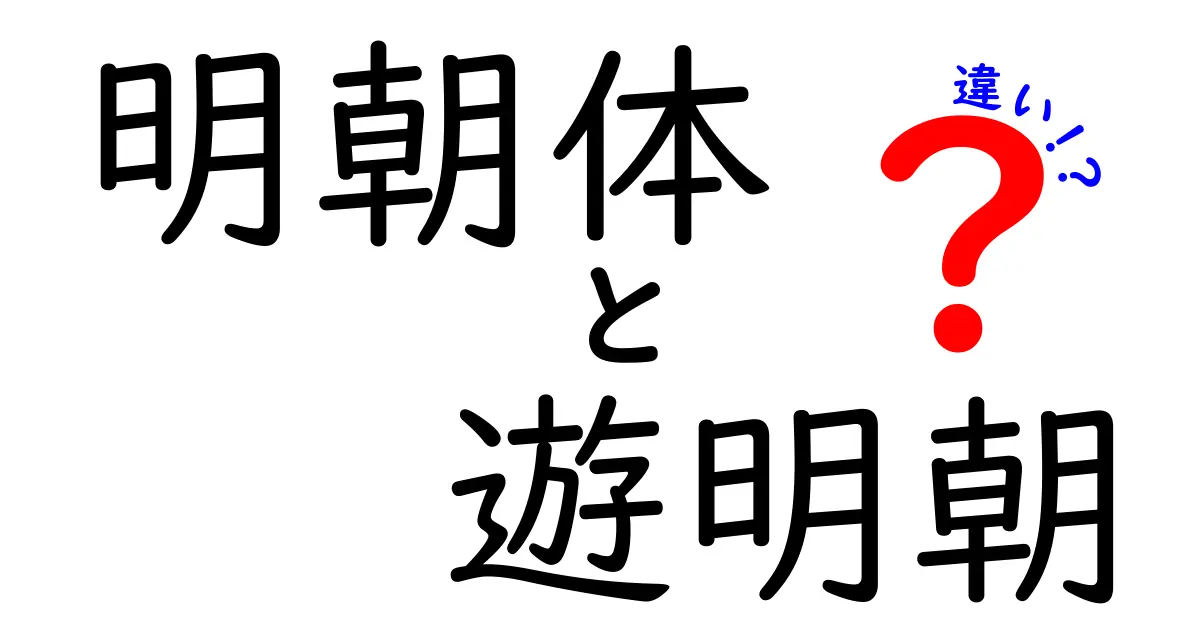

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
第1章:明朝体と遊明朝の基本的な違い
ここでは明朝体と遊明朝の見た目と使い方の違いを、中学生にも分かる言葉で説明します。まず大切なポイントは「線の太さのコントラスト」と「終点の形」「画面と紙の適性」です。
明朝体は、紙の印刷物を想定して作られた伝統的な字体です。
縦方向の線が太く、横方向の線が細くなるコントラストがはっきりしており、文章の長さを読んだときに「読みやすさ」と「落ち着き」を与えます。新聞や本、正式な文章の雰囲気に向いています。終端の線は角ばってシャープに見えることが多く、全体として「きちんとした感じ」が出ます。
一方、遊明朝は、明朝体の雰囲気を保ちつつ、現代のデジタル環境で読みやすさを高めた派生フォントです。線の太さの変化が少し控えめで、字形が丸みを帯びることが多くなっています。結果として、画面上でも印刷物でも、柔らかく親しみやすい印象になります。看板やウェブ上のタイトル、子ども向けの資料など、やわらかい雰囲気を出したい場面で選ばれることが多いです。
この二つは、同じ「明朝体」グループに属しますが、印象と用途が少し違います。次の表は、覚えておくと便利な基本情報を短く並べたものです。
比較表:明朝体 vs 遊明朝
第2章:実務での使い分けと選び方
実務では、フォントを選ぶときに「場面」「読みやすさ」「雰囲気」を同時に考えることが大切です。まず、正式で長い文章を読む機会が多い資料や印刷物には明朝体を選ぶとよいでしょう。読み慣れた字形と強いコントラストが、長い文章をストレスなく読ませてくれます。
しかし、スマートフォンやパソコンの画面で文章を読む機会が増えた現代では、遊明朝のように「読みやすさと親しみやすさ」を両立させた字体も人気です。特に見出しやスライド、教材の見出し部分には遊明朝系を使うと、視線の移動がスムーズになり、情報の整理がしやすくなります。
また、ブランドや学校の案内などでは、雰囲気にあわせて両方を組み合わせることもあります。例えば、本文には明朝体、見出しには遊明朝を使い分けると、公式感と親しみやすさのバランスが取れます。
以下のポイントを覚えておくと、 font 選びがスムーズになります:
- 目的を明確にする(公式文書か、ウェブの案内か、看板か)
- 読みやすさの基準を決める(長文が多いか、短い見出しが中心か)
- 雰囲気を想像して、ブランドの印象に合わせる
実際の作業では、まず原稿を読みやすい文章にし、次にフォントの候補を3つ前後に絞り、最後に実際の紙とスクリーンで見比べます。これを繰り返すだけで、あなたの資料が見やすく、伝わりやすくなります。
なお、フォントの著作権にも注意してください。商用資料やウェブサイトで使う場合は、ライセンス条件を確認してから使いましょう。
その点を守れば、明朝体と遊明朝は、同じ「文字の世界」にある仲間です。目的にあわせて使い分けることで、読み手に伝わる力を高めることができます。
友達とカフェで遊明朝の話をしていたときのこと。私はスマホで遊明朝のサンプルを見せながら、ニュースレターの見出しに向いている理由を説明していました。友達は「遊明朝って、遊び心があるのに読みやすいのが不思議だね」と笑いながら言いました。そこで私は「実は細かな線の差と字形の丸みが、目の移動を助けてくれるんだ」と述べ、具体的な見出し例を並べて比べました。結局、プレゼン資料では本文を明朝、見出しを遊明朝にすると、説明のテンポと印象の両方をコントロールできるという結論に至りました。この雑談の中で、字体は単なるデザインではなく、読みやすさと場の雰囲気を整える“道具”だと再認識しました。
次の記事: ハングル書体の違いを徹底解説|印象を決めるポイントと使い分け »





















