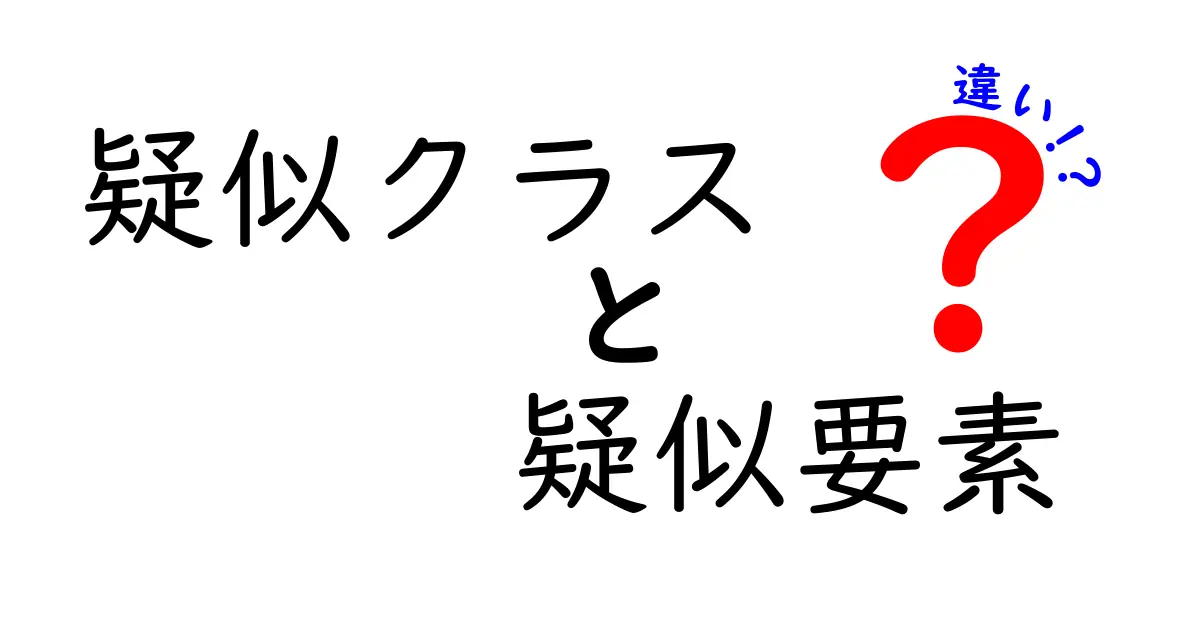

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
疑似クラスと疑似要素の基本的な違いを理解する
疑似クラスと疑似要素は、HTMLの実際の要素を追加せずに特定の部分だけを選択・装飾するための仕組みです。まず大切な点は、疑似クラスは要素の状態を表すものであり、マウスを乗せたときやフォーカスを受けたときなど、要素の状態に応じてスタイルを適用することです。例えば :hover はリンクにカーソルを合わせた時の見た目を変えるものです。一方、疑似要素は要素の内部の特定の場所を対象にして装飾を追加するものです。よく使われるのは ::before と ::after で、要素の前や後ろに空間を作ってマークを置いたり、装飾の背景を追加したりする用途です。
疑似クラスと疑似要素の使い分けのコツは、実装上の「何が DOM に存在するのか」をまず決めることです。疑似クラスは状態変化に応じた見た目の変化、応答性、アニメーションの起点となることが多く、マウスオーバー、フォーカス、アクティブ状態、特定の親要素の中の子要素の位置合わせなどが典型です。疑似要素は装飾のための追加的な領域を作る場合に有効です。例えばリストの最初の文字を大きくしたい、段落の最初の文字だけ色を変えたい、ボタンの前後に小さなアイコンを置きたいといったケースです。
以下は理解を深めるための要点整理です。
結論として、何かを“追加の見た目要素として描く”場合は疑似要素、状態変化や相互作用に応じた変化を実現する場合は疑似クラスを使うのが基本的な考え方です。これにより、DOMを複雑に増やさずにデザインをきちんと分けて管理できます。表現力は両方を組み合わせることで広がり、ウェブページのアクセシビリティや保守性も高まります。
実際の使い分けと具体的な例
実務での使い分けは、まず「この部分は DOM には存在しないが見た目だけ変えたいのか」という観点から始めると分かりやすいです。例を挙げて考えると、リンクをカーソルに合わせて色を変えたいときは疑似クラスの :hover を使います。これは DOM に新しい要素を追加せず、既存のリンクの見た目だけを変える手法です。いっぽう、リストの各項目の前にアイコンを表示したい場合や、段落の最初の文字を大きくして見出し風の雰囲気を作りたいときは疑似要素の ::before や ::first-letter を使います。これにより文章の構造を汚さずに装飾を追加できます。
もう少し具体的に見てみましょう。例えば、ボタンの前に小さな点をつけたい場合は ::before を用いてその点を挿入します。これにより HTML はシンプルなまま、視覚的な補助を追加できます。また、長い文章の最初の行の色を変えたいときは ::first-line を使うと、段落全体を改変せずに初回の表示だけをスタイルできます。これらの技法は、アクセシビリティにも配慮した設計に役立ちます。たとえば focus ring の表示を統一したい場合にも、疑似クラスを活用するのが効率的です。
- 疑似クラスは“状態や条件”に応じた変化を表現するのに適している。
- 疑似要素は“装飾や追加の領域”を作るのに適している。
- 両者を組み合わせることで、DOMを増やさずに美しいデザインが実現できる。
注意点としては、疑似要素は既存の要素の前後にしか追加要素を描画できないこと、疑似クラスの中でも CSS の cascade(継承と優先順位)に注意することです。特に 定義済みの支持ブラウザの差異 を意識する必要があります。古いブラウザでは ::before や ::after の挙動が現代の仕様と異なる場合があるため、実装前の検証を怠らないことが大切です。最後に、設計時には「どの装飾を疑似要素で、どの装飾を疑似クラスで扱うか」をチームで共有し、命名規則を決めておくと保守性が格段に上がります。
ある友人の話を思い出す。彼はデザインの段階で疑似要素を過剰に使い過ぎて、HTMLはシンプルなのに CSS がどんどん長くなってしまった。最初は ::before でちょっとしたアイコンを置いただけだったが、結局はアイコンの色変更やサイズ調整、さらにはアイコンのアニメーションまで追加していくうちに、どこで何が装飾されているのか分かりづらくなってしまった。彼が学んだのは、疑似要素は装飾の追加には強力だが、過剰に使うと CSS の可読性が落ちるということだった。使用は“必要最低限”を意識するのがコツだ。疑似クラスは状態の変化を美しく表現するための道具として活躍する。こうした使い分けを身につけると、HTML を汚さずにデザインの幅を広げられる。





















