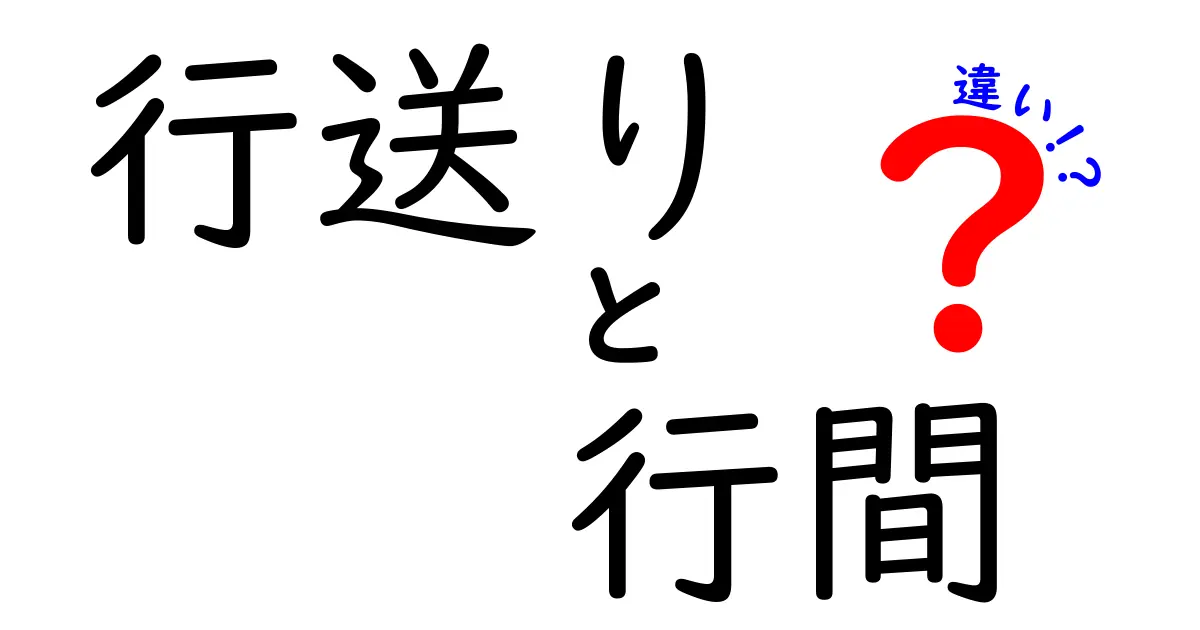

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
行送りと行間の基本を理解する
はじめに、行送りと行間はどちらも文字の列を読みやすくするための「縦の空白」ですが、指す意味には微妙な違いがあります。デザインや文字組みの現場では、行送りと行間を混同せずに使い分けることが重要です。行送りは1行の基準となる高さ全体を指し、行間は実際の文字の下端と次の行の上端の間に入る空白のことを指します。これらは、印刷ならインチやポイント、デジタルならpxやemで調整され、文章の雰囲気や読みやすさに大きく影響します。
たとえば、教科書のように読みやすさを最優先する場面では、行間を適度に広げることで読み手の目の疲れを減らせます。一方、狭いレイアウトや情報量を多く詰めたい場面では行送りを微妙に縮めて総行数を増やすことがあります。
この違いを知ると、同じ本文でもデザインの目的に合わせて達成したい効果を狙いやすくなります。
行送りと行間の定義と違い
まず基本を整理します。行送りは「基準線間隔」とも呼ばれ、1行分の総高さを決める要素です。文字の高さ(x-heightや ascender/descender の分)を含んだ、行と行の間の仮想的な⼀本の線の間隔を指します。デザインソフトやCSSでは、この行送りを決めることで全体のボリューム感が決まります。
一方、行間は実際に文字が描かれていない空白の部分、つまり行と行の間に存在する“余白”のことです。行間を広げると読みやすさが向上することが多い一方、行間を狭くしすぎると行同士がぶつかるように見え、連続して読むのが難しくなります。
両者は密接に関係していますが、行送りが全体の高さを決め、行間がその高さの中の余白の分をどのくらいとるかを決める、という役割分担が基本です。たとえば、フォントサイズが12ptの場合、行送りを14ptに設定すると、総高さが14ptになります。ここからフォントの実際の描画範囲と空白の配分を見直すことで、読みやすさの雰囲気を作れます。
ポイント:デザイン上の「余白感」を作るには、行送りと行間のバランスが鍵です。読みやすさとページの美しさを両立させるには、実際の読み手の視線の動きを想像して調整するのがコツです。
実務での使い分けと注意点
実務での使い分けは、作業環境と仕上がりの目的で変わります。印刷物では、紙の質感やフォントの実寸を考慮して行送りを設定します。紙が薄い場合は行間を広げて視認性を高めることが多く、逆に厚い紙では行間を控えめにして行数を増やすこともあります。
また、Webや電子書籍では、表示機器の解像度やブラウザのレンダリング差を考慮してline-heightの設定を行います。CSSでline-heightを1.2〜1.8程度に揃えるのが一般的ですが、フォントファミリーや文字サイズに合わせて微調整します。行送りが大きすぎると、スクロールの頻度が増え、読者の集中力が途切れやすくなります。逆に小さすぎると、見た目がぎゅっと詰まって読みづらくなるため、慣習的には1.2〜1.5程度の範囲を試して、本文の長さや段落の構造に合わせて微修正します。
具体的なコツとしては、段落間に空白を増やすよりも「行送りを調整して全体の高さを揃える」方が、行間の均一感が生まれやすいという点です。さらに、段落の長さを適切に保つことで、行間の効果を最大化できます。
まとめとして、行送りと行間はセットで考えるべき要素です。文章の目的(読みやすさ、雰囲気、情報量の多さ)に合わせて、段落ごとに微調整を繰り返すことが、読みやすいデザインの鉄則になります。
ある日、デザイン部の友達と話していて、行送りと行間の違いを例えるなら「列車の車両の高さ」と「列車の停車駅までの距離」みたいな感覚だね、と言われました。行送りは列車の総高さ、つまり車両が地面からどれくらいの高さで並んでいるか。その高さを決めるのが行送り。行間は車両同士の間隔、つまり停車駅と駅の間の空白の距離。実務ではこの2つを別々に調整することで、本文のリズムを作ります。たとえば本を開いたとき、行送りが大きいとゆったりとした印象に、行間が広いと読みやすさが増します。私は最近、プレゼン用のスライドで行送りを少し抑え、行間を広げると、情報量が多くても見やすいデザインになることに気づきました。結局、目的に合わせてこの2つを使い分けることが大切ですね。





















