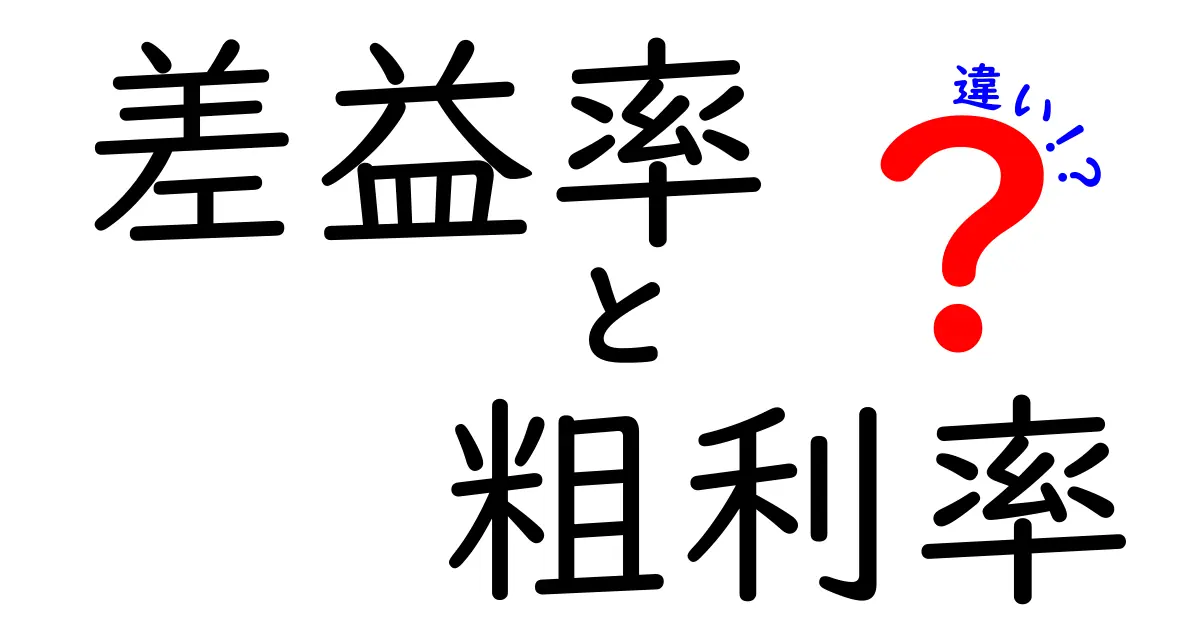

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
差益率と粗利率の基本を理解しよう
「差益率」と「粗利率」は、数字を見ただけで混乱しやすい言葉です。結論から言うと、どちらも「売上高に対してどれくらい利益が残るか」を表す指標ですが、使われ方や意味する範囲が少し違います。まずは基本の定義を押さえましょう。
粗利率とは、売上高から直接かかった原価を引いた「粗利」を売上高で割って得られる割合です。公式は 粗利率 = (売上高 − 売上原価) ÷ 売上高 × 100。ここでの「売上原価」はモノを作るために直接かかった費用を指します。
つまり、製造業や自社商品を持つ企業では、材料費や直接労務費などが原価として計算され、粗利率はその原価を引いた後に残る利益の割合を示します。
次に差益率は、売上高から「仕入高(仕入れにかかった費用)」を引いた金額を分母にして割る場合に使われることが多い用語です。公式は 差益率 = (売上高 − 仕入高) ÷ 売上高 × 100。ここでの「仕入高」は、小売業などで商品を仕入れて転売する場合の費用を指すことが多く、在庫を抱えずに売買を回すビジネスモデルでは差益率の考え方が直感的に理解しやすいです。
つまり、差益率は“仕入れをどれだけ抑えられたか”という観点で利益を評価する指標として使われることが多いのです。
この二つの指標の基本的な違いをつかむには、鋭い比べが必要です。
粗利率は“自社で作る・製造する商品”が対象になり、原価の中身が多いほど下がります。
差益率は“仕入れて販売する商売”の世界で、仕入れを安く抑えられるかが焦点になります。
どちらも売上高という分母を使うため、数値が大きいほど多くの利益を生む可能性を示しますが、原価の考え方が違うため、同じ売上高でも数値が異なることが普通です。
ここからは具体的な計算の例を見ていきましょう。例として売上高100万円、売上原価60万円、仕入高50万円の場合を考えます。
・粗利 = 100万円 − 60万円 = 40万円。
・粗利率 = 40万円 / 100万円 × 100 = 40%
・差益 = 100万円 − 50万円 = 50万円。
・差益率 = 50万円 / 100万円 × 100 = 50%
この組み合わせでは、同じ売上高でも原価の分布が違うと、粗利率と差益率が異なって見えることがわかります。
表を使って視覚的に整理しましょう。以下の表は、売上高と原価の関係を整理して、どの項目がどの指標に影響を与えるかを示しています。
表は日常的な買い物のイメージにも近いので、手元のノートでメモしておくと理解が深まります。
この表を見れば、粗利率と差益率の大きな差が出る場面を想像しやすくなります。
例えば、自社で製造している商品では原価の中に開発費や設備費の一部が含まれている場合があります。これが粗利率を低く見せることがあります。一方で、仕入れを安く抑えられれば差益率は高くなる場面が出ます。
つまり、同じ売上高でも“どこにコストを置くか”で指標の意味が変わるのです。
この視点を持っておくと、財務諸表の読み取りが格段に楽になります。
日常生活に置き換えるとわかりやすい
日常生活の例として考えると、粗利率は自分が作るお菓子の原材料費に近い考え方です。ケーキを作るとき、材料費が高ければ粗利が減り、結果として粗利率も低くなります。対して差益率は、100円の商品をお店で仕入れて販売するときの“仕入れ値”と“売値”の関係です。仕入れ値をどう抑えるか、つまりコストを下げられれば差益率が上がります。
この二つの指標は、同じ売上高という土俵を使っていても、視点を変えるだけで見える数字が変わる良い例です。
財務の数字は、正しく読み取ると自分の生活にも役立ちます。家計を見直すときにも同じ考え方を使えるので、練習として覚えておくと良いでしょう。
友だちとカフェで差益率と粗利率の話をしている雑談風の深掘り。僕がたとえば100円のクッキーを作って売るとき、材料費が40円、包装費が5円、そして自分の手間代をどう見積もるかで数字が変わる、みたいな話です。粗利率は材料費を含む“作る側の原価”の割合を表し、材料費が多いと粗利率は低くなります。差益率は仕入れ値を軸に考える指標で、仕入れ値を下げれば差益率は高くなります。つまり同じ売上高でも、製造業と小売業では使う計算が変わり、見える利益の姿が変わります。日常の買い物の感覚で理解を進めれば、財務の数字は難しくなく、家計の見直しにも役立つという結論にたどり着くことができます。





















