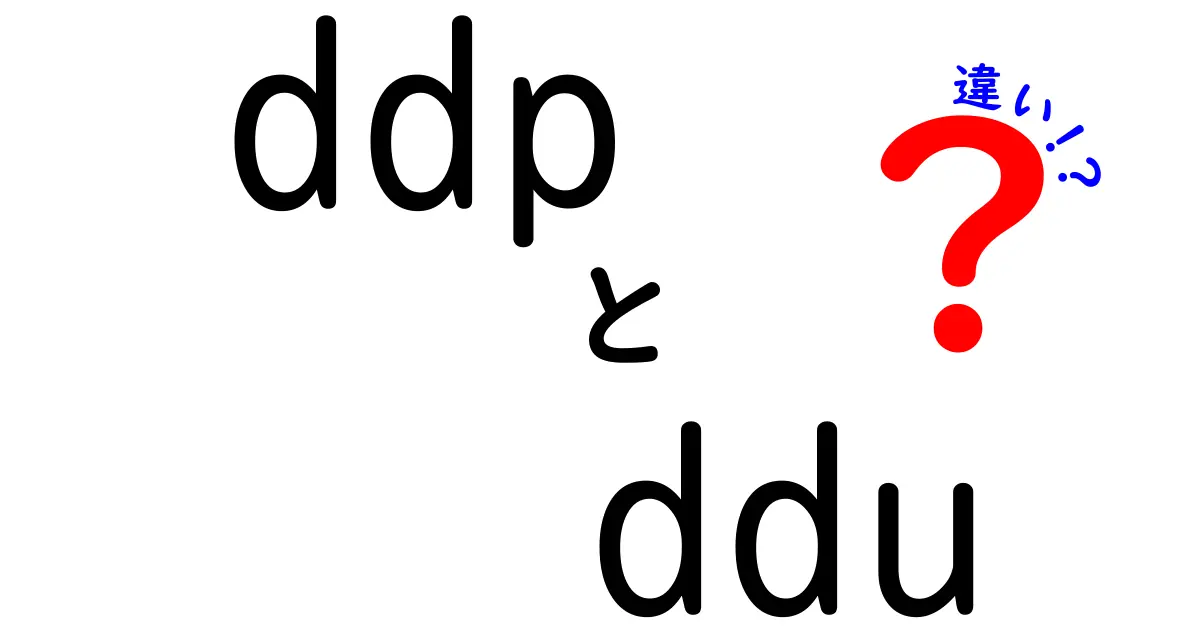

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ddpとdduの違いを徹底解説:初心者にもわかる選び方
国際取引で使われるインコタームズの用語の中でも、DDPとDDUは特に混乱しやすいポイントです。
この2つの用語は、誰が関税や税金を負担するのか、誰がどの手続きを進めるのかという「責任の所在」が大きく異なります。
まず結論から言うと、DDPは売り手が関税・税金・輸入手続きまで含めて責任を負う条件、DDUは輸入時の関税・税金が未払いで、買い手がその費用と手続きを負担する条件です。
この違いを理解していれば、見積もりの時点で正確な総費用を比較でき、トラブルを避けやすくなります。
以下では、基本の定義、具体的な責任範囲、そして実務での使い分け方を、初心者にもわかりやすい言い方で丁寧に解説します。
さらに、現実の取引でよくあるケースを想定して、注意点とコストの見積り方を示します。
最後には、DDPとDDUを比較する表も用意しました。これを見れば、一目で違いが分かるはずです。
DDPとは?誰が何を負担するのかを詳しく解説
DDP(Delivered Duty Paid)は、売り手の責任範囲が最も広い条件の一つです。
輸出入のためのすべての税金・関税・手続き・通関費用を売り手が負担し、買い手は指定された場所で商品を受け取ります。
この場合、税金や関税、そして通関手続きの費用も含まれるため、買い手にとっては「追加費用の心配が少なく、到着後すぐに使える」というメリットがあります。しかし、売り手側は費用と手続きの範囲が広くなるため、価格設定が難しくなることが多いです。
実務では、ECのように一般消費者に商品を届けるケースや、検品・納品までを一括して行いたいケースでDDPが選ばれやすい傾向にあります。
ただし、販売者は輸出入の税率・規制の変動、通関の遅延、保険料の負担増などのリスクも背負うことになります。
つまり、DDPは「売り手にとっては責任とコストが増えるが、買い手には最も分かりやすい条件」という特徴があります。
DDUとは?現代の貿易での位置づけと注意点
DDU(Delivered Duty Unpaid)は、売り手が輸出までの手続きや費用を負担しますが、輸入時の関税・税金・通関費用は買い手が負担する条件です。
このため、商品が目的地に届くまでの道のりは売り手がある程度確保しますが、国内での通関手続きや関税の支払いは買い手の責任となります。
DDUは、コストを抑えつつ、現地の通関手続きを経験豊富な買い手に任せたい場合に適しています。
ただし、買い手にとっては最終的な総費用がどれくらいになるかを事前に把握しにくく、納期の遅延リスクや追加料金の発生リスクが高まる点には注意が必要です。
また、現在のインコタームズではDDU自体は用語として書かれず、近年は主に DAP・DAPDPU などの表現に置き換えられるケースが多い点も押さえておきましょう。
つまり、DDUは現代の取引では「費用を前提とした交渉をしやすいが、買い手側のリスク管理が重要」という特徴があります。
実務でのポイントとよくある誤解
実務での選択は、単純な金額だけで決めてはいけません。
DDPを選ぶと総費用が明確で、商談が進みやすい反面、予算オーバーのリスクがあります。一方、DDUは初期費用を抑えられるように見えるものの、輸入時の手続きや関税の支払い準備が必要になる分、遅延や追加費用が発生しやすくなります。
ここで大切なのは、「どこで、誰が、どの費用を負担するのか」を契約書に明記すること」です。納品場所、通関手続き、保険、リスク移転の時点を明確に書面化しておくと、トラブルを防ぐことができます。
また、実務上は保険の適用範囲や輸送中の損害賠償責任の取り決めにも触れておくと安心です。
総じて、DDPとDDUを使い分けるには、相手国の法規制、運送手段、納期の要求、そして自社のコスト構造を総合的に考慮することが重要です。
実務で使えるポイントまとめ
以下のポイントを押さえておくと、現場の判断が楽になります。
1) 責任範囲を契約書に必ず明記する。
2) 総費用の内訳を見積りに含める。特に関税・税金・通関費用の扱いを正確に。
3) 納品場所とリスク移転のタイミングをはっきり決める。
4) 保険の有無と適用範囲を確認する。
5) 現地規制や税率の変化に対応できる余地を作っておく。
DDPという用語は、海外から商品を買うときに『全部任せて欲しい』という買い手の心強い要望と、海外へ物を売るときに『費用が増えるが簡便さを提供できる』という売り手の戦略が交差する場面でよく使われます。現場では、税金の計算根拠や通関の進行状況、保険の適用条件などが複雑になることが多く、しっかりと契約書へ落とし込むことが成功の鍵です。DDPを選ぶときは、最終的な総費用を事前に把握できるよう、見積もりの内訳を細かく確認する習慣をつけましょう。
この理解が深まると、国をまたぐ取引での交渉力が高まり、よりスムーズなビジネス展開につながります。
前の記事: « CFRとEXWの違いを徹底解説!初心者のための実務ガイド





















