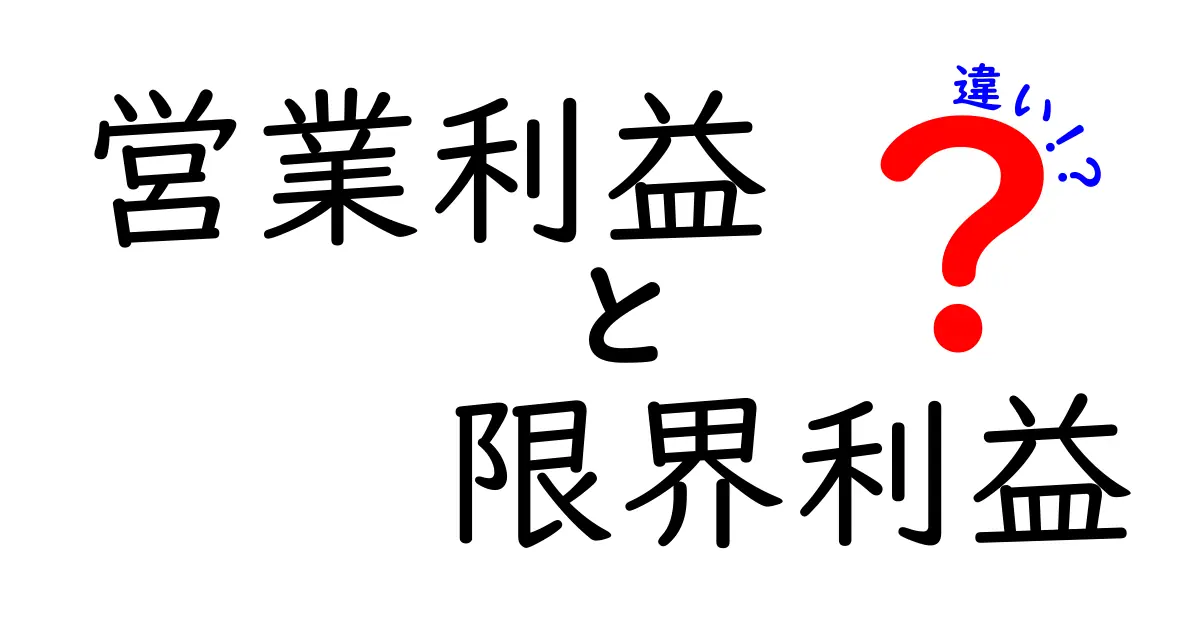

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
営業利益と限界利益の違いを正しく理解するための基本
まずは用語の定義から。営業利益は企業の本業で生み出す利益です。売上高から売上原価と販管費を引いた残りが営業利益になります。要は日々の活動で実際に稼いでいる本業の黒字の状態を指します。ここで大切なのは固定費と変動費の区別をきちんと意識することです。固定費は生産量や売上が増えても減ってもほぼ変わらない費用で、例として家賃や役員報酬などがあります。
一方限界利益は売上高と変動費の差、追加で一単位を売ったときにどれだけ貢献できるかを示す指標です。変動費は製品を作ったり販売する際に直接かかる費用で、売上が増えるほど増えます。固定費はこの段階では含まれません。
この二つの指標は用途が異なるため同じ場面で比べるだけでは不適切です。つまり営業利益は総合的な本業の収益力を、限界利益は追加売上の貢献度を示すのです。
次に実務での見方を整理しましょう。まず営業利益を見て企業が長期的に黒字を出せるかを判断します。次に限界利益を使って製品の値上げ値下げ新製品の導入がどれだけ影響するかを試算します。例えばある製品の一単位あたりの限界利益が高い場合追加販売が固定費を埋める力になる可能性が高いです。ここでも変動費を抑える施策が限界利益を改善する鍵になる場合が多いです。表計算ソフトでこれらを分けて見るとどの製品が黒字化の鍵かが見えやすくなります。
実務の例と計算のコツ
簡単な例で違いを見てみましょう。仮に売上高が1000、変動費が600、固定費が100の場合、限界利益は400、営業利益は300となります。固定費をさらに削減したり価格を調整してみると営業利益がどう変化するかを想定できます。このように限界利益は追加売上の貢献度を測るのに適し、営業利益は現状の本業の安定度を測る指標として使われます。表計算ソフトでこれらを整理すると製品別の貢献度が一目で分かります。
このように双方の指標を状況に応じて使い分けることで企業の収益性を正しく判断できます。営業利益は現状の本業の健全性を、限界利益は追加売上の貢献度を示す道具として扱うのがコツです。さらに理解を深めるには実際の財務諸表を見ながら各製品の売上高変動費固定費を分解して計算してみるとよいです。これを繰り返すと経営判断の入口が自然と身につきます。
放課後の教室で友達のミカと市場の話をしていた。彼女は新しいカードの割引キャンペーンについて聞いてきた。私は営業利益と限界利益の話を雑談風に説明した。限界利益は追加で売れたときにどれだけ儲かるかを示す指標だから今この瞬間の儲けの元と理解してもらう。逆に営業利益は固定費を含む全体の黒字であり会社全体の安定度を表す。ミカは納得して、今度のイベントの価格設定では限界利益を重視してみようとつぶやいた。こうして数字の世界は日常の会話にも入り込み、難しそうに見える経済の話も身近に感じられるようになる。





















