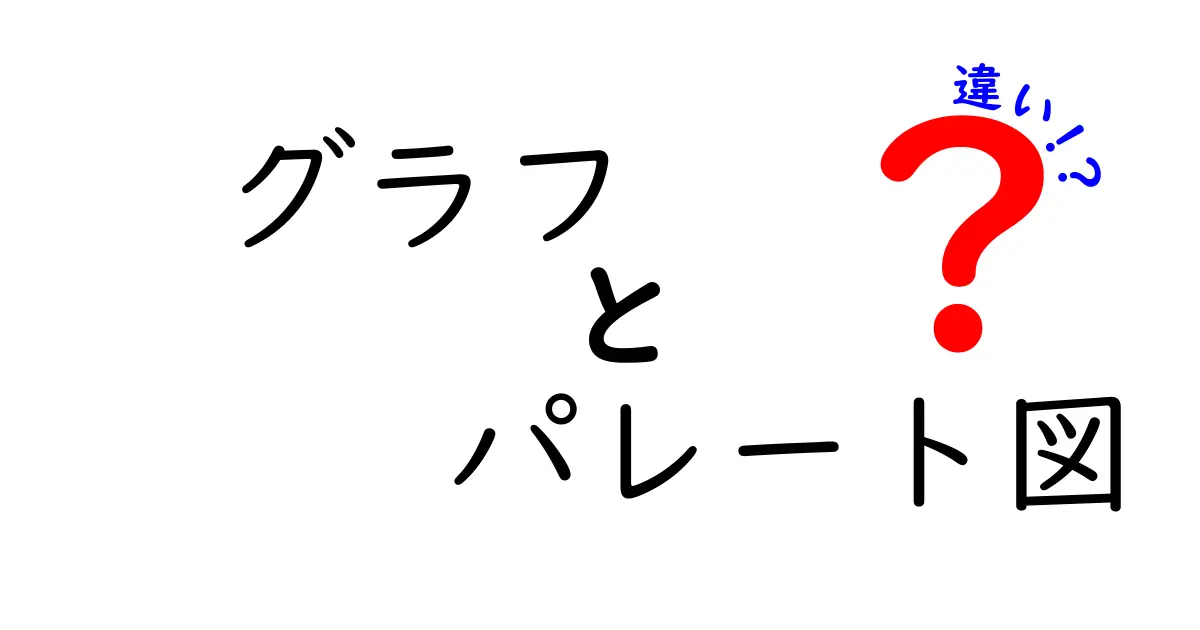

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:グラフとパレート図の基本的な違いを知ろう
グラフはデータを「見える化」するための道具の総称です。グラフには棒グラフや折れ線グラフ、円グラフなどいろいろなタイプがあります。これらはデータの分布、傾向、比較などを伝えるのが目的です。対してパレート図は、データをある特定の順番で並べ、累積の割合を同時に示す特別なグラフです。パレート図の最大の特徴は「重要な要因を優先して見ることができる」点です。80/20の法則という言葉を知っている人も多いでしょう。これは「全体の80%の影響が、わずか20%の要因から来る」という意味で、パレート図はこの考え方を視覚的に示すのにとても適しています。
日常の課題解決でも、データをただ並べるだけのグラフより、何が重要かを最初に示してくれるパレート図のほうが、意思決定が早くなります。例えば学校の行事の予算配分を検討するとき、売上のデータをただグラフ化するより、上位の売上要因を並べ替えて示すパレート図のほうが「何を優先すればよいか」がすぐ理解できます。この違いを知っておくと、データの取り扱いがぐっとラクになります。
また、グラフを作成する前にデータを正しく整理することも大切です。カテゴリごとにデータを合計し、欠損値や外れ値がある場合はどう扱うかを決めておくと、パレート図も正しく機能します。
パレート図の特徴と使い方
パレート図では、横軸にカテゴリを並べ、縦軸にはそのカテゴリの値を表す棒グラフを描きます。さらに別の縦軸に累積割合を示す折れ線を引くのが基本の形です。これにより、どのカテゴリが全体のどれくらいを占めているかが一目で分かります。読者は、上位のカテゴリを押さえるだけで全体の要因の大半を理解できるため、改善計画を立てる際にとても役立ちます。
パレート図を実際に作る手順はシンプルです。まずデータをカテゴリ別に集計し、頻度や金額の大きい順に並べます。次に累積割合を計算し、折れ線として追加します。最後に棒グラフの高さと折れ線のポイントを読み取り、上位のカテゴリを特定します。これを用いて、予算の割り振りや改善の優先度を決めると、行動の指針がはっきりします。以下の表は、通常のグラフとの違いを整理するのに役立つでしょう。
このように、グラフとパレート図は目的が少し違います。あなたが何を伝えたいのか、何を重視して伝えたいのかを意識して選ぶことが大切です。パレート図は「少数の要因が全体に与える影響」を強調してくれるので、決断を伴う場面で特に力を発揮します。強調したい点を読み手に伝えたい場合は、パレート図を使うことをおすすめします。
ある日、教室のデータの話題で、友だちがパレート図の意味を尋ねた。私は「80/20の法則を実感する道具なんだ」と答え、具体例として学校の購買データを例に挙げた。上位数点だけで全体の大半が決まるケースは、身の回りにもよくある。たとえば文房具の消費を見ても、100個のうち20個が全体の売上の80%を占めることが多い。パレート図はこの事実を視覚化してくれる。だから、予算の使い道を決めるとき、どのカテゴリを重点的に改善するべきかが一目でわかるのだ。





















