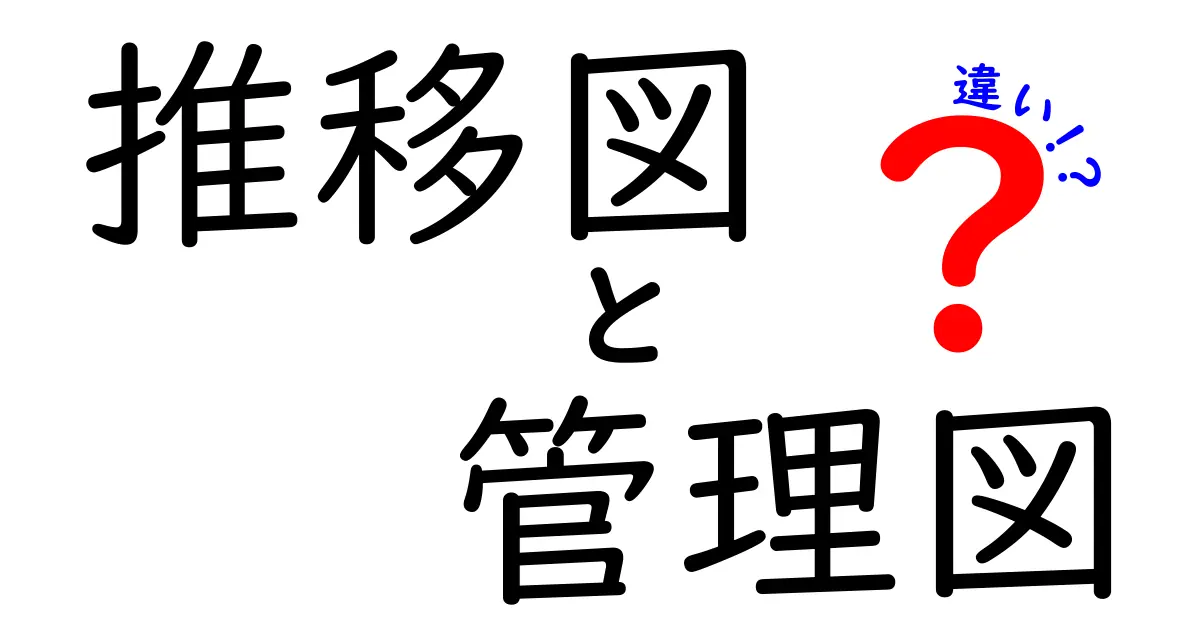

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
推移図と管理図の違いを徹底解説|現場で役立つ使い分けと選び方
ここでは、まず「推移図」と「管理図」がどういう目的で使われるのかを、実務と学習の両方の場面を想定して、分かりやすく解説します。
まず推移図とは、データの点を時間軸に沿って並べ、変化の方向性やリズムを読み取るためのグラフです。時系列のパターンを把握するのに適しており、季節性、周期性、急な変動、外れ値の兆候などを視覚的に示します。対して管理図は、データが「安定しているか」「規格の範囲内に収まっているか」を判断するための道具です。上下限線や中心線を設定し、データがその範囲を超えたときにアラートを出します。こうして、プロセスの状態を継続的に監視するのが管理図の役割です。
この二つの図は、「何を見たいか」が違うだけで、実は補完的な関係にあります。
推移図で全体の動きとトレンドをつかみ、管理図で異常を即座に検出して対処する、という流れが品質管理の基本リズムです。
たとえば食品工場の温度・湿度データを扱う場合、推移図は「季節の影響や日による変動」を可視化し、管理図はその温度が規格内に収まっているかを監視します。
現場の人たちが混乱しないよう、見せ方にも工夫を重ねるとよいでしょう。例えば色分けや注釈を使い、初心者でも迷わず読み取れる図にすることが大切です。
このような理解を土台に、データの扱い方を段階的に学ぶと、統計の世界がぐっと身近になります。
違いを理解する具体的なポイント
この二つの図の差を実務でどう使い分けるかを、具体的なケースで考えると理解が深まります。推移図はデータがどのように変化しているかを直感的に示し、季節性や日々のばらつきを見つけやすくします。管理図は「このデータが安定かどうか」「中心線からのズレが小さいか大きいか」を判断する核となる道具です。両者を組み合わせると、意思決定の速度と正確さが上がります。
例えば製造ラインの温度データを考えましょう。推移図は日次の高低や急に上がる日のパターンを示し、管理図はその温度が規格内に収まっているかを監視します。データをただ並べるだけでなく、色分けや注釈をつけると、現場の人にも伝わりやすくなります。
また、表現の工夫として、実務では表とグラフを組み合わせた資料が好まれます。理由は、言葉だけの説明より「見ればわかる」力が強いからです。
この章のまとめとして、推移図と管理図は相互補完的で、使い分けのコツを知ると、データの読み取りと意思決定の両方が速くなる点を覚えておきましょう。
管理図という言葉には、ただデータを線でつなぐ以上の“物語”があって、日常生活の中にも応用できるヒントが隠れています。例えばテストの点数をとって管理する場面を想像してください。中心線を意識して点数がばらつく理由を考えると、どの科目を強化すべきかがすぐに見えてきます。管理図の考え方を身につけると、友達や先生に説明する時にも“この変動は一時的か、それとも継続的な問題なのか”を判断でき、話がスムーズになります。データに惑わされず、原因を探る習慣が自然と身につくのです。





















