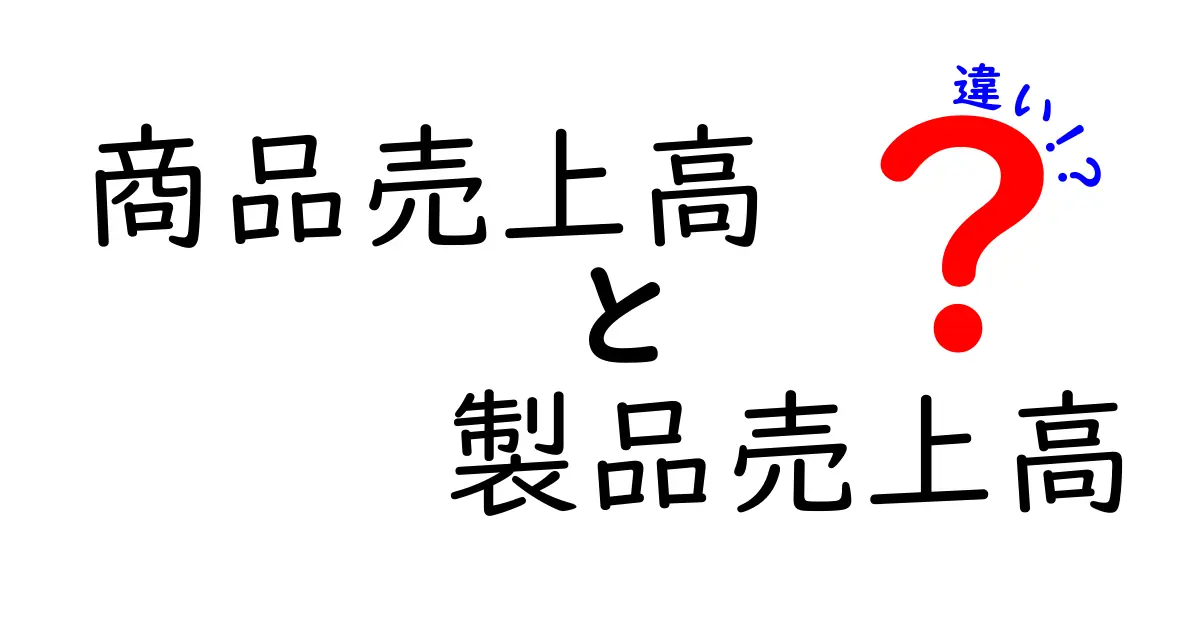

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
商品売上高と製品売上高の違いを理解する基本
まず基本を押さえましょう。売上高は企業が商品やサービスを販売して得た総額のことであり、会計上の重要な指標です。ここでの「商品売上高」と「製品売上高」は似ているようで意味が異なり、使われる場面も異なります。
ここでのポイントはどの品物が対象かを確認することです。
「商品売上高」は、仕入れて販売した品物全体の売上の合計を指すことが多く、流通業や商社系の企業で使われることが多い表現です。
一方「製品売上高」は企業が自社で製造・開発した完成品の売上高を指すのが一般的で、製造業の計測に用いられます。
つまり同じ売上高の字面でも、どの品物が対象かで意味が変わるのです。ここを混同すると、売上構成の分析や予算の見積もりがずれてしまいます。
この違いを正しく理解しておくと、外部の決算説明資料を読んだときや社内の部門別業績を比較するときに、数字の背後にある実態をつかみやすくなります。
以下のポイントを押さえましょう:どの品物が対象かを確認する、取引の性質を確認する、製造と販売の関係を混同しない、などです。
次に実務上の違いについて詳しく見ていきます。商品売上高は、流通業のように仕入れて顧客に再販する企業で重要な指標です。市場や取引先の傾向を把握しやすく、販売チャネル別の分析にも向いています。製品売上高は、製造業で自社が作った製品の売上を分解する際に使われます。製品Aと製品Bの売上の寄与を比較したり、製品ライフサイクルのステージごとに売上の伸びを評価したりするのに適しています。
ここで覚えておきたいのは、商品のことだけを見るだけでは全体像は見えにくく、製品別の収益性やコストの関係を理解するには両者をセットで見る必要があるということです。たとえば、同じ1000万円の売上でも、商品売上高が増えているのに製品売上高が低下している場合、在庫回転や取引条件の悪化が原因かもしれません。
表を使って整理すると理解が深まります。次の表は商品の売上高と製品売上高の基本を並べたものです。
この表を読むと、どちらの指標を知りたいかで見るべき数値が変わることがわかります。
結論として、売上高の指標を使い分けるコツは、分析の目的と対象を最初に決めることです。
会社の現状把握や予算作成の際には両方の数値を組み合わせて見ると、売上の構造が見え、どの製品が利益の源泉なのか、どの販路が成長を支えるのかが見えてきます。
また外部報告時には用語の定義を必ず確認してください。企業ごとに呼び方が異なることがあり、同じ言葉でも意味が違う場合があります。
最後に、定性的な情報と定量的な数字を結びつけて読み解く癖をつけると、データの海の中で迷子になりにくくなります。
実務での使い分けと分析のコツ
売上高のこの二つの指標を現場でどう使い分けるかが、意思決定の質を大きく左右します。製品売上高が自社の開発した製品の出来栄えや市場性を示すのに対し、商品売上高は市場全体の動向や取引関係の安定性を反映します。こうした違いを理解しておくと、経営会議での質問にも速く答えられ、投資判断の根拠が強くなります。
具体的には、製品別の利益率を知りたいときは製品売上高と費用を分解して計算します。対して、市場規模や販路別の成長を分析する場合は商品売上高の動向を追うと良いでしょう。両者の関係を見比べることで、どの製品がどの販路で強いのか、どのチャネルを強化すべきかが見えてきます。
- 目的を最初に決める
- 対象を正確に把握する
- 両方の指標を併記して分析する
- 外部資料の定義を確認する
最後に覚えておくべきことは、データは文脈とセットで読むことです。数字そのものだけを見ても全体像は見えません。人が使う言葉の意味や、事業のビジネスモデルを理解しながら読み解くと、売上の“原因と結果”が分かりやすくなります。これを日常の勉強や将来のビジネスに活かしてください。
今日は授業後の雑談から生まれた小ネタ。商品売上高と製品売上高の違いについて、友だちと話してみたんだ。友だちは『商品売上高って何を指してるの?』と素直に質問してきた。僕は「商品売上高は仕入れて売る全体の売上、製品売上高は自分たちが作って売る完成品の売上」という、分かりやすい例を出して説明した。すると友だちは「なるほど、同じ売上高でも“誰が売ったのか”で意味が変わるんだね」と納得。更に僕らは、学校のバザーの話に置き換えて考えた。仕入れて売るお菓子は商品売上高、手作りのクラフトは製品売上高。こうして日常の中に数字の世界を見つけると、難しさがぐっと身近になるんだ。数字は難しい言葉じゃなく、現実の行動の結果だと理解できれば、勉強も楽しくなるはずだよ。次は自分の学校の部活で、どちらの指標を使って成果を測るべきか、じっくり考えてみたい。





















