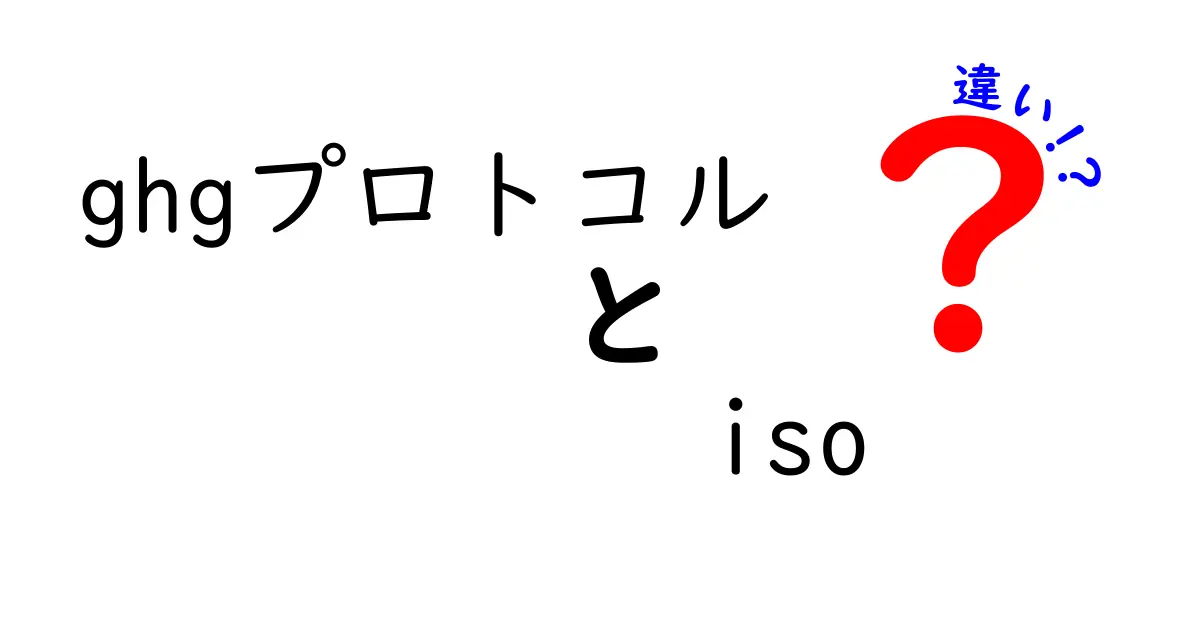

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ghgプロトコルとISOの違いを知る基本
地球温暖化対策が進む中、企業や自治体が自社の排出量を適切に把握して公表する機会が増えました。ここでよく出てくるのが「GHGプロトコル」と「ISO」という二つの考え方です。GHGプロトコルは、排出量の会計と報告の実務的な枠組みとして広く使われ、世界中の企業が日常的に参照します。一方、ISOは国際標準化機構が作る公式な標準群で、測定だけでなく検証や認証のプロセスまで含む総合的な規則です。これらは同じゴールを目指しますが、現場での使い方や求められる品質が異なります。
まず大きな違いを一言で言えば「使われ方と目的の違い」です。GHGプロトコルは“どれだけ排出したかを数える方法”を示す実務ガイドで、企業が自分の排出を把握し、報告する際の標準的な手順を提供します。ISO 14064は“排出量を正確に測り、公表するための標準化されたプロセスと検証のルール”を提供します。つまり、GHGプロトコルは実務の道具箱、ISOは品質の保証をつくる規格と捉えると理解しやすいです。
この違いをさらに具体的に見ると、GHGプロトコルには三つの主要ツールがあります。企業全体の標準(Corporate Standard)、サプライチェーンを含むスコープ3の標準、製品レベルの製品標準などです。これらは「どの範囲をどのように数えるか」という実務の設計図であり、柔軟性が高いのが特徴です。一方ISO 14064は、組織全体の排出量の測定と検証・認証のプロセスを規定する点で重みが少し違います。ISOは第三者による検証を前提とする場面が多く、信頼性を高める仕組みとして機能します。
このような表の違いを理解すると、現場での準備物が見えてきます。データの収集方法、境界の設定、報告の形式、そして検証を受けるかどうかといった項目が、まずはっきりと整理されます。GHGプロトコルのツール群は実務の自由度を生み出しやすく、企業が自分たちのビジネスモデルに合わせて組み立てやすいのが特徴です。ISOは、それを補完する形で“正しさの証明”という価値を付与します。
実務での適用と比較ポイント
実務でどちらを使うべきかは、目的とステークホルダー次第です。もし企業が「透明性の高い一般向け報告」を強化したい場合、GHGプロトコルの Corporate StandardやScope 3の標準を使って、幅広い範囲のデータを取りまとめるのが現実的です。反対に、正式な認証や監査を求める投資家や公共機関の要請がある場合には、ISO 14064の規格に沿って検証プロセスを組み込むのが有効です。ISOは要件が明確で、第三者検証を経ることが多く、信頼性の高い報告を実現します。
日本企業の事例を想像してみましょう。多くの企業はまずGHGプロトコルに基づく内部データの整備から始め、時にはサプライチェーン全体の排出量を把握するためにスコープ3の算定を追加します。これにより、どの部門がどれだけの排出を生み出しているかを可視化でき、改善の優先順位を決めやすくなります。次の段階として、外部の監査や認証を検討する局面でISO 14064の規格を取り入れると、投資家やパートナーに対してより強い信頼を示すことができます。
重要なポイントは二つです。第一に、「境界設定」をどうするかです。GHGプロトコルは組織の排出の範囲を決める枠組みを提供しますが、境界をどう設定するかで結果が変わります。第二に、データの品質管理の徹底です。どんな標準を選んでも、データの正確性・完全性・透明性が高くなければ意味がありません。これらを意識して運用すれば、信頼性の高い報告を継続的に作成できるでしょう。
このような表の違いを理解すると、現場での準備物が見えてきます。
データの収集方法や境界設定、報告の形式、検証の有無など、どの順番で取り組むべきかが具体的に見えてきます。
実務上の柔軟性と信頼性の保証を両立させるには、GHGプロトコルのツールを土台に、必要に応じてISOの検証要素を組み合わせるのが現実解です。
ある日の放課後、友だちと環境の話題になって「GHGプロトコルとISO、どう違うの?」と聞かれました。私はこう答えました。GHGプロトコルは“やるべきことを整えるための道具箱”で、実務の現場に合わせて自由に組み替えられる。ISOは“品質の証明書”のような役割で、検証がついてくることが多い。つまり、GHGプロトコルは現場の運用ノウハウを提供し、ISOはその運用を第三者が信頼できる形で裏打ちする仕組みだよ。私たちが覚えるべきは、どちらを使うかでなく、どう組み合わせて信頼性を高めるかという視点だと思います。





















