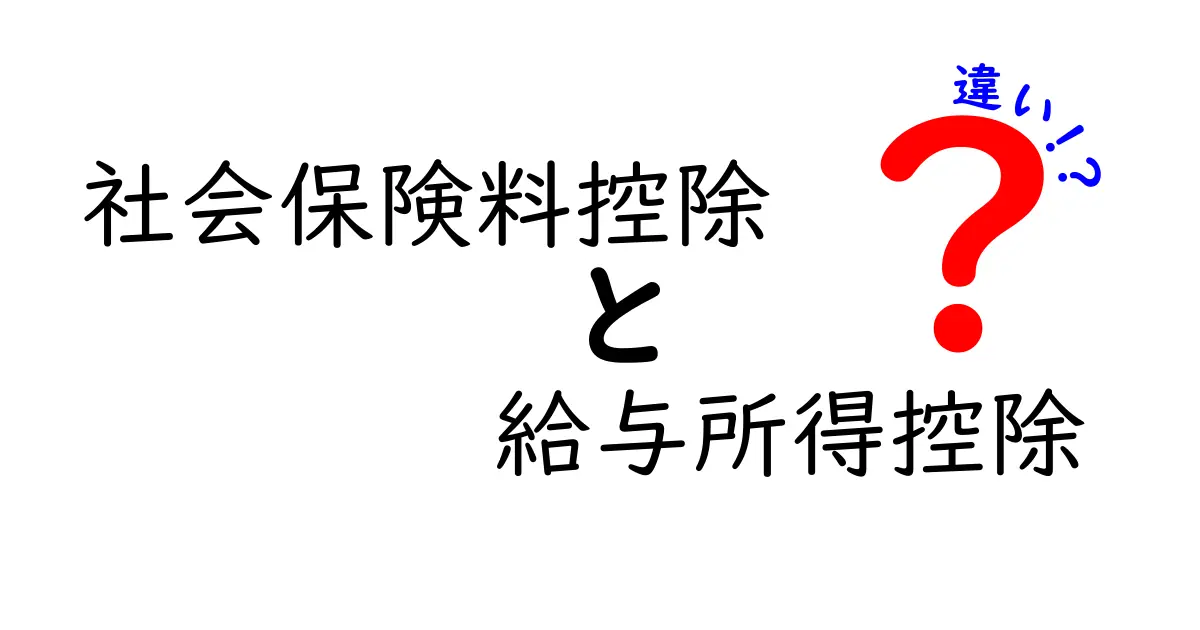

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
社会保険料控除と給与所得控除の違いとは?
お給料から差し引かれる税金や保険料について聞いたことがあると思います。その中に「社会保険料控除」と「給与所得控除」という言葉がありますが、これらは何が違うのでしょうか?
簡単に言うと、社会保険料控除は実際に支払った社会保険料(健康保険、年金など)を税金の計算から差し引く仕組みです。一方、給与所得控除はお給料から仕事にかかる経費などを差し引くための控除で、給与所得者のために国が定めた一定の金額を引いてくれる制度です。
この2つは税金を減らすための制度ですが、性質や計算方法、控除される対象が大きく異なります。
社会保険料控除とは?仕組みや対象になるもの
社会保険料控除は、健康保険や厚生年金、雇用保険といった社会保険に加入している人が、その保険料を支払った場合に所得から差し引くことができる控除です。
これは実際に支払った金額だけが控除対象となり、支払った社会保険料の全額が税金計算上の所得から引かれます。なので、保険料を多く払っている人ほど控除額も大きくなり、結果的に税金が安くなります。
具体的に控除される社会保険料は以下のとおりです。
- 健康保険料
- 介護保険料(一定の年齢以上の場合)
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 国民年金保険料
給与所得控除とは?計算方法とポイント
給与所得控除は、働いて得たお給料の中から仕事にかかる経費を差し引くイメージの控除です。自己負担する経費を一人ひとり細かく計算するのは大変なので、国が一定の計算式や表を定めて、おおよその経費として控除金額を決めています。
例えば、年収が高い人ほど控除額も大きくなりますが、限度額が決まっています。
2023年現在の給与所得控除の一例を下記の表に示します。給与等の収入金額(年収) 給与所得控除額 550万円以下 収入金額×40%(最低55万円) 550万円超~1,000万円以下 220万円+(収入金額-550万円)×30% 1,000万円超 195万円(上限額)
このように、給与所得控除はあくまで〈給与所得者の仕事に関わる経費の概算〉として、税金の計算を簡単に、そして公平にするための制度です。
社会保険料控除と給与所得控除の違いまとめ
ここまで説明した内容を簡単に整理すると下記のようになります。
| 項目 | 社会保険料控除 | 給与所得控除 |
|---|---|---|
| 意味 | 実際に払った社会保険料を所得から差し引く | 給与所得者の概算経費として税金を計算する際に控除 |
| 控除額 | 支払った社会保険料の全額 | 収入に応じて定められた一定の金額 |
| 対象 | 健康保険、年金、雇用保険などの保険料 | 給与所得から自動で差し引かれる経費控除 |
| 申告 | 証明書を添付し申告が必要 | 年末調整などで自動で適用されることが多い |
これらの控除は正しく理解することで、税金の仕組みを知り、自分の収入や支払いをより賢く管理できるようになります。
特に社会保険料控除は自分が支払った分だけ控除できるので、保険料の金額が分かる証明書は大切に保管しておきましょう。給与所得控除は、給与明細や源泉徴収票を見るとどのくらい控除されているか確認できます。
税金についてわからないことがあれば、税務署や専門家に相談することもおすすめです。
社会保険料控除って、実はあなたが払った保険料の全額がそのまま控除になるんです。つまり、健康保険料や年金の金額が増えると、控除も増えて税金が少なくなる仕組み。これは働く人にとってすごく大事なポイントで、証明書を使ってきちんと申告することが必要ですよ。たまに『控除はどれくらい受けられるの?』と気になる人も多いですが、支払った金額がそのまま控除になるから安心してOK!
前の記事: « 健康保険と労働保険の違いを徹底解説!中学生でもわかる保険の基本





















