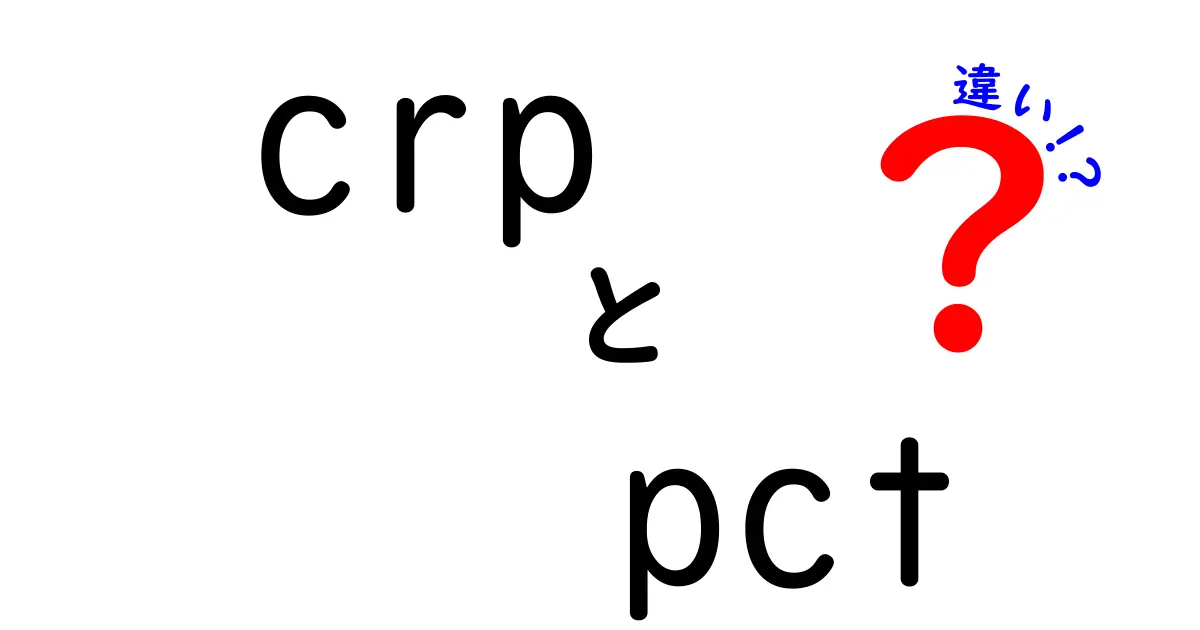

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CRPとPCTの違いを徹底解説!炎症と感染を見分けるための基本ガイド
この二つの指標は、体の中で炎症や感染が起きているかを教えてくれる重要な手がかりです。CRPは炎症の広さや程度を示す信号として働き、PCTは特に細菌感染を捉える手がかりとして使われます。この記事では、CRPとPCTの基本的な仕組み、どんな場面で使われるのか、どう解釈するべきかを、難しくならないように丁寧に解説します。中学生のみなさんにもわかるように、日常の例を交えつつ説明します。
まずは結論から。CRPとPCTは別々の役割を持つ“体のサインの種類”です。CRPは炎症が起きているかを広く知らせてくれる指標で、風邪やけが、ニキビの跡のような小さな炎症でも上がることがあります。一方でPCTは“細菌が原因の感染が進んでいるか”を示すことが多く、ウイルス性の病気ではあまり高くなりません。この違いを知っておくと、受診時の検査結果を医師がどう解釈しているのかが想像しやすくなります。
CRPとは何か?体の炎症をどう知らせるのか
CRPとはC反応性タンパク質のことで、肝臓で作られ、体の炎症があると血液中の量が増えます。体で炎症が起こると、IL-6のような炎症性の信号が出て、肝臓はCRPを作って血流に放出します。CRPは急速に増減する性質をもち、通常は数時間で上がり、24〜48時間かけてピークに達します。健康な人のCRPは0〜1 mg/L程度ですが、炎症が起きると数値は大きく上がることがあります。CRPは非特異的な指標なので、炎症の原因が必ずしも病原体の感染とは限らず、怪我・手術・自己免疫疾患・慢性疾患など様々な理由で上がることがあります。治療の経過を見る際に、CRPの値が下がるかどうかを見ることで“炎症が収まってきているか”を判断する助けになります。高いCRPの数値だけを見て判断するのではなく、症状の変化、他の検査結果、時間の経過とともにどう推移しているかを総合的に見ることが大切です。なお、CRPは感染の有無を直接示すものではない点に注意が必要です。風邪などウイルス性の病気でもCRPが少し上がることがありますし、心筋梗塞など炎症とは別の理由で上がることもあります。
PCTとは何か?細菌感染とどう結びつくのか
PCT、すなわちプロカルシトニンは、体の別の反応として作られるタンパク質の一種。細菌感染が強くなると体のさまざまな組織でPCTが作られ、血液中のPCT濃度が上昇します。ウイルス感染の場合はPCTの上昇が控えめか、ほとんど上がらないことが多いのが特徴です。PCTが高いほど“細菌が関与している可能性が高い”と判断され、抗生物質を使うべきかどうかの判断材料になります。PCTは発生から数時間で上昇し、感染が進むほど高値を取りやすくなります。治療の途中でPCTの値が下がれば抗菌薬を減量・中止する判断材料にも使われることがあります。ただしPCTも完璧な指標ではなく、免疫力が弱い人や一部の炎症性疾患、外傷などでも値が変動することがあります。臨床現場ではCRPとPCTをセットで見て、総合的に判断するのが基本です。
CRPとPCTの違いを日常の場面でどう使い分けるか
現場では、CRPとPCTの違いを“炎症の有無と広がり”と“感染の性質”に分けて考えるとわかりやすいです。例えば発熱があり、喉の痛みや咳があるとします。このときCRPが高くてもPCTが低い場合、風邪のようなウイルス性の炎症である可能性が高いかもしれません。反対にPCTが高めでCRPも高い場合は、細菌感染が絡んでいる可能性が高く、抗菌薬の適切な使用を考える場面が増えます。医師はこれらの値だけで判断せず、患者さんの症状、検査結果、画像診断、経過観察などを総合的に組み合わせます。また、PCTは抗菌薬の開始・継続・終了の判断材料として使われる場面が多く、抗菌薬を必要最小限に抑える助けにもなります。つまりCRPは“炎症の総量”を教え、PCTは“細菌感染の可能性と重症度”を教える、役割の違いを理解して医師の判断をサポートするということです。これらの指標は万能ではありませんが、適切に用いれば病気の早期発見と適切な治療選択に役立ちます。病気のとき、検査結果を恐れるのではなく、経過観察と医師との対話で不安を減らしましょう。
表で見るCRPとPCTの比較
CRPとPCTの話題を友だちと雑談してみると、CRPは“体の炎症サインの広報担当”みたいで、PCTは“細菌攻撃の警報システム”みたいだね。CRPは風邪や怪我でも上がることがあり、感染の種類を必ず教えてくれない。ただ、PCTは細菌感染が関与している場合に反応しやすく、抗生物質を使うべきかどうかの判断にも役立つ。二つを同時に見ると病気の原因がわかりやすく、治療の適切さを見極めやすくなる。





















