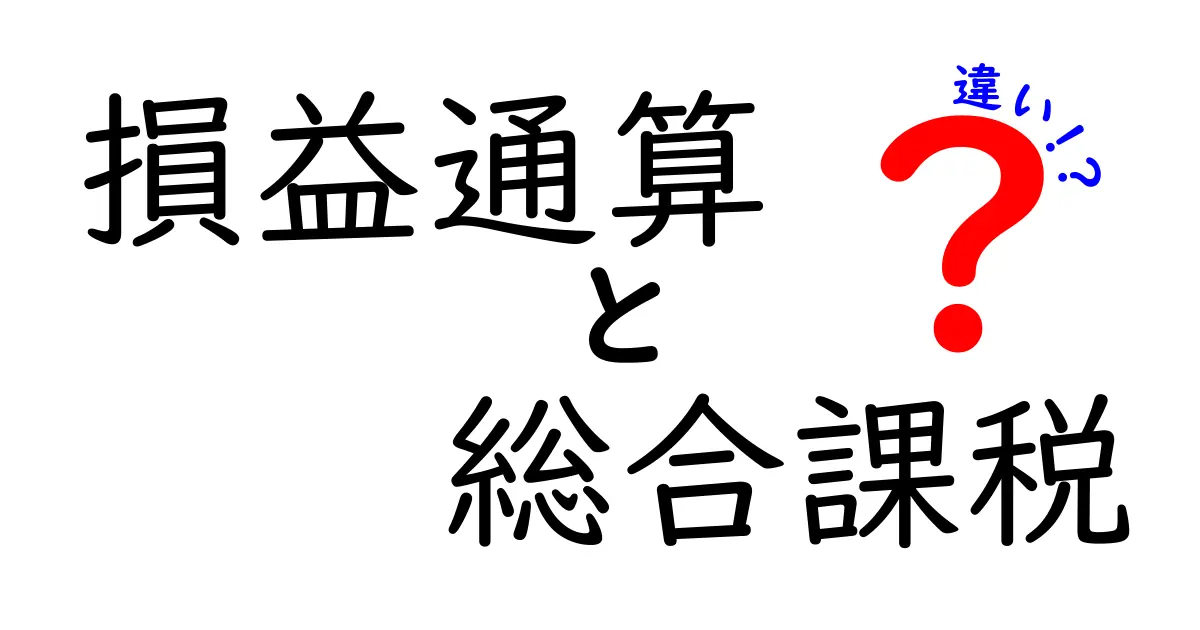

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
損益通算とは何か?基本をわかりやすく解説します
税金の計算に関して「損益通算(そんえきつうさん)」という言葉を耳にしたことがある人も多いでしょう。損益通算とは、簡単に言うと、ある種類の所得で損失が出た場合に、その損失を他の所得から差し引いて、税金の計算をする方法です。
例えば、株式投資で損をした場合、給与所得や事業所得など他の所得と合算して計算し、総所得金額を減らすことができることが損益通算です。これは節税に役立つ非常に便利な制度ですが、損益通算には対象となる所得の種類に制限があり、すべての所得が対象になるわけではありません。
また、損益通算を活用すると税金の負担が軽くなるため、投資家や副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)をしている人にとっては重要なポイントとなります。損益通算を理解することは、所得税の節税対策に欠かせません。
次に、損益通算が適用できる所得の種類や条件について詳しく見ていきましょう。
損益通算ができる所得とできない所得
| 損益通算ができる所得 | 損益通算ができない所得 | |
|---|---|---|
| ・株式や投資信託の譲渡所得 ・先物取引などの差金決済取引の所得 ・不動産所得での損失の一部(条件あり) | ・給与所得 ・一時所得 ・配当所得(一部条件あり) ・年金などの雑所得 |
| 項目 | 損益通算 | 総合課税 |
|---|---|---|
| 意味 | 損失と利益を相殺する制度 | 所得を合算して税率を決定する方法 |
| 対象 | 一部の所得間で利用可能 | 給与所得、事業所得、配当所得など幅広い |
| 目的 | 税負担の軽減 | 所得税の計算基準を作る |
このように、それぞれ役割が違いますが、税金を適切に計算するために互いに連携している仕組みなのです。
最後に、実際の税金計算の流れのイメージを解説します。
実際の税金計算での損益通算と総合課税の流れ
税金の計算をイメージすると、まず損益通算を行い、所得ごとの損失と利益を相殺して課税対象の所得金額を算出します。
その後、損益通算によって調整された所得を含めて、所有する所得をすべて合算し総合課税によって課税所得を計算します。
この課税所得に対して所得税の累進税率が適用されるため、税金が決定されます。
この流れを理解すると、税金を計算するときにどのような仕組みで数字が導かれているかがよくわかります。投資や副業をしている人は、特に損益通算を活用すれば節税効果が期待できるので積極的に知識を深めましょう。
- ① 損益通算で損失を差し引く
- ② 所得をすべて合算する(総合課税)
- ③ 税率をかけて所得税を計算する
これを理解することが所得税の仕組みを使いこなす第一歩です。
今回の記事で「損益通算」と「総合課税」の違いと関係性がよく分かったのではないでしょうか?
税金は難しく感じますが、一つずつ意味を理解していくと、意外とシンプルです。今後の税金対策にぜひ役立ててくださいね。
みなさん、損益通算の知識はありますか?実は、損益通算をうまく活用すると、株式投資や不動産投資での損失を他の所得と相殺して税金を減らせるんです。例えば株で損した分を給料から差し引けるので、税金が軽くなるんですよ。株の利益だけでなく損失も翌年に繰り越せる仕組みがあって、この繰越控除を活用するともっと節税効果が期待できます。投資を始めるなら、損益通算の知識はぜひ押さえておきたいですね!
前の記事: « 課税免除と非課税の違いとは?税金の基本がスッキリ分かる解説





















