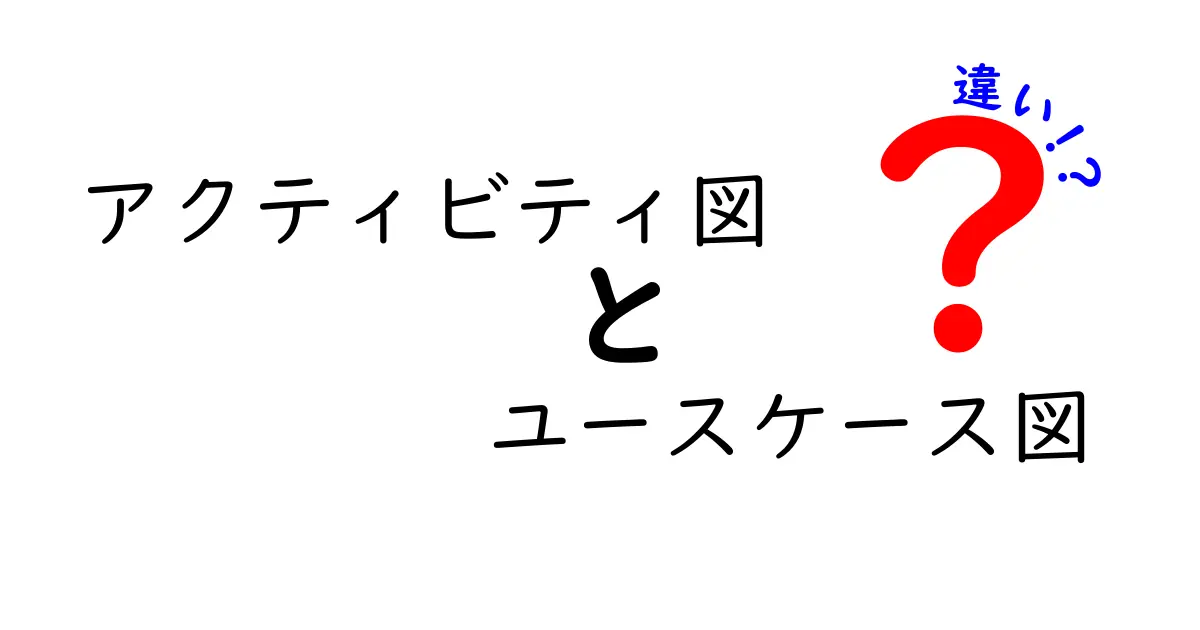

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
アクティビティ図とユースケース図は、ソフトウェア開発や要件整理でよく使われる図ですが、役割や表現するものが異なります。アクティビティ図は「処理の流れ」や「動的な動作の順序」を描くための道具で、実際にどの順番で作業が進むのか、どの条件で分岐するのかを分かりやすく示します。一方でユースケース図は「誰が何を使えるか」という、システムの境界と外部の関係を示す静的な視点の図です。これらを区別して使うことで、要件定義の時点から設計・実装までの理解を深めやすくなります。
本記事では、この二つの違いを基礎から丁寧に解説し、なぜ区別が大事なのか、そして実務でどう活かせばよいのかを中学生にも伝わるように分かりやすく説明します。
まず前提として覚えておきたいのは、アクティビティ図は「動的な処理の流れを表す図」であるのに対し、ユースケース図は「誰が何を使うのかという機能と人物・役割の関係を表す図」である、という点です。これらを混同してしまうと、要件が不明確になったり、開発チーム内で話がずれてしまったりします。図を使って説明するときには、まずこの二つの視点の違いを意識することが第一歩になります。
また、UMLの他の図と組み合わせると、要件から設計へと自然につながる見取り図を作ることができます。例えば、アクティビティ図で業務の流れを明確化し、ユースケース図でシステムの機能と利用者を整理する、という流れです。これができると、後の開発フェーズで役割分担や作業の順序づけがスムーズになり、コミュニケーションの齟齬を減らすことができます。
この章を読んで、まずは「動的な流れと静的な関係」という二つの観点を自分の言葉で言い換えられるようにしておきましょう。アクティビティ図とユースケース図の両方を使い分ける練習を重ねると、要件定義の段階での考え方がまとまり、設計やテストの段階でも効果的なツールとして役立つようになります。
アクティビティ図とユースケース図の違いを理解する
このセクションでは、二つの図の違いを「目的」「主な表現」「表現する情報」「作成の場面」という観点からじっくり比べて説明します。まずは両図の基本的な役割を再確認し、それから具体的な例でどう使い分けるかを見ていきましょう。
まずアクティビティ図は、業務プロセスやシナリオの実行順序を示す「動的な流れ」の可視化に適しています。判断ポイント、並列処理、分岐の条件、ループ、待ち時間など、処理がどう動くかを直感的に追える点が特徴です。一方、ユースケース図は、システムが提供する機能と、それを利用する人や外部システムとの関係を整理する「機能と境界の関係性」を描くのに向いています。ここではアクターとユースケースの組み合わせ、そしてそれらの関連を線で結ぶ形が基本となります。
つまり、アクティビティ図は“どう動くか”を描く地図であり、ユースケース図は“何を使えるか”を描く地図だと覚えると理解しやすいです。どちらを使うかは、要件の段階で何を明らかにしたいかによって決まります。要件定義の初期段階ではユースケース図で機能の範囲と関係を整理し、設計フェーズに入ってからはアクティビティ図で実際の処理の流れを具体化する、という順序もよく用いられます。
以下のポイントを意識すると、違いが頭に入りやすくなります。
目的の違い:アクティビティ図は処理の流れを明確化すること、ユースケース図は機能と利用者の関係を整理すること。
対象の違い:アクティビティ図は業務やシステム内の手順を対象に、ユースケース図はシステムの外部との境界と機能を対象にする。
表現の仕方:アクティビティ図は活動や分岐、並列などの動的要素をつないで描く。ユースケース図はアクターとユースケースを結ぶ関連線で構成する。
これらを踏まえると、図を描くときに迷う場面が減ります。
また、実務ではこの二つを同時に使うことで、要件がどのように実装に落ちるのかをチーム全体で共有しやすくなります。
以下の表は、両図の要点を要約したものです。比較表を見れば、どの場面でどちらを使うべきかが直感的に分かるようになるはずです。
表を読み解くときも、誤解を避けるために「動的 vs 静的」「流れの表現 vs 機能の表現」という二つの軸を思い出すとよいでしょう。
主な特徴の比較
この小見出しの下にも、要点を深掘りして説明します。具体的な定義、要素、表現方法、適した場面、作成の順序などを、私たちが現場で直面するケースを想定して語ります。
まずは簡潔な違いを押さえた上で、後半の表と具体例で理解をさらに深めましょう。
この表を見れば、どちらの図がどんな情報を扱うのか、どの段階で作成するべきかがはっきり理解できます。
次のセクションでは、実務での使い分けのコツと具体例を紹介します。
使いどころの例
実務での使い分けは、要件定義の初期と設計の段階での目的の違いを意識することがコツです。
要件定義の段階では、ユースケース図を使って「何ができるのか」「誰が関与するのか」を洗い出します。これにより、機能の外部からの視点を逃さず、関係者の認識をそろえることができます。
設計の段階では、アクティビティ図を使って「処理の具体的な順序」を可視化します。ここでは分岐条件や同時実行、待機状態など、実装時に必要な動作を細かく描くことが求められます。
また、これら二つの図を併用すると、要件がどのように実装に落ちていくのかをチーム全体で共有しやすくなります。現場では、まずユースケース図で全体像を固め、次にアクティビティ図で流れを詳細化するのが、混乱を避ける王道の進め方です。
まとめ
本記事ではアクティビティ図とユースケース図の違いと使い分けのポイントを、基礎から丁寧に解説しました。
要点を箇条書きにすると、
・アクティビティ図は動的な処理の流れを表す図であること、
・ユースケース図は機能と境界・利用者の関係を整理する図であること、
・実務では要件定義と設計の二段階で使い分けるのが有効であること、が主なポイントです。
この二つを組み合わせて使うことで、開発チーム全体の理解が深まり、要件の見落としや認識のズレを減らす効果が期待できます。図の作成を通じて、誰が・何を・どう使えるのかを明確に描く訓練を続けていきましょう。
ねえ、アクティビティ図って、日常の“手順の流れ”を描く迷路みたいなものなんだ。例えば学校の給食の準備を思い浮かべてみて。配膳係が運ぶ順番、皿が回ってくるタイミング、分岐する場面(おかわりOKかどうか)などを線と記号で表す。実は、僕らが授業で使う時間割の組み立てにも同じ発想が活きていて、順番に処理を並べることが大切。ユースケース図はそれと少し別の視点で、誰が何を使えるのかという“入口と機能”の関係を示す。つまり、アクティビティ図が“どう動くか”を描く地図だとしたら、ユースケース図は“誰が何を使えるか”という地図。二つを組み合わせると、学校のイベントの計画や部活の運営計画を立てるときにも役立つんだ。
前の記事: « 事業部長と本部長の違いを徹底解説:役割の境界線をわかりやすく





















