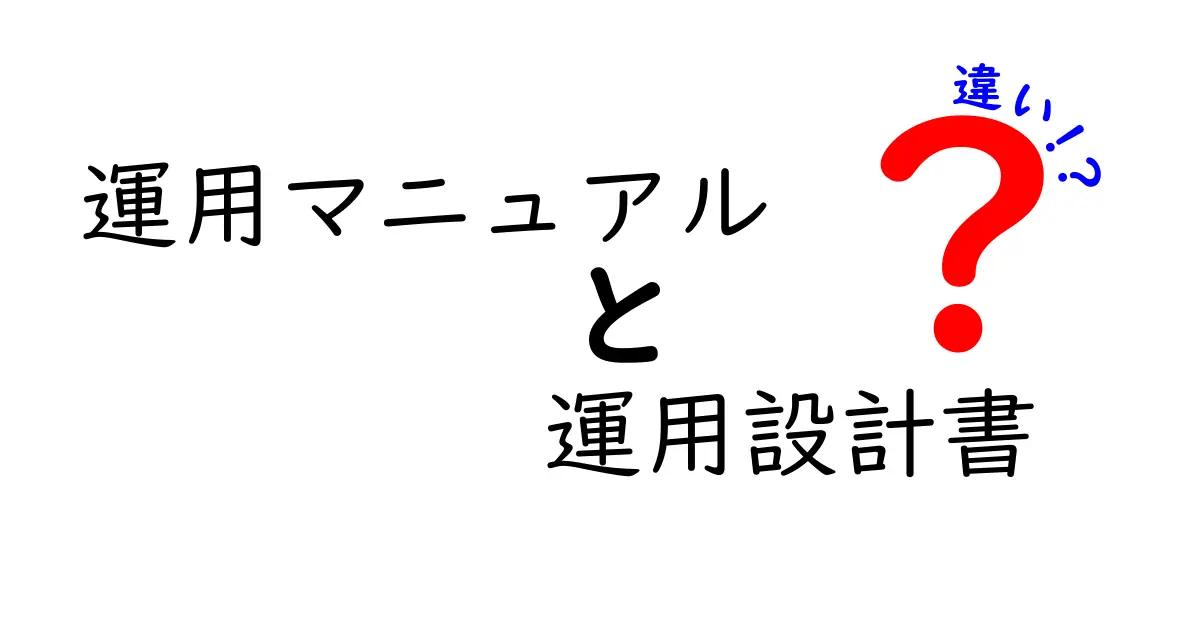

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
運用マニュアルと運用設計書の違いを理解するための完全ガイド
現場の運用を円滑に回すためには、作るべき文書の種類を混同しないことが大切です。この記事では「運用マニュアル」と「運用設計書」の違いを、誰が読んでどう使うべきかという視点から分かりやすく解説します。前提として、運用マニュアルは現場の作業手順を標準化した実務ガイドであり、運用設計書はサービスやシステムの運用観点を定義する仕様書です。以下の説明を読んで、あなたの組織でどのように使い分けるべきかを考えてください。
それぞれの文書がもつ役割を理解することで、トラブル時の対応が速くなり、日々の運用が安定します。
長文ですが、一度頭の中に図を描くと、混乱せずに使い分けができるようになります。
運用マニュアルとは何か
運用マニュアルは、現場の作業者が日常的に行う運用手順を具体的に書き下した「実務の手引き」です。たとえばサーバーの再起動手順、障害時のエスカレーションフロー、定期的なバックアップの実施日、担当者、期限、チェックリストの形式で構成されます。
このマニュアルの目的は、誰が読んでも同じ作業を同じ手順で再現できるようにすることです。
読者は現場のオペレーター、サポート担当、運用監視の担当者など、現場で作業を実行する人たちです。
重要なポイントは、実際の手順が最新の運用ルールと整合していることと、現場の負荷を考慮した分かりやすさです。また、運用マニュアルは変更時に頻繁に更新され、履歴管理が求められます。
読みやすさの工夫として、手順ごとに番号を振り、図解や写真を挿入するのも有効です。
運用設計書とは何か
運用設計書は、サービスやシステムを“どう運用するか”を決めた設計文書です。ここには監視の閾値、SLA(サービスレベルアグリーメント)、障害発生時の対応方針、運用対象となる機器やソフトウェアの構成、運用の自動化方針、リスク評価、バックアップ方針、リカバリ手順などが含まれます。
読み手はIT部門の設計担当者、運用設計責任者、監視・自動化を担当するエンジニア、そして将来的な拡張を見据えるマネージャーです。
運用設計書の狙いは、技術的な仕様と運用上の要件を結びつけ、将来の変更にも強い骨組みを作ること。現場の手順だけでなく、システムの運用性能を左右する根幹を記します。
違いのポイントと実務での使い分け
ここまでで、運用マニュアルと運用設計書の役割がだいぶ分かってきたはずです。では、現場でどう使い分ければよいのでしょうか。
まず目的の違いを整理します。運用マニュアルは“今この瞬間の作業をどうやるか”を示す実務ガイド。対して運用設計書は“将来どう運用するべきか”の設計思想と前提条件を示す仕様書です。
次に対象者の違いです。前者は現場の作業者が主な読者、後者は設計者・マネージャー・運用自動化を担当するエンジニアが中心になります。
内容の違いは、前者が手順・チェックリスト・エスカレーションといった“実務の細かさ”に焦点を当てるのに対して、後者は監視項目・閾値・復旧戦略・リスクや依存関係といった“設計思想の表現”を重視することです。
最後に更新の頻度と履歴の扱いの違いです。運用マニュアルは日常的に更新され、現場の状況変化をすぐ反映します。一方、運用設計書は長期の設計方針を示すため、変更は慎重に管理され、変更履歴と影響範囲の評価が重要です。
このように、現場の実務と設計思想という二つの側面をしっかり分けて考えることで、両者を相互補完的に活用できます。
実務と設計の連携を強化するためには、定期的なレビューと、変更時の通知・同意のプロセスを整えることが有効です。
この二つの文書を適切に使い分け、連携させることで、トラブル時の対応が速くなり、平常時の運用も安定します。
また、両者の間で情報を行き来させるための共通の用語集を作成しておくと、誤解が減り、更新作業もスムーズになります。
ねえ、運用設計書って未来の地図みたいだよね。現場は毎日動いているけど、何かあったらどうするかを“設計”として決めておく。だから、運用設計書は『こう動くべきだ』という約束事を形にしたもの。私たちが例えばサーバーが落ちた時の対応を考えるとき、運用マニュアルだけだと手順はあるけど“なぜこの手順なのか”の理由まで薄くなる。そこで運用設計書が存在する。差が明確になる。結局、現場の人は手順と理由を両方持つべきで、設計書は理由の部分、マニュアルは実践の部分と覚えると良い。





















