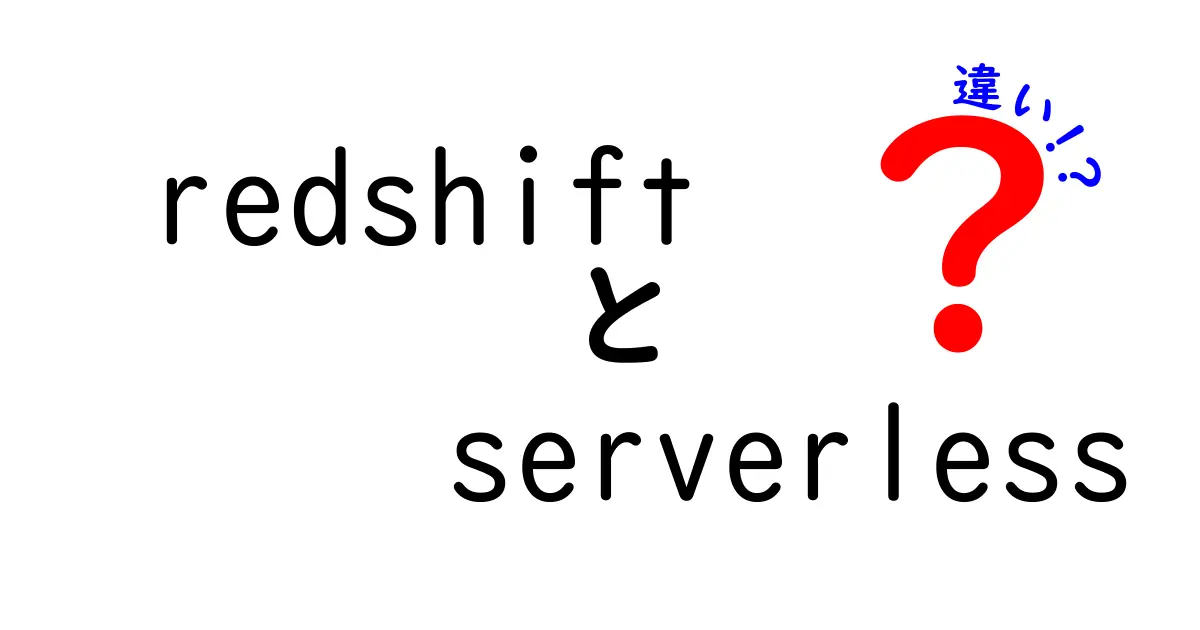

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
Redshift Serverlessと従来Redshiftの違いを徹底解説|クリックしたくなる比較ガイド
このガイドは AWS のデータウェアハウス Redshift の「Serverless」と「従来のクラスタ運用」の違いを、難しく感じずに理解できるように作っています。
Redshift は大容量データの分析に強いサービスですが、従来版は事前にクラスタの規模を決めて運用します。つまり クラスタのサイズを予測して用意する必要があり、需要が増えるときにはノードを追加して拡張します。これに対して Serverless はクエリが来るたびに必要なリソースを割り当て、実行が終われば不要なリソースを解放します。
さらに Serverless には自動的なスケーリング機能や実行中のクエリ数に応じた同時実行制御が組み込まれており、コストを無駄にせず、安定したレスポンスを保ちやすい設計になっています。
ただし従来版には長所もあり、予測可能な負荷が続く大規模なデータ分析や、複雑な ETL ジョブを長時間走らせるケースでは安定したパフォーマンスを得やすい場面もあります。
本記事では、それぞれの特徴を実務の場面に落とし込み、どのようなケースでどちらを選ぶと良いかを具体的に解説します。
背景と基本的な違い
ここではまず背景と基本的な仕組みの違いを整理します。従来の Redshift クラスタは 固定サイズのリソースセットとして動作し、事前にノード数とタイプを決めて運用します。需要が増えればノードを追加して拡張しますが、稼働中の変更には計画と手動の作業が伴います。これが運用の負担やコスト管理の難しさにつながることがあり、特に変動の大きいデータ分析では影響が出やすいです。これに対して Redshift Serverless は クエリ単位の自動割り当てを行い、使った分だけ料金が発生します。
サーバーレスの利点は 容量の事前確保を気にしなくてよい点と、需要が急増する場面での適応性です。
使い分けの具体的ケース
実務での使い分けは、ワークロードの性質をよく見ることから始まります。予測可能な長期的負荷があるなら従来のクラスタ運用が安定する場面があり、コストをギリギリまで抑えたい場合や変化が大きい日や週には Serverless が有利です。例えば毎日同じ時間に大量のデータを集計するBIダッシュボードなら従来版、午後に急に分析リクエストが集中するマーケティングイベントの分析なら Serverless が適しています。
また開発チームの規模が小さく、運用リソースを削減したい場合は Serverless の方が管理負担を減らせます。逆に複雑なジョブチェーンを長時間走らせる場合はカスタムのチューニングや特定ノードの性能を活かせる従来の方が向いていることもあります。
価格と運用の観点
最後にコストと運用の観点を整理します。従来版はクラスタのサイズと利用時間に応じて料金が発生するため、総コストは利用パターンに強く影響されます。常時運用する固定コストを許容できる大規模分析には向いていますが、変動の多い workloads にはコスト管理が難しくなることがあります。対して Serverless は 使った分だけ払う料金体系で、アイドル時間が少ないほど有利です。ただしクエリの最適化が十分でないと、思ったより高額になるケースもあるため、クエリの実行計画を理解することが重要です。運用の観点では Serverless の自動停止・再起動・自動スケーリング機能が強力な味方になりますが、特定のワークロードでは手動での微調整が必要になる場合もあります。
| 特徴 | 従来 Redshift | Redshift Serverless |
|---|---|---|
| 料金モデル | 固定クラスタ料金(ノード数に依存) | 使用量課金・自動停止/起動 |
| スケーリング | 固定サイズのクラスタが対象 | クエリ負荷に合わせ自動スケール |
| 運用手間 | ノード追加・削除の作業が発生 | 基本的に自動化・管理負担低 |
| 適したワークロード | 一定の予測が立つ大規模分析 | 変動するワークロード・不定期クエリ |
昨日、友だちと図書館でこの話題を雑談していて、Redshift Serverlessと従来 Redshift の違いについて深く語り合った。Serverless の自動化と料金の柔軟性は魅力的だが、現場には依然として安定感のある従来版を好む人もいる。結局のところ、データ分析の現場ではワークロードの性質を見極め、使い分ける判断を身につけることが大事だと私は感じた。少しの工夫でコストを抑えつつ、必要なときに迅速に分析を進められる、それが今回のポイントだった。





















