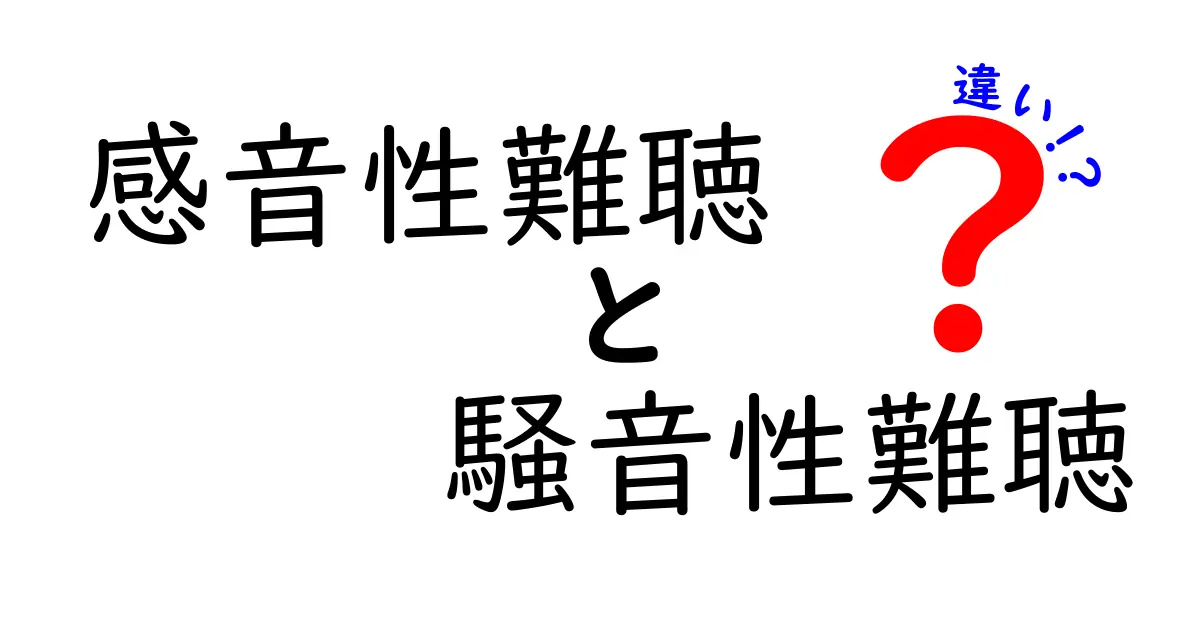

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
感音性難聴と騒音性難聴の違いを完全解説|原因・症状・治療・予防を中学生にも分かる図解付き
このテーマを学ぶと、耳のしくみが少し見えてきます。耳は外耳・中耳・内耳の三層構造で音を拾い、聴覚神経を介して脳に音情報を伝える仕組みになっています。感音性難聴は主に内耳の「聴覚細胞」や聴神経の働きが傷つくことで起こりやすく、騒音性難聴は長時間や急激な大きな音刺激が耳の機械部分や内耳を損傷して生じます。症状は類似していることもあり、最初は小さい音が聞こえづらい、耳鳴りがする、聞こえが遠い・こもって聞こえるといった感覚です。検査では耳の奥の構造が正常かを調べる聴力検査(オージオメトリ)と、鼓膜の動きを見る検査が行われます。治療は原因により異なり、感音性難聴は補聴器や人工内耳、騒音性難聴は早期の音刺激の停止と予防が鍵になります。学校や部活動の現場では、耳が痛い、難聴の疑いがあると感じたらすぐに保健室や耳鼻科を受診することが大切です。早期対応ほど回復の見通しがよく、将来のコミュニケーション能力にも影響します。
ここからは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
感音性難聴とは何か
感音性難聴は、耳の内側の問題で起こるタイプです。内耳の蝸牛(かいろう)にある聴覚細胞や聴神経の働きが傷つくと、音が小さく聞こえたり、音の質が変わったりします。原因には加齢、薬の影響、感染症、遺伝的な要因、時には強い音の長時間曝露などがあります。特徴は内耳側のダメージが中心で、外耳・中耳には問題がほとんどないことが多い点です。検査としては聴力検査が中心で、周囲の音の聴こえ方を詳しく測定します。治療は個人差が大きく、補聴器や人工内耳の適用が検討され、聴覚機能の回復よりも聴こえの改善を目指します。早期に対応するほど、生活の質を保つチャンスが高まります。生活面では、テレビの音量を大きくし過ぎない、会話の際には視覚情報(口の動き)を頼る、などの日常的な工夫が有効です。
騒音性難聴とは何か
騒音性難聴は、外耳・中耳・内耳のいずれか、あるいは複数の部位が長時間または大きな音刺激によって損傷を受けるタイプです。工事現場、音楽イベント、楽器演奏、携帯音楽プレーヤーの高音など、日常の生活場面にも起こり得ます。長く続く音刺激は内耳の毛細胞を傷つけ、回復が難しくなることが多い点が特徴です。急性で大きな音を浴びた後に聴こえが歪む、耳鳴りが続く、しばらく音が遠く感じるといった症状が現れることがあります。予防には耳栓やイヤーマフの使用、音楽の聴き方を見直す、休憩を挟むなどの工夫が有効です。早期の対応と予防が最大の武器であり、生活習慣を少し変えるだけで聴力のダメージを大きく減らせます。
違いを理解するポイント
感音性難聴と騒音性難聴の違いを押さえるためのポイントを、わかりやすく整理します。
原因の場所:感音性難聴は内耳・聴神経の問題が中心、騒音性難聴は音刺激による外耳・中耳・内耳の総合的なダメージが原因になることが多い。
うつろい方の特徴:感音性難聴は高周波から難聴になる傾向があり、音のこもりや耳鳴りを伴うことが多い。騒音性難聴は長期間の露出後に徐々に悪化するか、急性の音で一時的に悪化した後も回復が不確実になることがある。
検査と治療の方向性:感音性難聴は補聴器・人工内耳などの聴覚補助が中心、騒音性難聴は予防・予防教育と早期対処が鍵。
このようなポイントを理解することで、日常生活の中での耳の健康管理が具体的になります。
予防と対策
予防の基本は「音の環境を守ること」です。大きな音を長時間聴かない、耳栓やイヤーマフを適切に使う、音楽を聴く際には音量を適切な範囲に抑える、休憩を挟んで耳を休ませる、学校や部活動での騒音対策を講じる、などの対策を日常に取り入れましょう。もし聴こえに不安を感じたら、早めに耳鼻科を受診して聴力検査を受けることが大切です。治療可能性は年齢や原因によって異なりますが、早期検査と早期対処が最も重要です。
表で見る代表的な違い(簡易比較)
以上のポイントを押さえると、難聴の種類や対処法がぐっと身近になります。
友だちと放課後に話していたら、彼が感音性難聴について興味深い話をしてくれた。彼は「耳の内側の聴覚細胞が傷つくと音がこもって聞こえるんだ」と言い、私は「じゃあ音楽の部活の後は耳を守る工夫が必要だね」と返した。彼は最近の授業で聴力検査の話を思い出し、<強>早期発見と予防の大切さを痛感していると言っていた。部活動の練習中、爆音の機材を使う場面もあり、私は適切な耳栓の使い方を一緒に調べることにした。雑談の中で、難聴は「大人だけの問題」ではなく、成長期の子どもたちが自分自身の耳を守る意識を育てる良い機会だと気づかされた。これからも友だちと知識を共有し、耳の健康を守る習慣を一緒に作っていきたい。





















