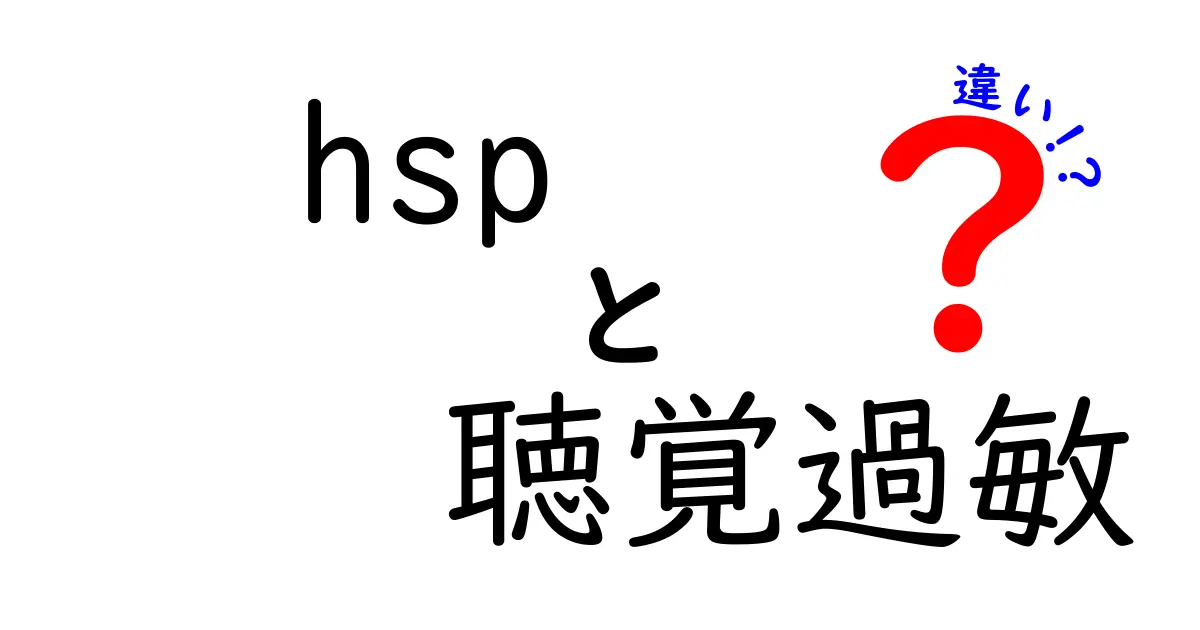

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:HSPと聴覚過敏の違いを正しく理解する
現代の学校や家庭で「HSP」と「聴覚過敏」という言葉を耳にすることが増えました。似ているように感じる人もいますが、実は意味や背景が違います。この違いを知ることは、自分や周りの人の気持ちを理解し、適切に距離感をとるために重要です。HSPは「生まれつき感じ方が敏感な性格傾向」を指し、必ずしも病気ではありません。一方、聴覚過敏は音の刺激に対して過剰に反応して苦痛を感じる状態で、場合によっては医学的な評価が必要になることもあります。
この章では、両方の基本を押さえ、同じ言葉として混同しないコツを紹介します。気づきの第一歩として、自分の感じ方を言語化する習慣をつくるのがおすすめです。話し方や場の選び方、休憩の取り方など、生活の中でできる工夫を後半で具体的にまとめます。
さっそく特徴の違いを見ていきましょう。読んでいるあなた自身や身近な人を思い浮かべながら、無理なく読める言葉で解説します。
HSPとは何か?
HSPは「Highly Sensitive Person」の頭文字をとった日本語訳で、高感受性の人を指します。感覚や情報を処理する脳の傾向が、一般の人より敏感であるため、音・匂い・光・人の気持ちなど、周囲の刺激を強く受け取ります。しかしその敏感さは悪い面ばかりではなく、創造性や共感力、観察力が高まるという利点にもつながります。HSPの人は小さな変化にも気づきやすく、他者の心情を読み取る力が強い反面、過度な刺激で疲れやすい、眠れない、頭痛が起きやすいなどの疲労サインを感じやすいことがあります。
大事なのは「自分のペースを守ること」と「不要な刺激を減らす工夫をすること」です。学校や部活、家庭での環境調整が重要で、他人と比べる必要はありません。自分の感受性を武器にする考え方を持つことで、HSPは日常生活の中で大きな力を発揮します。
聴覚過敏とは何か?
聴覚過敏は、音に対する感受性が過剰に働く状態を指します。音の大きさだけでなく、音の質や編集された雑音の混じり方、会話のリズムなど細かな音の組み合わせにも敏感に反応します。たとえば教室のざわめき、廊下のドアの開閉音、ロッカーのきしみ音などが不快に感じられることが多いのです。聴覚過敏があると、日常の場面がストレス源になり、集中力が落ちたり、緊張が続いたり、体調を崩しやすくなることがあります。原因は多岐にわたり、聴覚処理の個人差、睡眠不足、心身の疲労、ストレス、あるいは発達障害の一部のケースと関連することもあります。適切な対処には医師や専門家の評価が役立つこともありますが、身近な工夫としては、音を遮る環境づくり、耳栓の活用、休憩の取り方、音源を事前に調整しておくことなどがあります。
自分の聴覚過敏を「敵」ではなく「自分の特性の一部」として理解することが、対策を続けやすくします。自分に合う対処法を探すことが大切です。
違いのポイントと日常での向き合い方
HSPと聴覚過敏は「感覚の強さ」が特徴的ですが、原因や現れる状況、対処法は異なります。HSPは性格的傾向の一部であり、音以外の感覚にも影響を受けやすいのが特徴です。対して聴覚過敏は音に特化した感覚過敏で、生活の中の音が苦痛や不安の原因になりやすい点が大きな違いです。ここを混同せず、それぞれの状態に応じた対策を取ることが大切です。
まずは自分の感じ方を把握するセルフチェックを習慣化しましょう。周囲に配慮を求める練習や、無理をしない時間配分、そして休憩をしっかりとることが基本です。次に、環境の工夫です。教室や自宅での音環境を見直し、静かな場所を選ぶ、雑音を和らげる工夫をする、耳栓やノイズキャンセル機器を活用するなどの具体的な手段を取り入れます。
また、対人関係の学びも欠かせません。感受性が高いことを伝え、協力を得るコミュニケーションを心がけると、誤解を減らせます。最後に、必要なら専門家の力を借りることをためらわないでください。専門家の診断や指導は、長く続く困難を軽くしてくれます。
| 特徴 | HSPの特徴 | 聴覚過敏の特徴 |
|---|---|---|
| 感覚の強さ | 日常の刺激を過剰に受け取り、疲労しやすい | 音の質やリズムにも敏感で、不快感が強い |
| 日常の影響 | 人混みや長時間の作業で眠気や頭痛、感情の乱れが起きやすい | 授業中の音、通学路の騒音、家庭の生活音で集中困難 |
| 対処法の基本 | 自分のペースを守る、静かな環境を作る、共感できる人の理解を得る | 音源のコントロール、休憩の取り方、耳を守る工夫 |
まとめとおすすめの実践例
本記事では、HSPと聴覚過敏の違いと日常での向き合い方を解説しました。ポイントは「自分を知り、無理をしすぎない工夫を取り入れること」です。教室や家庭での環境調整、周囲への伝え方、そして必要に応じた専門家のサポートを活用することで、ストレスを減らし、心身の健康を保つことができます。自分の感じ方を大切にし、適切な休憩と適切な音環境を整える習慣を身につけてください。
小さな変化の積み重ねが、長い目で見て大きな安心につながります。
今日は友人との雑談の中で、HSPと聴覚過敏の話題が出ました。私の結論は“違いを知ることが安心の第一歩”です。HSPは生まれつき感じ方が敏感な性格の傾向であり、音だけでなく光、匂い、人の気持ちにも影響を受けやすい。ただ聴覚過敏は音の刺激に対して強い反応を起こしやすい状態で、生活の中で具体的な工夫が必要になることが多い。私たちはこの2つを混同せず、それぞれに合った休憩の取り方や音環境の整え方を実践していくべきだ、という話をしました。





















