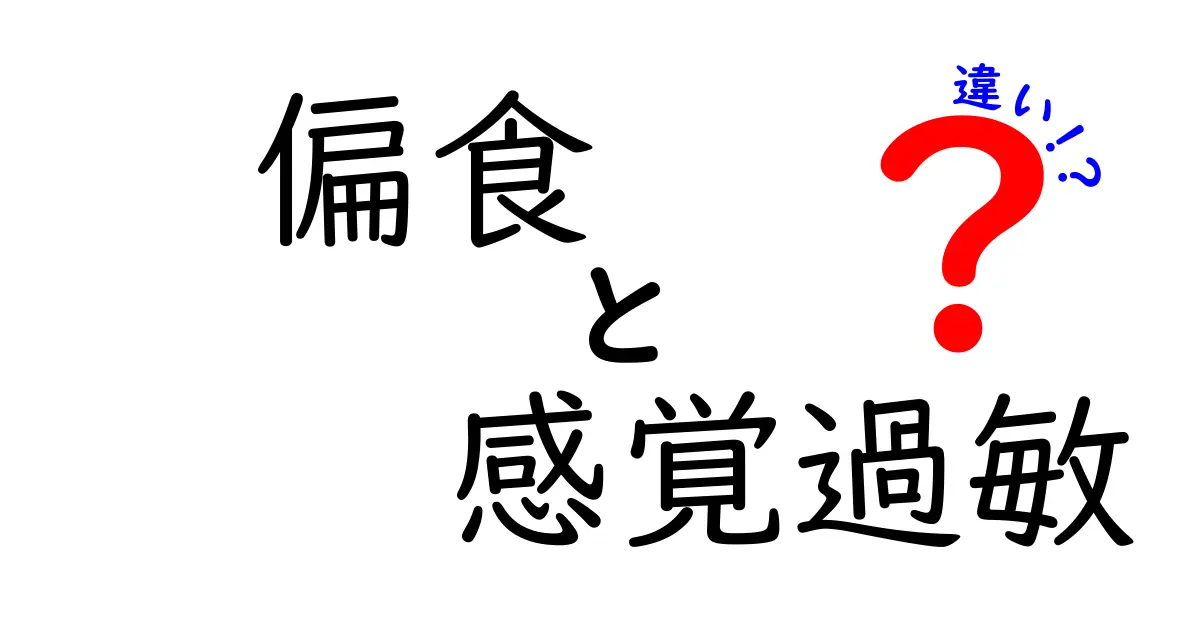

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
偏食とは何か?その原因と特徴について
偏食とは、食べ物の好き嫌いが強く、特定の食品ばかり食べたり、逆に特定の食品をまったく食べなかったりすることを言います。
偏食の主な特徴としては、好きな食べ物に偏ってしまうため、栄養バランスが偏りやすいことが挙げられます。例えば、肉ばかり食べて野菜をほとんど食べないというケースが典型的です。
偏食の原因は様々で、子どもの味覚の発達段階や、食べ物の見た目や食感への好き嫌い、心の問題が関係することもあります。時には、環境や習慣の影響で特定の食べ物に偏ることもあります。
偏食は成長に影響を与える恐れがあるため、周囲の人が上手に理解し、栄養バランスを整える工夫が必要です。
感覚過敏とは?食べ物との関係や生活への影響
感覚過敏は、音や光、触覚、味覚など、五感が普通の人よりも敏感に反応してしまう状態です。
食べ物に関する感覚過敏では、特定の味やにおい、食感が強すぎて受け入れにくくなることがあります。このため、感覚過敏の人は特定の食べ物を避けやすく、結果として偏食になってしまうこともあります。
感覚過敏は発達障害の特徴の一つとしても知られており、日常生活でのストレスや疲れの原因になります。適切な対応としては、環境調整や食べやすい食材の選択、専門家の支援が重要です。
偏食と感覚過敏の違いをわかりやすく比較!
この二つは似ているようで実は異なるものです。偏食は食べる物の好みや習慣の問題であるのに対し、感覚過敏は感覚の敏感さによる身体や心の反応が原因です。
以下の表で主な違いをまとめてみました。
| 項目 | 偏食 | 感覚過敏 |
|---|---|---|
| 意味 | 特定の食品を好む、または避ける食習慣 | 感覚が過敏で刺激を強く感じる状態 |
| 主な原因 | 味の好み、習慣、環境 | 神経の過敏性、発達障害など |
| 食事への影響 | 栄養バランスの偏り | 食感や味の刺激による拒否 |
| 対策 | 栄養教育や多様な食体験 | 環境調整、専門支援 |
このように偏食は好き嫌いの問題、感覚過敏は感覚そのものの敏感さに関連しています。ときに感覚過敏が原因で偏食になることがありますが、原因と対策は異なるため見極めが大切です。
感覚過敏の中でも特に食事に関わる味覚過敏は、普通の人が気にしない微妙な味の違いや食感がとても気になってしまいます。
例えば、少し苦みがあるだけでその食べ物を拒否する子供もいます。
感覚過敏は脳の情報処理の仕方が関係しており、単なる好き嫌いとは違うため、無理に食べさせるのは逆効果です。
じっくり慣れさせたり刺激を和らげる方法を探すことが大切なんですよ。
前の記事: « 「接触」と「接近」の違いとは?わかりやすく徹底解説!
次の記事: 内向的と陰キャの違いとは?性格の特徴と誤解を分かりやすく解説! »





















