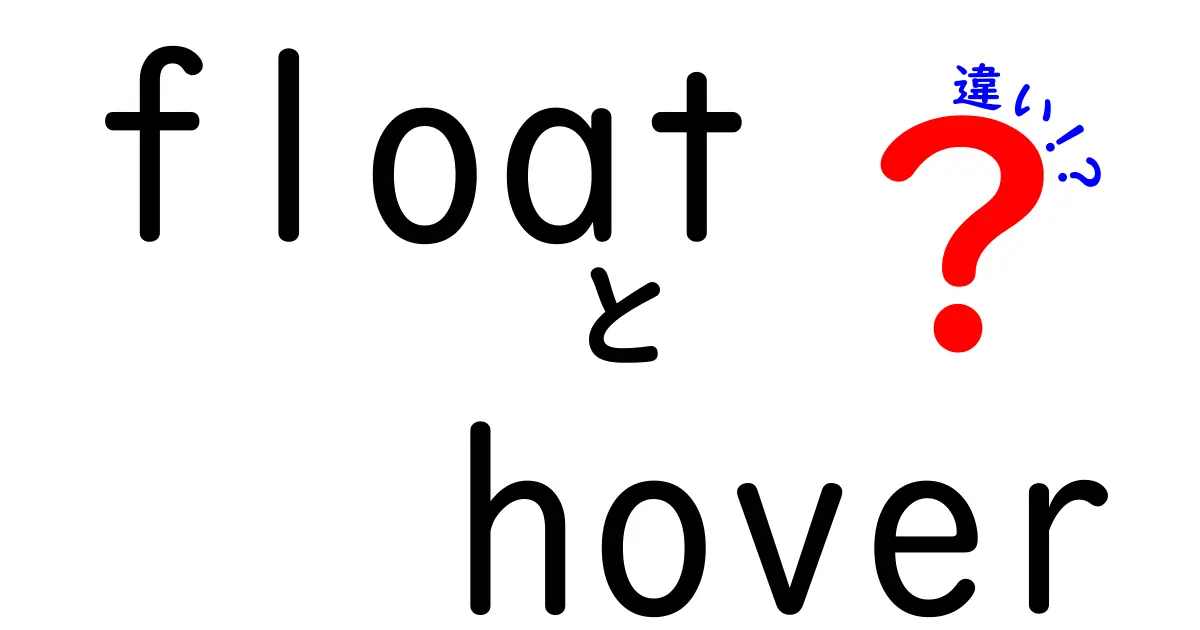

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
floatとhoverの基本を押さえよう
この章では float と hover の基本的な考え方を中学生にも伝わるように丁寧に説明します。まず float は要素を横に寄せるための CSS の仕組みです。通常の文書の流れから外れて左寄せや右寄せをすることで、並んだアイコンやボタンを横並びに整えられます。
ただし float を使うとその周りのレイアウトに影響が出ることがあり、後で「親要素の高さが崩れた」などの現象が起こることもあります。
このため float を使うときはクリアリングの考え方やボックスモデルの理解が必要です。
次に hover についてです。hover はマウスカーソルを対象要素の上に置いたときに見た目を変えるための疑似クラスです。これを使うと色が変わったり、背景が変わったり、境界線が太くなったりします。
インタラクティブな体験を作るには有効ですが、スマホなどのタッチ端末では hover が使えない場合が多い点に注意します。
またアクセシビリティの観点から focus を併用して、キーボード操作でも同じ効果を得られるようにするのが望ましいです。
ここまでの要点は float はレイアウトの配置手段、hover は視覚的な反応の手段 という点です。両者は役割が異なるため、使い分けるとデザインの質が上がります。今後の実践では、実例コードを見ながら自分のサイトの要素がどう動くかを確かめていくことが大切です。
floatの使い方と注意点
float の基本的な使い方は、要素に float: left; または float: right; を指定して、周囲の要素を回り込ませる感じです。テキストは横並びに回り込み、画像は横並びになることが多いです。ここで大切なのは「クリアリング」です。float が残ると、その後のブロックが浮いたまま表示され、見た目の崩れが生じます。クリアを用意する方法として clear: both を適用するか、親要素に overflow: hidden; を与える方法、または clearfix テクニックを使う方法があります。これらの方法を使い分けると、レイアウトが安定します。
実践コードを想像してみましょう。左に画像、右に本文、というパターンなら img { float: left; margin: 0 1em 1em 0; } のように書きます。すると本文は画像の右側を回り込み、段落全体が左寄りに揃います。しかし float だけで終わらせると、親要素の高さが0になる問題が発生することがあります。その場合は前述のクリアリングを使って、次のセクションが正しく表示されるようにします。
float を使うときの注意点は、モバイル表示での崩れや、ネストされた要素の影響です。モバイルでは float を使わずに flexbox や grid に移行する選択肢を検討するのが現代の流れ です。長い文章の横並びよりも、読みやすさを優先する場面が増えています。適切な代替手段を使えば、デザインの自由度を保ちつつ安定したレイアウトを作れます。
hoverの使い方とデザインのポイント
hover の基本は、マウスが載っているときだけ発動する視覚的な反応を作ることです。ボタンの色を変えたり、背景を変えたり、影をつけたりします。
ただし hover はすべての端末で同じように機能するわけではありません。特にスマホは hover が使えないため、 focus-within や :focus を組み合わせてキーボード操作にも対応させるのがポイントです。
デザインのコツとしては、変化量を控えめにすること、アニメーションの継続時間を長くしすぎないこと、そしてアクセシビリティを確保することです。コントラストと視認性を落とさず、操作時のみ目立つ演出を心がけましょう。また、 hover にのみ依存するインターフェイスは、フォーカス時に何も起こらない体験を生むので避けるべきです。
実用的な例として、リスト項目の hover で色を変える、リンクの下線を強調する、ボタンのパディングを変化させる、などがあります。これらは CSS のトランジションを使うと滑らかな体験になります。
モバイルを意識して、 hover を使用する場面とそうでない場面を分ける設計が重要です。
この章のまとめとして、 hover は「視覚的な反応を加える装置」であり、float は「配置を動かす装置」であると覚えておくと混乱を避けられます。実務ではこの二つを組み合わせて、使いやすく美しいページを作ることが目的になります。
ある日のデザイン課で友だちと先生が CSS の話をしていた。float は左のボックスを動かして本文をその横に並べる魔法みたいだ、とは彼の一言。hover はそのボタンに指を置くと色が変わって気づきを与える仕掛け。けれどスマホでは hover が使えない問題もある。私は思う、デザインは手品ではなく道具の組み合わせだと。float の力を過信せずに、flexbox の風を取り入れればもっと安定する。こうして私たちは、使い分けの感覚を身につけるのだ。





















