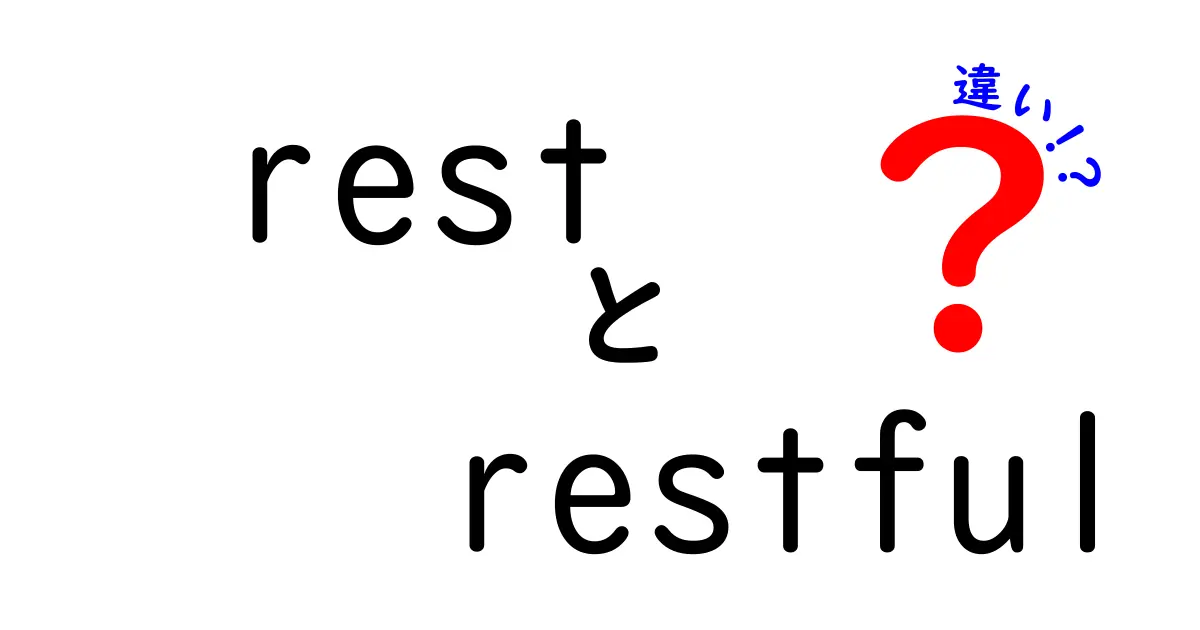

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:RESTとRESTfulの違いを混乱させる原因と正しい考え方
近年 REST と RESTful という言葉がよく混ざって使われています。表現の違いを正しく理解するには、まず REST が何を意味するのかを知ることが大切です。RESTは特定の技術の集合ではなく、ウェブ上の資源をどう取り扱うかという設計思想のことです。これを守るときの条件や原則を指しており、技術的な実装の仕方を厳密に決めるものではありません。対して RESTful とは、そのRESTの原則を「実際のAPI設計やシステムに適用した状態」であると表現する言い方です。つまりRESTそのものが思想であり、RESTfulはその思想を現実のソフトウェアにどう反映させたかを表す言葉なのです。
この違いを理解すると、RESTをどう適用するかという議論がスムーズになります。安易にRESTfulという語を使う人もいますが、背景を知ればその言葉の意味が自然と見えてきます。
本記事ではまずRESTの基本を整理し、その後RESTfulとの違いを具体的な例とともに解説します。最後には使い分けのポイントとよくある誤解についても触れます。
RESTとRESTfulの基本の違いを見抜くコツ
まず押さえたいのは REST はアーキテクチャスタイルの一つであり、特定の技術や実装を指す語ではないという点です。資源をURIで一意に表現し、HTTPの GET POST PUT DELETE などの標準メソッドを適切に使い分け、レスポンスは自己記述的で理解しやすい形にする——これらがRESTの基本的な考え方です。
一方 RESTful は、実際のAPIやサービスがこのRESTの思想をどれくらい忠実に満たしているかを示す状態です。設計や実装がRESTの原則にどれだけ沿っているかが評価基準になります。
実務では RESTful という語がしばしば仕様の満たし具合を指す名詞的な表現として使われますが、厳密には REST自体は思想を指し、RESTful はそれを現実のソフトウェアに落とし込んだ状態を指す形容詞的な用語です。ここを区別して理解することで、APIの設計方針を正しく読み解く力が身につきます。特に資源の表現方法やステートレスの考え方、キャッシュポリシーの適用などはRESTful設計かどうかを判断する重要なポイントです。
実践的な例とよくある誤解
実務での違いをつかむには具体例が役に立ちます。例えばあるAPIが資源を /books のように表現し、資源へ対してHTTPの標準メソッドを使い分けている場合はRESTの思想を正しく取り入れています。これに対してURL にアクションを明示する形の設計(例 /books/like や /books/updateStock など)は、資源指向の原則よりも操作をURLで示すアプローチでありRESTの統一インタフェース原則から離れがちです。
以下の表はRESTとRESTfulの特徴を簡潔に比較したものです。 観点 REST RESTful 定義 資源指向のアーキテクチャスタイル RESTの思想を実装でどれだけ満たしているかの状態 資源の扱い URIで資源を一意に表現 実装が資源の表現を正しく返しているかを評価 HTTPメソッドの役割 標準メソッドを意味に沿って使用 実装がメソッドの期待する副作用と副作用の扱いを適切に設計しているか ble>状態管理 サーバはクライアントの状態を持たない< ステートレスを保てているかを基準に評価
実務ではこのような違いを意識して設計を進めると混乱を防げます。
また 文献 や ガイドライン は時代とともに更新されるため、最新の実装例を複数観察することが重要です。読み手が理解しやすいAPIを設計するには、資源の表現と操作の分離、そして統一的なインタフェースの徹底が鍵になります。
まとめと使い分けのポイント
本記事の要点を整理すると、まず REST は設計思想であり、 RESTful はその思想を実際のAPIに落とし込んだ状態を指すという点が基本です。使い分けのコツは次の3点です。1つ目、資源をURIで表現し HTTP メソッドを正しく使うことで 統一インタフェース を保つ。2つ目、サーバ側のセッション状態を最小限にして ステートレス を守る。3つ目、応答は自己記述的に設計しキャッシュ可能性を適切に設定する。これを満たすAPIは RESTful であると評価されやすく、逆にこれらを欠くと RESTの精神から外れてしまいます。実務での運用では、仕様書や設計ガイドに RESTful の要件がどう適用されているかをチェックすることが安全です。最後に、RESTful かどうかは単純な判断ではなく、資源の表現方法、HTTPメソッドの使い方、状態管理の方針、レスポンスの設計など複数の要素を総合して判断します。現場ではこの総合的な視点を持つ人ほど、保守性が高く拡張性のある API を作りやすくなります。
REST についての小ネタ話題を雑談風に。私たちは普段 Web API に触れるとき、RESTという言葉をよく耳にしますね。実は REST は決まった技術の集まりではなく、資源をどう扱い表現するかという設計思想の集まりです。昔のウェブが URL と HTTP の組み合わせで動いていたのと同じように、現代の API も REST の考え方を受け継いでいます。ただし現場では RESTful という言葉が先走って使われがちで、正式な意味の区別を忘れやすいです。私が思うのは、REST の本質は資源の一貫性と操作の透明性にあるという点。つまり「この資源をこの方法で操作する」という約束を、誰が読んでも同じように解釈できる設計にすること。これが崩れると API の使い勝手が急速に悪化します。だからこそ、設計時には URI の命名規則、HTTP メソッドの副作用、リソース表現の一貫性、そしてキャッシュ可能性を意識することが大切です。





















