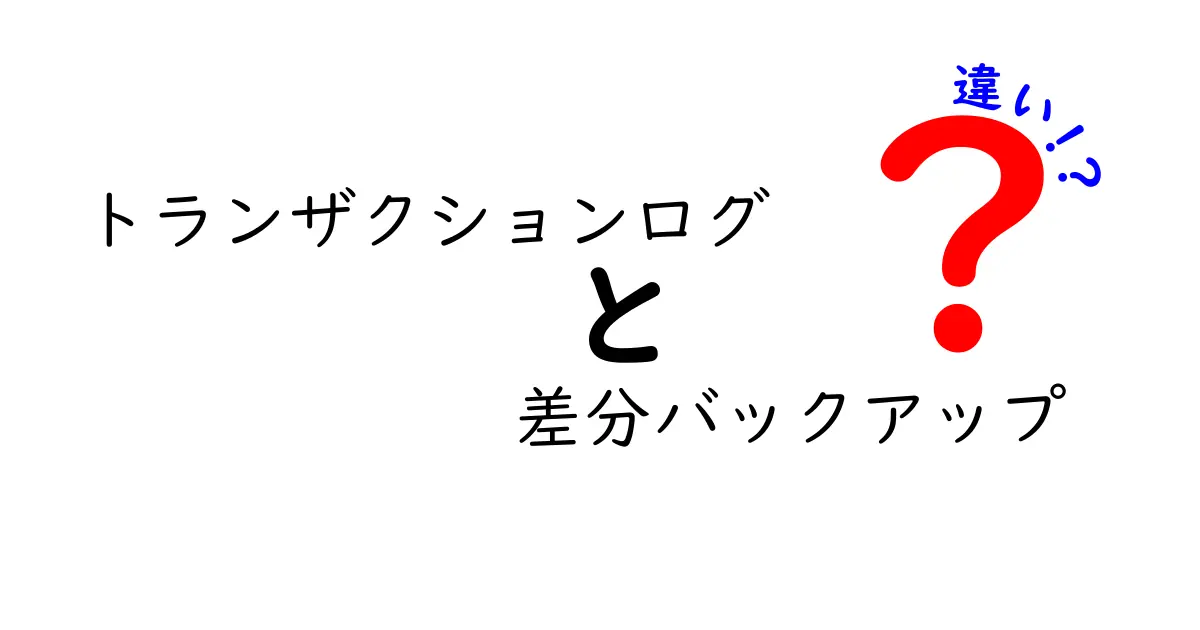

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
トランザクションログと差分バックアップの違いを徹底解説:初心者でもわかる選び方
この話題はデータを守る仕組みの中でもよく混乱するところです。
名前が似ているようで実際には別の役割を持つ二つの方法を正しく理解することが、バックアップ計画の第一歩になります。
この記事ではまず基本をやさしく説明し、その後に実務での使い分けを具体的な場面でどう選ぶかを解説します。
とくに学校の宿題のように「間違いなく戻せるか」が問われるとき、トランザクションログと 差分バックアップの違いを知っていると対応が早くなります。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、要点はとてもシンプルです。
重要なのは復元の速さとバックアップの量のバランスであり、それぞれの性質を知っておくことで選択肢を減らすことができます。
以下の説明を読んで、どんな場面でどちらを使えばよいかをイメージしてみましょう。
トランザクションログとは何か
トランザクションログはデータベースが行った変更の記録を時系列に残す仕組みです。
例えるなら日記のように、どのときに誰が何をしたのかを逐一書き留めるデータの連なりです。
このログを使うと、ある時点へだけ正確に戻すことができます。つまり点対点の復元に強い特徴を持っています。
ただしこの日記だけでは復元できず、最新のバックアップや前回のバックアップの情報も必要になることが多いです。実務ではlog backupと呼ばれる定期保存が伴い、容量が増え続ける点に注意が必要です。
またログが長くなると復元に時間がかかる場合もあるため、使い方を設計することが大切です。
差分バックアップとは何か
差分バックアップは前回行った完全バックアップ(フルバックアップ)以降に発生した変更だけを保存する方法です。
要するに「今の状態と前回の状態の差分」を集めたデータの集合です。
この方式の良さは、バックアップ量を抑えつつ、復元時に必要なデータをすぐにまとめて取り出せる点です。
ただし時とともに差分が大きくなると復元にかかる時間が長くなる可能性があり、バックアップを適切に設計しないと容量が急増してしまいます。
実務では週に一度のフルバックアップと日次の差分バックアップの組み合わせがよく使われます。
回復の観点とストレージコストのバランスを見ながら計画を立てることが大切です。
違いの要点と実務での使い分け
以下のポイントを覚えておくと選択がしやすくなります。
復元の要件が「ある時点へ戻す」か「最新状態へ戻す」かで選択は変わります。
速度の観点では差分バックアップは通常のフルバックアップより復元時間を短縮しやすい反面、ログベースの方法は点対点復元に強いという特徴があります。
容量の観点では日々の差分バックアップの方が長期的には少ない容量で済む場合がありますが、差分が大きくなると差分バックアップのサイズが増えます。
実務ではバックアップの目的を整理し、フルバックアップと差分バックアップまたはログバックアップの組み合わせを作ることが多いです。
最後に復元テストを定期的に行うことを忘れないでください。
これを行えば、緊急時に本当にデータを戻せるかを確認できます。
まとめと実務の実践例
本記事で紹介した三つのポイントを実務に活かすには、まず現場のバックアップポリシーを紙に書き出すことから始めましょう。
現状のバックアップ頻度、復元要件、保存期間、保存容量の上限などを整理します。
そして可能な限り自動化を目指します。
運用を自動化できれば、人的ミスを減らし、復元時の手順を確実にたどれるようになります。
最後に定期的な復元テストを忘れずに行い、実際にデータが戻ることを確認してください。
差分バックアップの話を友達と雑談風に深掘りする小ネタです。ある日、カフェでデータの話をしていて、差分バックアップが「前回のフルバックアップ以降に変わった分だけを保存する」という点にたどり着きました。友達が『じゃあ容量が少なくて済むの?』と聞くと、私は『うん、容量は抑えられるけど、復元には前提となるフルバックアップが必要になるからリスク分散が大事だよ』と答えました。差分は時間とともに大きくなることがあるので、頻度と組み合わせ方が大切です。こうした雑談の中で、原理と現場の現実が結びつく瞬間が私は好きです。





















