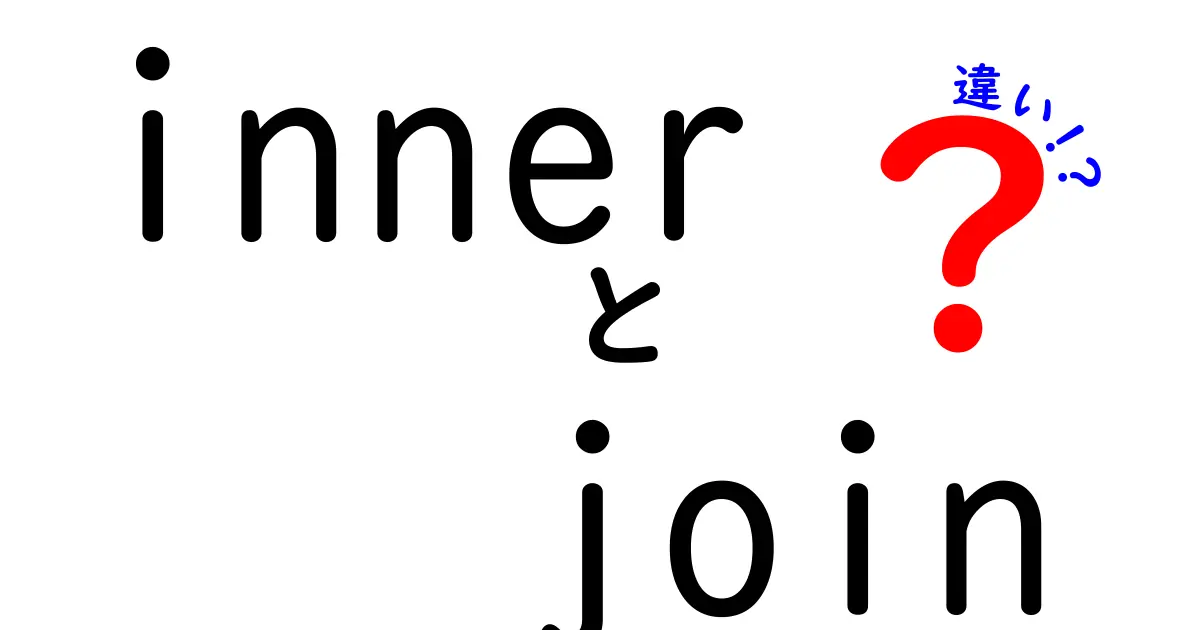

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
inner join の違いを理解して実務で活かす徹底ガイド
inner joinはデータベースの世界でよく使われる基本的な結合のひとつです。これは二つのテーブルにある共通の情報をつなぐときに使われます。例えば学校のデータを例にすると、ある生徒の基本情報が入っているテーブルと、その生徒の成績が入っているテーブルを結びつけて、どの生徒がどの科目で何点取ったかを一つの表にまとめるといった使い方ができます。
このときの大事なポイントは、結合条件と結合の種類です。結合条件とは、二つのテーブルをどの列でつなぐかを決めるルールのこと。例えば生徒IDという共通の列がある場合はその列でつなぎます。結合の種類はどういう結果が欲しいかによって変わりますが、inner joinは「両方の表に共通してデータがある行だけを取り出す」結合です。つまり片方にしかデータがない場合はその行は結果に現れません。これを覚えておくとデータを整理するときに混乱しにくくなります。
日常の例えで考えると、二つのリストを同じ名前で突き合わせる作業に似ています。名前が一致する人だけを新しいリストに入れる感じです。
この考え方を実務で使うときは、まずどのテーブルに必要なデータがあるかを確認し、次に共通のキーを見つけます。もし共通のキーがなかったり、両方の表に同じ名前の列が複数あったりする場合は別の戦略を選ぶ必要があります。
inner join はデータの整合性を保ちやすい一方で、欠けている情報を自動では補えません。必要な場合は left join や full join など他の結合方法と使い分けることが大切です。以下の表と例を参考にすると理解が深まります。
inner join の動作原理を分解
inner join は結合条件として指定された列の値が一致する行同士を結びつけ、新しい表を作ります。最初は両方の表の全行を順番に比べていくイメージです。例えば生徒テーブルと成績テーブルがあり、生徒IDを結合条件に指定した場合、同じ生徒IDを持つ行だけがひとつの新しいレコードとして並びます。
このとき注意したいのは、結合条件の列に 不足値やNULL値 があると、その行は結合の対象外になることです。つまりデータの揃い具合が結合結果を大きく左右します。
また inner join は一度結合を実行すると、結合後の表のサイズは「両方の表に共通してあるキーの数」に左右されます。キーが多く一致するほど結果の行数は増え、逆に一致が少なければ行数は減ります。
実務ではこの性質を利用して、二つのデータが正しくつながっているかを検証するのに使います。たとえば顧客データと購入履歴を結ぶとき、実際に購入があった顧客だけを取り出したい場合に inner join が適しています。
重要なのは「共通のキーを正しく設定すること」「欠損データをどう扱うかを事前に決めておくこと」です。こうすることで、分析の結果がブレず信頼性が高くなります。
実務での活用例を少し具体的に見てみましょう。学生データと授業データを結合する場面を考えます。ids という共通のキーがあり、成績がある学生だけを抽出したい場合 inner join を使います。結果には成績が記録されていない学生は現れません。もし「成績がない学生も含めたい」場合は left join を選びます。こういった選択が分析の前提を決める重要な決断になるのです。
このように inner join は情報の要点をきちんと絞ってくれる点が強みですが、すべてのケースに適しているわけではありません。状況に応じて他の結合方法と使い分ける知識が必要です。
inner join の使い分けと実務例のコツ
実務で inner join を使い分けるコツはふたつです。第一に「結合キーを正しく選ぶ」こと。キーが間違っていると全く違う結果になるので、データの性質を理解しておく必要があります。第二に「欠損データの扱いを決めておく」ことです。欠損データが多いと inner join の結果が大きく欠けることになります。
これらを前提に設計をすると、レポートや分析の信頼性が高まります。
また結合後のデータを見やすくする工夫も大切です。例えば集計用の列を追加したり、重複している列を整理したりすると、後の処理が楽になります。
要点のまとめ
inner join の本質は「共通のキーを持つ行だけをつなぐこと」です。共通キーの正しさと欠損データの扱いをきちんと決めておくことが成功のカギです。使い分けの感覚を養うには、実際のデータを使っていろいろなケースを試すのが一番早い方法です。以下のポイントを覚えておくと、実務での混乱を防げます。
- 共通キーの確認を最初に行う
- 欠損データの有無を事前にチェックする
- 他の結合とどう違うかを常に意識する
- 結果を見やすく整形する工夫をする
inner join の話を身近な例えで深掘りすると、学校のイベントで参加者リストと出席リストを照合するときのイメージがつかみやすいです。名前やIDが両方のリストに書かれていて、それらが一致した人だけを新しいリストに集める感じです。もし出席リストにいるのにイベント登録リストにはない人がいたら、その人は新しいリストには載りません。つまり inner join は「完全な一致」が前提です。この考え方を覚えておくと、データの整合性を保つ際に非常に重宝します。実務ではキーの選び方と欠測データの扱いをセットで考えることが、分析の精度を高めるコツです。なお、結合の結果をどう使うかによって left join など他の結合を選ぶ判断も生まれます。
この話のポイントは、結合の目的をはっきりさせること。例えば「欠損データを除外して強い結論を出したい」のか「欠損データも含めて全体像を知りたい」のかで、inner join か別の結合を選ぶべきかが変わります。





















