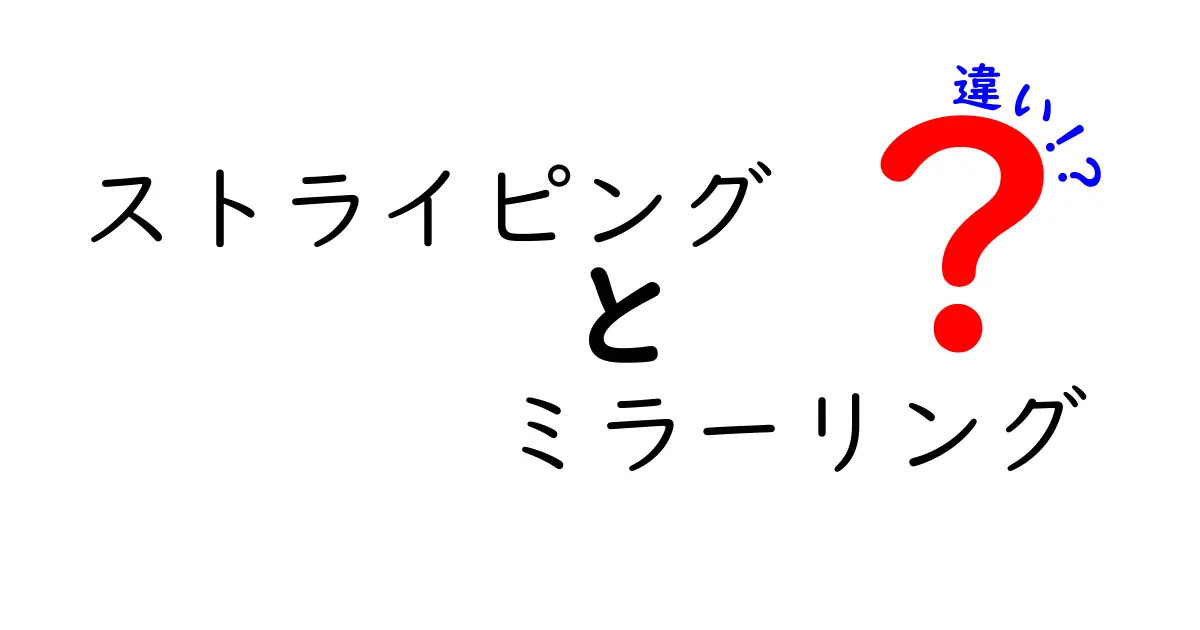

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ストライピングとミラーリングの違いを徹底解説!初心者でも分かる RAID の基礎理解
データ保存のしくみにはいろいろな考え方があります。ストライピングとミラーリングは、複数のディスクを使ってデータをどう配置するかの考え方の違いです。まず結論から言うと、ストライピングは速さを重視してデータを分割して並べる方法、ミラーリングは安全性を重視して同じデータを二つ以上のディスクに写す方法です。例えば、本を1冊分を2つの棚に分けて交互に並べるようなイメージを想像してください。最初のページは棚A、次のページは棚B、さらに次のページは棚Aへ戻す、というふうに配置すると、両方の棚から同時にページを取り出すことができます。この「同時アクセス」がストライピングの基本的な仕組みです。
ストライピングの魅力は、ディスクが複数あればあるほど同時に動くデータの量が増え、読み取りと書き込みの速度が大きく向上する点にあります。ただし、ここには重要な落とし穴もあり、ストライピングだけではデータの安全性はほとんど守られません。どんなにたくさんのディスクを使っていても、一つのディスクが壊れると、分散していたデータの一部が破損する可能性が高くなります。実務では「ストライピング+別の冗長性を組み合わせる」ことが一般的です。たとえば、RAID0のようにストライピングのみを使う構成は、速さを最優先する環境に適していますが、バックアップとしての信頼性を確保するためには別の手段が不可欠です。こうした基本を押さえつつ、なぜこの2つが別の設計思想なのかを理解することが、後の選択を楽にしてくれます。さらに実務で気をつけるべき点として、ストライピングはディスクの数が増えるほど「コントローラの負荷」や「再構築の時間」が長くなること、そして「容量の効率」がディスク数と関係して変わることがあります。これらの要素をよく理解せずに導入すると、思っていたほどの効果を得られないこともあるため、家電量販店の広告だけで決めるのは避けたいところです。次のセクションでは、もう一方の代表格であるミラーリングについて詳しく見ていきましょう。ここまでの話を踏まえ、読者のみなさんが自分のケースに合う構成を選ぶヒントをつかんでくれればうれしいです。
なお、後半の説明へ進む前に、一つの覚え方を紹介します。ストライピング=“速さの分割”、ミラーリング=“安全の複製”。この覚え方だけでも、選択の方向性が見えやすくなるはずです。
ストライピングとは?
ストライピングとは、データを小さなブロックに分割して、複数のディスクに同時に書き込む仕組みです。1つのファイルを連続したブロックに分け、それぞれを2台以上のディスクに交互に配置します。こうすることで、読み取り時には複数のディスクから同時にデータを読み出せるため、全体のスループットが上がります。たとえば大きな動画ファイルを再生したり、ゲームを起動したりする場合、ディスクが同時に動く量が増えるので、待ち時間が短く感じられやすいです。また、ストライピングは「容量の総量をほぼそのまま使える」点も利点のひとつです。RAID0の場合、ディスク2台で容量は2TBなら2TB、ディスクがn台あればn倍の容量を使えます。しかし、ここには落とし穴があります。前に触れたとおり、冗長性がほとんど無いため、1台でも壊れるとデータの一部が失われやすくなります。ここで大事なのは「バックアップが別にあるかどうか」です。たとえばクラウドストレージや定期的なバックアップを別途行えば、リスクを軽減できます。ストライピングは、日常的な作業の中で、写真や動画の編集、大きなファイルの移動、アプリのロード時間の短縮など、"実感できる速さ"を体感しやすい場面が多いです。実務の現場では、SSDの速度をさらに引き出すための工夫として使われることが多く、特に読み取りが多い環境で効果を発揮します。ここでは、ストライピングの仕組みを分かりやすく整理し、どうして速度が出るのか、どんな場面で強いのか、そしてどう回避策を講じるべきかを、具体例とともに解説します。
また、ストライピングを有効活用するためには、ストライピングの幅(Stripe Width)と呼ばれる指標にも着目する必要があります。stripe widthが大きいほど、データの並列処理が増え、結果として読み書きの速度が向上しますが、同時に故障リスクの影響範囲も広がるため、適切なディスク数と構成を選ぶことが大切です。
ミラーリングとは?
ミラーリングは、データをそのまま複製して別のディスクに書く方法です。RAID1とも呼ばれ、1台のディスクが壊れても、もう一方のディスクに同じデータが残っているため、復旧が比較的スムーズです。実務的には、2台以上のディスクを使い、書き込み処理を2台以上のディスクに同時に行います。こうして、読み取りは2台の中からデータを取り出せるため、読み取りの速度が改善されることもあります。ただし、ストライピングと比べて書き込みの負荷は増えるため、総じて書き込み性能は低下する傾向があります。容量は、最も小さいディスクの容量に合わせて決まり、2台ならその半分、3台なら同じ容量を足しても、総容量は最も小さいディスクの容量に制限されます。故障時の回復は、壊れたディスクを取り替え、ミラーリングを再構成することで完了します。再構築には時間がかかることがあり、特に大容量のディスクを使う場合はデータの一部が一時的に安全性を欠く状態になることにも注意が必要です。ミラーリングの最大の魅力は「データの安全性」です。重要なファイルや長期保存するデータ、学校の課題データ、写真・動画など、消えると困る情報を扱う場面で強みを発揮します。仮に1台が故障しても、もう1台に同じ情報が残っているので、すぐに復旧作業を始められます。さらに、近年は消費電力の低下とコストの低下が同時に進んでおり、家庭用のPCでもミラーリングを取り入れるケースが増えています。とはいえ、ミラーリングにもデメリットはあります。容量効率はストライピングよりも劣り、同じ容量を使う場合でもディスクの総コストは高くなりがちです。書き込みのオーバーヘッドが増えるため、速度を第一に考える作業には向かないことも多いです。つまり、用途をはっきりさせ、どんなときに安定した保存と復旧を重視するのかを考えることが大切です。ミラーリングは「バックアップの中でも最も身近で信頼性の高い選択肢」として、特に学習用のデータや日常の重要なファイルの保護に適しています。以上を踏まえ、ストライピングとミラーリング、それぞれの長所・短所を整理することで、あなたの使い方に最も適した構成を選ぶ手助けになるはずです。
違いのポイントと選び方
違いの要点は3つの軸で考えると分かりやすいです:安全性、速度、容量効率。安全性はミラーリングが強く、ストライピングはほぼゼロです。速度はストライピングが優れ、容量はストライピングが高い、ミラーリングは容量が半分程度に目減りすることが多い。実際の選択は、何を重視するかで決まります。家庭向けの写真データのバックアップなら、ミラーリングをベースに適切なバックアップを追加するのが安全です。しかし作業用データの編集や動画の大型ファイルの扱いなど、読み取り・書き込みの速度が重要な場合は、ストライピングを中心に考え、必要に応じてバックアップを別に取るとよいでしょう。さらに現実的な話としては、コストと電力、故障時の回復時間の3点が重くのしかかります。たとえば、2台のディスクだけで済む構成と4台を使う構成では、コストと電力の差が大きく現れます。故障時の回復には、同じ構成を維持して新しいディスクにデータを再コピーする期間が必要です。この期間中は、データの整合性を保つための管理作業も増えます。技術的な専門用語は覚える必要がありますが、基本の考え方を押さえるだけで、選択はぐっと簡単になります。目的をはっきりさせ、速度と安全性のどちらを優先するのか、そしてコストをどう抑えるかを軸に判断すると良いでしょう。最終的には、実際の運用状況を見ながら、専用の管理ソフトウェアの機能や、バックアップの方法を組み合わせて最適化することが成功への近道です。
ある日、友だちとパソコンの話をしていてストライピングの話題になった。私は『データを分けて同時に書くんだよ』と説明した。友だちは『それって本の並べ方みたいだね』と言い、私は『そう、速さを重視する分散実行の考え方なんだ』と続けた。私たちは、実際に2台のハードディスクを使うときの手触り、壊れたときの復旧の難しさ、そして安全性とのバランスについて、具体的な例を出しながら友人と話していった。
ストライピングの要点は、速さを追求する一方で冗長性が薄い点。 だから、バックアップを別に用意するのがコツだと学んだ。そんな会話の中で、私たちはシンプルな暗号のように、考え方の軸を一本化する覚え方を見つけた。ストライピング=速さの分割、ミラーリング=安全の複製。これを覚えておくと、次に新しい構成を検討するときの指針になる。





















