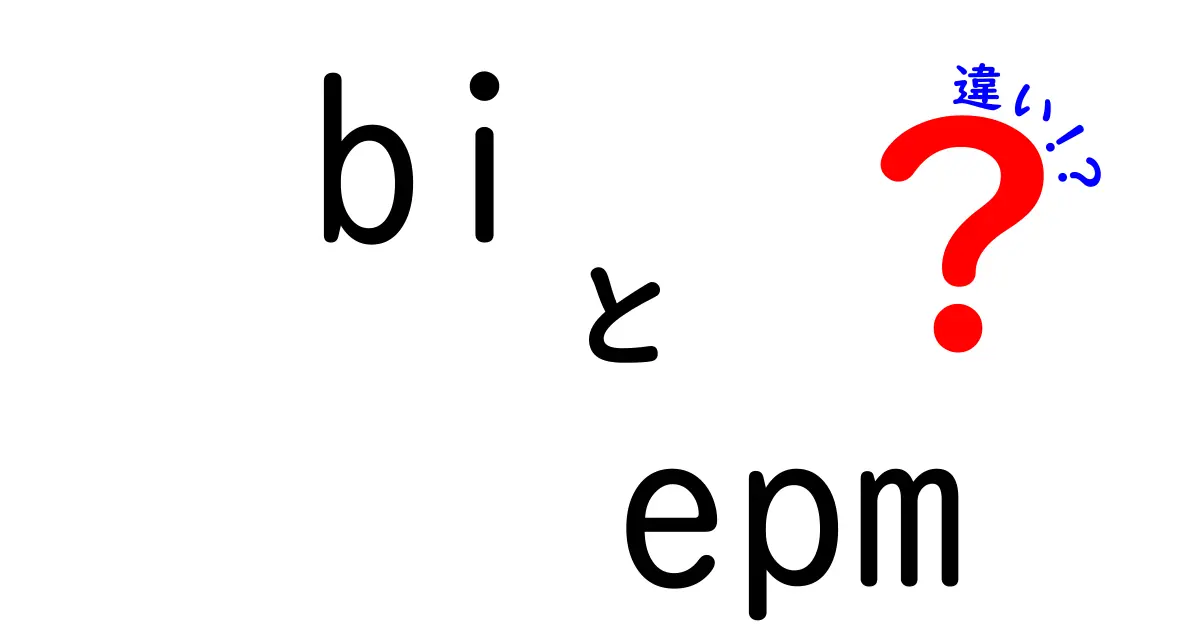

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
BIとEPMの違いを徹底解説!初心者にも分かる3つのポイントと使い分け
現代の企業や学校では、データを活用して「何が起きているのか」を知ることが大切です。BIとEPMは似ている言葉ですが、役割や使い方が異なります。ここでは基礎から丁寧に解説します。
まずは結論から言うと、BIはデータを集めて分析し、現状を“見える化”するツール、EPMは企業の長期的な計画を立て、予算と実績を横断的に管理する仕組みです。これを理解することで、日常の業務で「何をどう比較するべきか」が見えてきます。
以下では、身近な例を使いながら、順番に説明します。
なお、両者は相補的に使われることが多く、情報の流れをスムーズにすることが目的です。
BIとは何か、基本概念と使い道
BIはビジネス・インテリジェンスの略で、企業が保有しているデータを集め、整理し、分析して「どうなっているのか」をわかりやすく見せる道具です。日常の例を考えると、クラスの出席データを月ごとに集計してグラフ化する、学校の成績データを科目別に比較する、売上データを地域ごとに並べ替える、そんな作業がBIの基本です。
BIの主な工程は、データの収集・統合・整理・分析・可視化の5つ。ここで大事なのは、データの品質と統一性、そして“誰が何を見るべきか”という視点です。
BIツールはダッシュボードと呼ばれる画面を提供し、直感的に指標を確認できるように設計されています。例えば「日別の売上、前月比、商品別ランキング」を一枚の画面で同時に見られるようにします。
中学生にも分かりやすく言えば、BIは「データの地図」を作って、地図上の点をクリックするともっと詳しい情報が出てくる、そんな感じです。
この地図を作るには、データの正確さがとても大切で、データ入力のルールや重複データの削除、欠損値の処理などの前処理が欠かせません。
つまり、BIを使うと「何が起きているのか」「どの指標が重要なのか」が一目で分かるようになり、現場の人たちが素早く判断できるようになります。
EPMとは何か、基本概念と使い道
EPMはEnterprise Performance Managementの略で、企業の戦略目標を達成するための計画、予算、予測、財務統合をサポートするための仕組みです。BIが“現状の把握”に強いのに対して、EPMは“これからどうするか”を設計する機能に焦点を当てます。
具体的には、財務計画、部門別の予算管理、キャッシュフローの予測、KPIの追跡、戦略のシナリオ分析などが含まれます。大きな会社では、毎年の予算編成だけでなく、 quarterlyや月次の実績との比較、将来のシナリオを作成して意思決定を支援します。
EPMは複数のデータソースを横断して「整合性のある前提」を作り、実際の実績と計画のズレを早期に検知する機能を持つことが多いです。これにより、戦略と実行のギャップを埋め、組織全体のパフォーマンスを高めます。
中学生レベルで言えば、EPMは「学校の年間計画書と日々の成績を結びつけて、進行状況を常にチェックする仕組み」とイメージすると分かりやすいでしょう。
EPMの導入には、データガバナンスや権限管理、セキュリティの配慮が欠かせず、正確なデータ構造と明確な責任分担が基盤となります。
BiとEPMの違いの実務的な使い分けと注意点
BIとEPMは役割が異なるため、混ぜて使う場面と分けて使う場面を理解して使い分けることが大切です。
まず、BIは日々の運用で現状を把握するための強力なツールです。日次・週次のレポート、売上やコストの分析、顧客動向の見える化など、現場の意思決定を迅速化します。
一方のEPMは「未来の計画を作成し、それを実行していく」仕組みです。予算の設定、予測の更新、KPIの達成状況を横断的に監視します。現実にはBIとEPMを組み合わせて使うケースが多く、BIでデータの現状をしっかり把握した上で、EPMで戦略計画と予算を結びつけて実行します。
注意点としては、データの統合元を増やしすぎない、過剰な複雑さを避けること、そして権限とセキュリティを明確にすることです。
小さな組織では、まずBIの導入から始め、データの基本的な品質を確保してからEPMへ段階的に拡張するのが現実的です。表形式の比較を後半で示します。
最後に、BIとEPMの併用は組織の意思決定を大きく改善します。現状の状況把握と未来の戦略実行を一つの流れとして回すことで、目標達成までの道筋がはっきりします。中学生の皆さんも、学校のイベント運営や部活動の計画立案にこの考え方を応用できるはずです。
今日は放課後、友だちと『BIって何だろう?』と雑談していたんだ。BIは“今のデータを集めて、何が起きているのかを可視化する道具”のようだと直感した。たとえば校内の成績データをグラフ化して、どの科目が伸びていて、どこが苦手かが一目でわかる。EPMは“これからどうするか”の計画を作って、それを実行していく仕組み。過去のデータ分析と未来の計画立案を結ぶ橋みたいだ。二つを上手に使い分けると、部活の予算管理や学校行事の運営にも活かせると実感した。





















