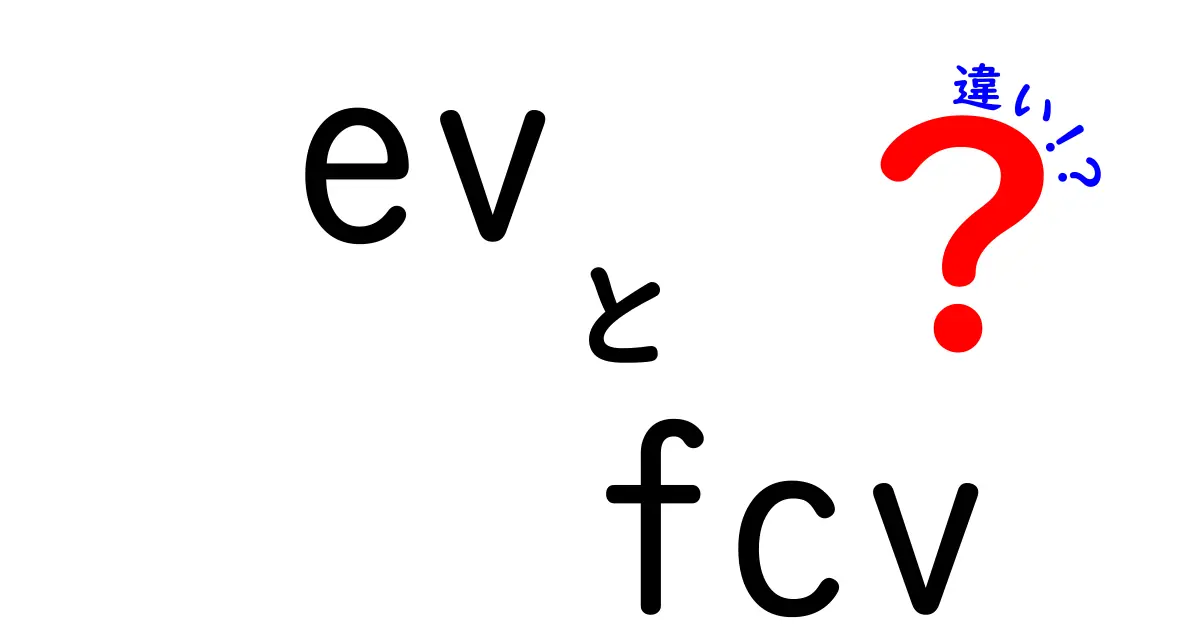

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
EVとFCVの違いを理解する基本ポイント
現代の車には大きく分けて電気を動力として使う車が増えています。その中でも「EV(電気自動車)」と「FCV(燃料電池車)」はよく比較される代表格です。ここではまず基本を押さえます。
EVはバッテリーに蓄えた電力をモーターで走らせます。充電は家庭のコンセントや充電スタンドから行い、一度の充電で走れる距離はバッテリー容量と充電の効率に左右されます。対してFCVは水素を燃料として燃料電池が電気を作り出し、それをモーターに送って動きます。水素はガソリンのようにガソリンスタンドで補充します。充填は通常3〜5分程度で完了しますが、水素ステーションの数はまだ限られています。
つまり、基本的な違いは「エネルギーの貯蔵・供給方法」と「給油・充電の方法」にあります。これらの差は走る距離だけでなく、インフラの整備状況やコスト、使い方にも影響します。
理解のポイントは“どのように電力を手に入れるか”と“どれだけ手早く補充できるか”の2つです。
日常の使い方での違いを比較
日常的な使い方を想像すると、EVは「自宅の電源を使って夜間にじっくり充電する」生活が合うことが多いです。夜間の安い電力を使えばランニングコストを抑えられます。対してFCVは「急いで長距離を移動したいときに水素を補給して走り切る」イメージです。水素ステーションが近くにあれば、出張や遠出でも時間を大幅に節約できます。とはいえ、水素ステーションがまだ少ない地域では、充填の機会が限られるため計画性が必要です。走行距離の点では、最新のEVは車種ごとに100km台〜500km以上の範囲を持ちます。FCVも同様にモデルにより大きく差があります。環境性の面では両者とも運動エネルギーを使うため排出量は低く、特に走行時の排出はほぼゼロに近いのが特徴です。実際の費用面では、車両価格と燃料費の2つを長期で見る必要があります。EVは初期費用が高めでも蓄電のコストを長期間で回収しやすい場合があります。FCVは水素の補給コストが影響しますが、走行距離が長い場合には有利になることもあります。総じて、用途と生活スタイル次第で最適解は変わります。
この違いを理解することで、ショップでの説明をより正確に受け取れるようになります。
なお、車両以外の選択肢としてはガソリン車・ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車といった中間タイプも存在します。
昨日、友だちとEVとFCVの充電時間の話をしていて面白かったんだ。EVは夜間の自宅充電を活用して長い待ち時間を“生活リズムの一部”に組み込むのがコツだと気づいた。逆にFCVは水素を瞬時に補給できる利点があり、急ぎの長旅には強い。ただ、水素ステーションの数がまだ限られている地域もある。つまり、充電時間というキーワードは“場所と時間の組み合わせ”で変わるという結論に落ち着いた。こうした視点で見ると、どちらを選ぶべきかが自分の生活圏と目的次第だと分かるんだ。





















