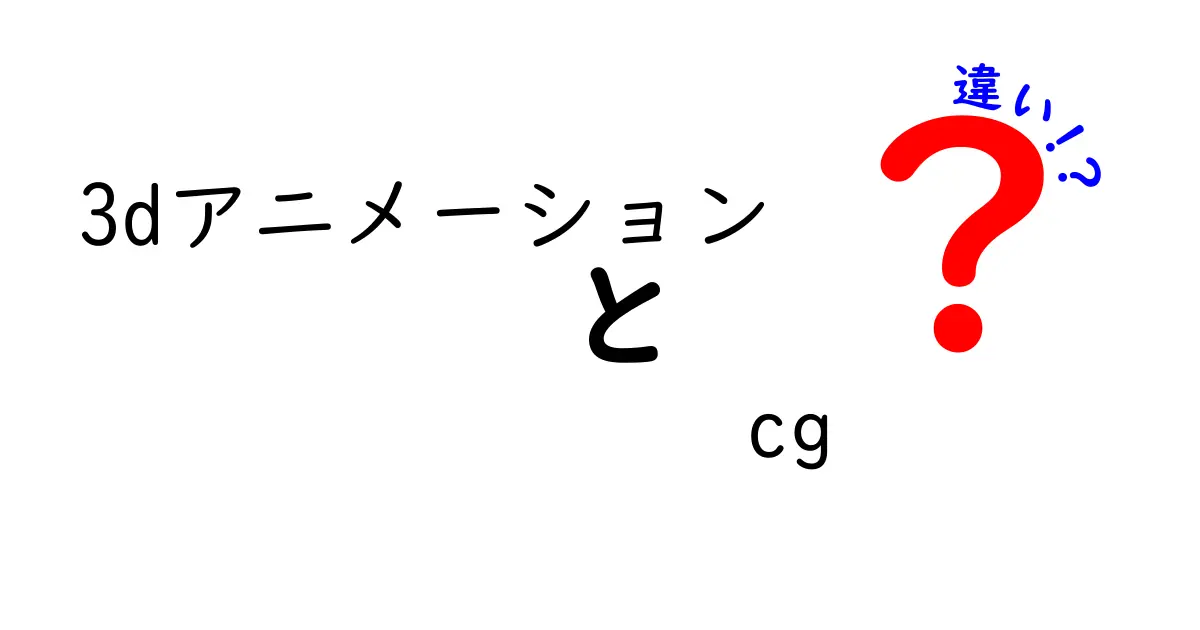

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3DアニメーションとCGの違いを徹底解説!初心者にも分かる図解つきガイド
本記事では「3dアニメーション」と「cg」の違いを、中学生にも分かる言葉で丁寧に解説します。映像を作る現場では似ているようで違う用語が混在します。ここではまず基本的な意味から整理し、その後「作り方の流れ」「よくある誤解」「実務での活用例」まで、具体例と図を使いながら説明します。
3Dアニメーションは「動く立体感」を作る技術全体のことを指す場合が多く、CG(Computer Graphics)は「コンピュータで描くグラフィックス全般」を指す広い概念です。
この二つの関係を押さえると、作品を作るときに何を準備し、どのツールを選ぶべきかが見えてきます。
以下の内容は初めて学ぶ人が混乱しがちなポイントを中心にまとめました。
まずは用語の違いをしっかり押さえ、次に制作の流れとツール、最後に実務での活用例を見ていきましょう。
1. 基本の違いを押さえる
「3Dアニメーション」とは、3次元の空間を使ってキャラクターや物体を動かす表現のことを指します。観客の視点で見ると、実写に近い動きやリアルな陰影、カメラワークの自由度などが生まれます。
いっぽう「CG」はもっと広い概念で、静止画のCG、3D CG、VFXの合成、UIの描画など、デジタルで作られるすべてのグラフィックスを含みます。例えば、ポスターのCGデザイン、ゲームのキャラのテクスチャ、映画の特殊効果もCGの分野に入ります。
つまり「3Dアニメーション」はCGの中の一つの技法であり、動きと空間を作る具体的な作業プロセスを指すことが多いのです。
この違いを理解すると、制作現場での会話もスムーズになり、何を学ぶべきかが見えてきます。
2. 作り方の流れと道具
3Dアニメーションを作る一般的な流れは、まずキャラクターやオブジェクトの「モデル」を作成します。これは粘土モデルのデジタル版のようなもので、形を決める「モデリング」と呼ばれる工程です。次にそのモデルに「骨格」を入れて動かせるようにする「リギング」、そして「動きを付けるアニメーション」を作ります。ここではキーフレームと呼ばれる重要な瞬間を決め、ソフトウェアが中間の動きを補完します。
続いて「マテリアル(質感)とテクスチャ」を設定して表面の色や光の反射を決め、ライティングとカメラ設定を整え、最終的に映像として出力します。これが「レンダリング」と呼ばれる工程です。リアルな陰影や反射を出すにはレンダリングエンジンと呼ばれるソフトウェアの機能を使います。
CGの道具としては、Maya、Blender、3ds Max などの3Dソフトと、Substance Painter などのテクスチャツール、Nuke や After Effects のような合成ソフトが代表的です。用途に応じて組み合わせを選ぶのが現場のコツです。
なお「2Dアニメーション」との違いは、物体の奥行きと視点の変化を3D空間で表現する点にあります。
3. 実務での使われ方の例
映画やゲームの現場では、3DアニメーションとCGは密接に関係しています。例えば映画のモンスターを3Dでモデル化して動かす作業は、3Dアニメーションの典型です。一方でその3Dモデルを画面に合成して、背景の風景や爆発の煙、炎などをCGとして追加します。こうした「3DアニメーションとCGの組み合わせ」は、観客にとって自然で迫力のある映像を作る秘訣です。
また、教育用動画や医療シミュレーション、建築のプレゼン資料など、非エンタメ分野でもCG技術は広く使われています。デザインの段階で静止画のCGを作り、後で3Dアニメーションの要素を加えるケースも多く、学ぶ範囲は広がっています。
この章では現場の実例を交え、どのようなスキルセットが必要か、また学ぶ順序の目安を具体的に紹介します。
興味がある人は、まず基礎的なモデリングとテクスチャの操作から始め、次にアニメーションの基本とレンダリングの workflow を体験してみてください。
このように、3Dアニメーションは実際の動きや空間を作る技術であり、CGはそれを含むより広いデジタル表現の総称です。
初心者はまず「3Dの基本操作」「リギングとアニメーションの考え方」を学ぶと、現場の会話が理解しやすくなります。
次のステップとして、レンダリングと合成の技術を学ぶと、納得のいく作品に近づきます。
将来的には自分の作品をポートフォリオとして公開するまでを目標に、段階的にスキルを積み上げてください。
小ネタとしてのひとくち雑談: 実は3DアニメーションとCGの違いを理解すると、好きな映画の見方が変わることがあります。背景が実写に見える場面は、実際にはCGで描かれていることが多く、その背景とキャラクターの動きを合わせる“合成”技術が使われています。モデリングが形を作り、テクスチャが肌や衣服の質感を決め、リギングが動きをつけ、レンダリングが光と影を計算する—この一連の工程を知れば、映画の一場面一場面に込められた工夫をより深く楽しむことができます。つまり、作品を作る現場は大人数のチームワークで成り立っており、デザイナー、アニメーター、照明、音響など、役割は多岐にわたるのです。





















