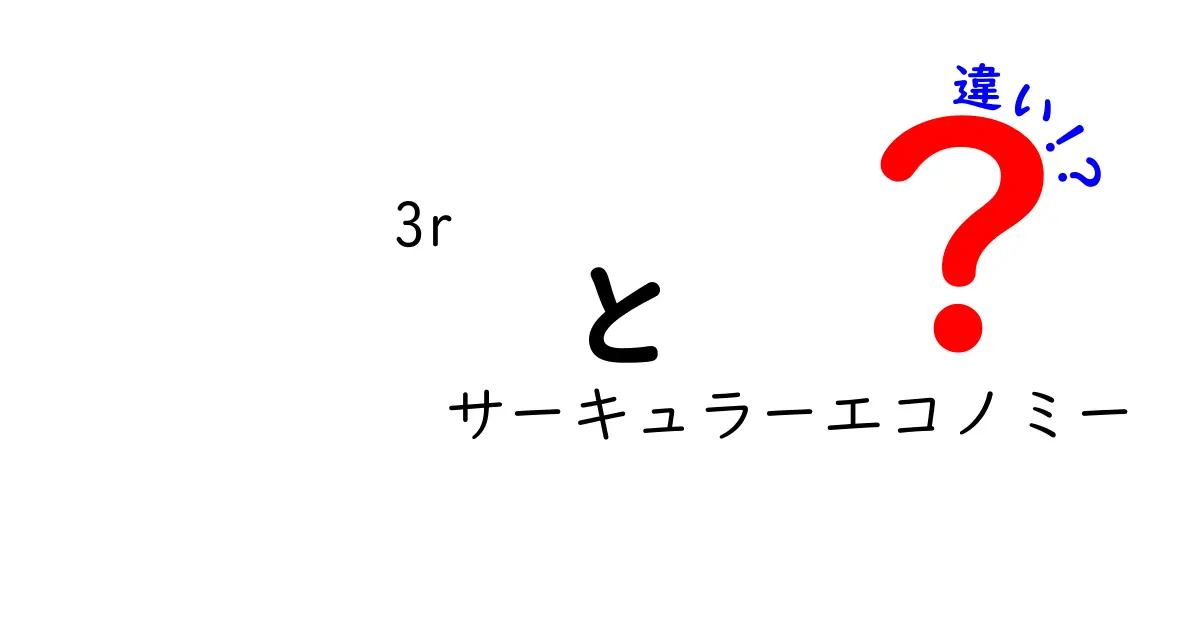

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3Rとサーキュラーエコノミーの違いを理解する3つの観点
ここでは 3Rとサーキュラーエコノミーの違いを、基本の意味、目的、そして私たちが日常でどう活かせるかという観点から分かりやすく解説します。3Rは主に資源の使い方を工夫して废棄を減らす実践の考え方で、Reduce/Reuse/Recycleの3つの行動を指します。一方のサーキュラーエコノミーは経済全体の仕組みとして、物を長く使い回し、資源を閉じた循環に乗せ、廃棄を極力減らすための社会・ビジネスの設計思想です。つまり 3R が日常の行動指針だとすると、サーキュラーエコノミーは社会全体の仕組みをどう作るかという大きな設計思想です。ここを混同してしまうと、具体的な現場の取り組みと経済の大きな動きが別物として語られてしまうことがあります。
この違いを理解することで、学校の授業や家庭での実践、企業の取り組みを結びつけて考えることができ、みんなが取り組むべき優先順位も見えてきます。
以下では 3R の3つの柱を詳しく見つつ、サーキュラーエコノミーがどんな設計思想なのか、どのように現場で適用されるのかを具体的な例を交えて説明します。
3Rの基本とは何か
3R は Reduce の考え方から始まります。つまり「必要以上に作らない・使い過ぎない」ことを最優先にするのです。次に Reuse です。再利用できる部品や資材を可能な限り使い回すこと。最後に Recycle、つまり資源を破砕して新しい材料として再生するプロセスを指します。この順番が重要で、最も効果が大きいのは Reduce、次に Reuse、そして Recycle へと進む順序です。日常生活では、買い物の回数を減らす、使い捨てを避ける、壊れたものを修理して長く使うといった具体的な行動が 3R の実践です。学校の授業ではリデュースの視点から教科のプロジェクトに取り組み、家庭では買い物の計画性を高めることで成果を出すことができます。
注意すべき点は、Recycle だけを過度に強調すると資源の循環を誤解させることがある点です。Recycle は確かに資源を取り戻す手段ですが、可能な限り Reduce と Reuse を優先するべきという原則を忘れてはいけません。
この章では、実際の製品設計や消費者の選択にどう現れるのかを、日常生活の具体例を通して見ていきます。
サーキュラーエコノミーの基本概念
サーキュラーエコノミーは「資源を使い切るモデル」ではなく、「資源をできるだけ長く使い続け、廃棄を極力減らす社会経済の仕組み」を作る考え方です。ここでのキーワードは 閉じた循環と 設計の工夫です。製品は単に売るものではなく、長寿命・修理・再利用・再設計を前提に作られます。例えば、家具が壊れたときに部品を取り替えやすくするデザイン、衣類が傷ついたら修理で再び着用できるようにする生地選択、家電が古くなっても部品を交換して長く使える仕組みなどが挙げられます。企業側には、製品を売るのではなく「サービスとして提供する」モデル(製品の所有権ではなく使用権を提供する)も増えています。これにより、製品の寿命を延ばすインセンティブが高まり、資源の新規需要を減らしていくことが狙いです。
サーキュラーエコノミーは政府の政策、企業の投資、消費者の選択の三つが連携して初めて機能します。地域のリサイクル施設を拡充するだけでなく、企業が新しい素材開発に投資し、学校教育で循環経済の考え方を教える、地域での回収ボックスを設置するといった取り組みが同時に進むことで、社会全体が資源を大切に扱う仕組みに近づきます。
子どもたちにも伝えたいのは、サーキュラーエコノミーは「人々の生活を守るための全体設計」だという点です。私たちが学んだことを使って、将来の地球の資源を守る活動が、学校や地域、企業の文化として根づくことが目標です。
3Rとサーキュラーエコノミーの違いをつなぐ視点
3Rとサーキュラーエコノミーの違いを学ぶとき、最も分かりやすいのは「目的と規模の違い」を理解することです。3R は家庭や学校、地域の行動指針としての具体的な手段を示します。Reduce を優先し、物を作る量を減らす、使い捨てを減らす、長く使うための工夫をする、という日常の実践が軸です。対してサーキュラーエコノミーは、企業の製品設計や都市全体の資源フローを変える大きな設計思想であり、資金の流れ、素材の流通、製品のライフサイクル、回収と再利用の制度設計までを含みます。つまり 3R は「個人・家庭・学校の具体的な行動」、サーキュラーエコノミーは「社会全体の仕組みと経済モデル」という対応関係です。
この違いを意識して学ぶと、授業の中で「何を、誰が、どう変えるべきか」がはっきり見えてきます。例えば、学校の cafeteria で使い捨てカトラリーをやめて再利用可能なものに変えると、資源の浪費を減らす効果が直ちに出ます。一方、企業が製品を修理しやすい設計に変えれば、製品の寿命が延び、資源の消費を長期的に抑えることができます。
このように 3R の実践とサーキュラーエコノミーの設計思想を結びつけて考えると、個人の行動と社会の仕組みの両方が改善される道筋が見えてきます。
今日は友達と放課後に 3R の話題を深掘りしてみたよ。特にリデュースという考え方は、最初の一歩としてとても実用的だと感じた。僕たちが買い物をする回数を減らす工夫を日常に取り入れれば、無駄な資源の使い方を減らせるんだ。例えば文房具を大切に使う、壊れたものを修理して長く使い続ける、家で出るゴミの分別をきちんとする――そんな小さな積み重ねが、将来の地球に大きな影響を与えるって考えると、なんだかワクワクする。リデュースは「今ある資源を大切に使う」という視点で、友達との協力や学校の取り組みにも自然とつながっていく。結局、3Rは単なる言葉遊びじゃなく、私たちの生活を守るための“現実的な設計”なんだと、今日改めて感じたよ。
前の記事: « 受領証 預り証 違いを徹底解説!場面別の使い分けとポイント





















