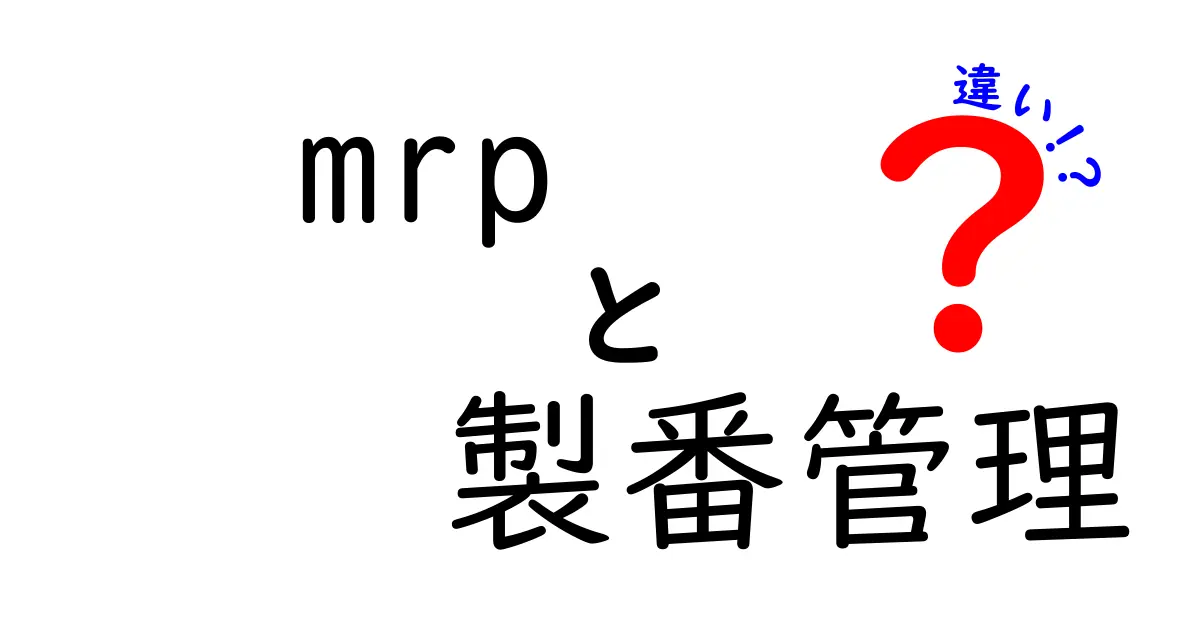

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:MRPと製番管理の違いを理解する
MRPは材料所要量計画の略で、製品を作るために必要な部品や原材料をいつ、どれだけ調達するかを数字で予測します。需要データ、BOM、納期、仕入先のリードタイムなどを組み合わせ、欠品を減らし生産計画を安定させるのが狙いです。MRPは通常ERPの機能として動作し、企業全体の購買と製造の動きを統合します。データの正確さが結果を決め、データが古いと発注や生産指示がずれて過剰在庫や欠品が起こるリスクがあります。
ここで重要なのは、MRPと現場の実作業のつながりを適切に保つことです。現場の実情と最新のデータを結びつける仕組みが整っていれば、計画と実績のギャップを小さくできます。
製番管理は製品が実際にラインを通って作られた後の追跡や品質管理に焦点を当てる仕組みです。製番やロット番号を使って、どの製品がどのロットで作られたか、検査結果はどうだったかを後から辿ることができます。これによりリコール対応や品質問題の原因追及が速くなり、顧客への信頼を守る力になります。MRPと製番管理は連携して使われることが多いですが、役割は異なります。
均等に使うより“用途に応じた使い分け”が現場の生産性を高める鍵です。
MRPとは何か:材料計画の仕組みと役割
MRPの基本は、BOM(部品表)と需要データを元に、どの部材がいつどれだけ必要になるかを計算して、購買・生産の指示へと変換することです。需要が入ると部品が最終製品に変わるまでの過程を“爆発的に”展開して、欠品を防ぐための調達時期と数量を提案します。これには納期やリードタイム、在庫量、サプライヤの信頼性といった情報が不可欠です。
現場と購買部門が同じデータを見て動けるようにすることで、納期遵守と在庫最適化の両立を目指します。
MRPはデータの正確さに強く依存します。例えば在庫数量が実在とずれていたり、納期情報が遅れて更新されていると、計画はすぐに崩れてしまいます。したがって導入時にはデータクリーニングとデータガバナンス、定期的なデータの検証が不可欠です。ERP内の権限設定やワークフローも影響し、誰がどの変更を承認するかが生産計画の信頼性を左右します。
またMRPは周期的な更新で現状を反映します。日次更新か週次更新かは企業の規模や業態により異なり、現場の agilityと整合させることが重要です。
実務上のメリットは在庫削減と納期の安定、調達コストの適正化です。一方デメリットはデータ品質の維持コストと初期設定の難しさ、急な設計変更や部品の代替対応が遅れるリスクです。これらを乗り越えるには、データの一元管理と現場との密な情報共有が欠かせません。
製番管理とは何か:追跡と品質管理の現場
製番管理は製品が実際に製造・出荷されるまでの全履歴を追跡する仕組みです。製番やロット番号を割り当て、どの製品がどのロットでどの工程を経たか、どの検査結果や工程の記録があるかを記録します。これにより不具合が発生した場合の原因追及が速くなり、品質保証の体制を強化します。具体的には不具合のあるロットを特定して早期に回収指示を出す、保証期間の管理を正確に行うといった対応が可能になります。
製番管理はMES(製造実行システム)やERPと連携することが多く、リアルタイム性を高めるほど現場の意思決定が素早くなります。現場ではバーコードやRFIDの活用で作業履歴の入力を楽にする工夫が一般的です。これにより、誰がいつどの工程を担当したのかが正確に記録され、品質トラブルの再発防止にもつながります。
ただし製番管理を徹底するには規則の整備と運用の周知が不可欠です。番号の付け方、データの入力ルール、監査の体制を事前に決めておく必要があります。
表と事例を交えた整理は、現場の混乱を避けるのに役立ちます。下の表はMRPと製番管理の観点を比べたごく基本的なものです。現実の運用ではこの差を自社の業務フローに合わせて具体化していくことが大切です。
ねえ、MRPって難しそうに聞こえるけど、要は『在庫を減らして納期を守るための賢い計画表』みたいなものだよ。需要が増えたときにどう部品を準備するか、どの順番で作るかを自動で教えてくれる。だから現場は指示待ちじゃなく、データに基づいて動けるようになる。製番管理はその後の実際の製品の履歴をきっちり記録して、もし不具合が起きても原因を特定しやすくする仕組み。二つを上手に組み合わせると、見えないコストを減らせるんだよ。





















