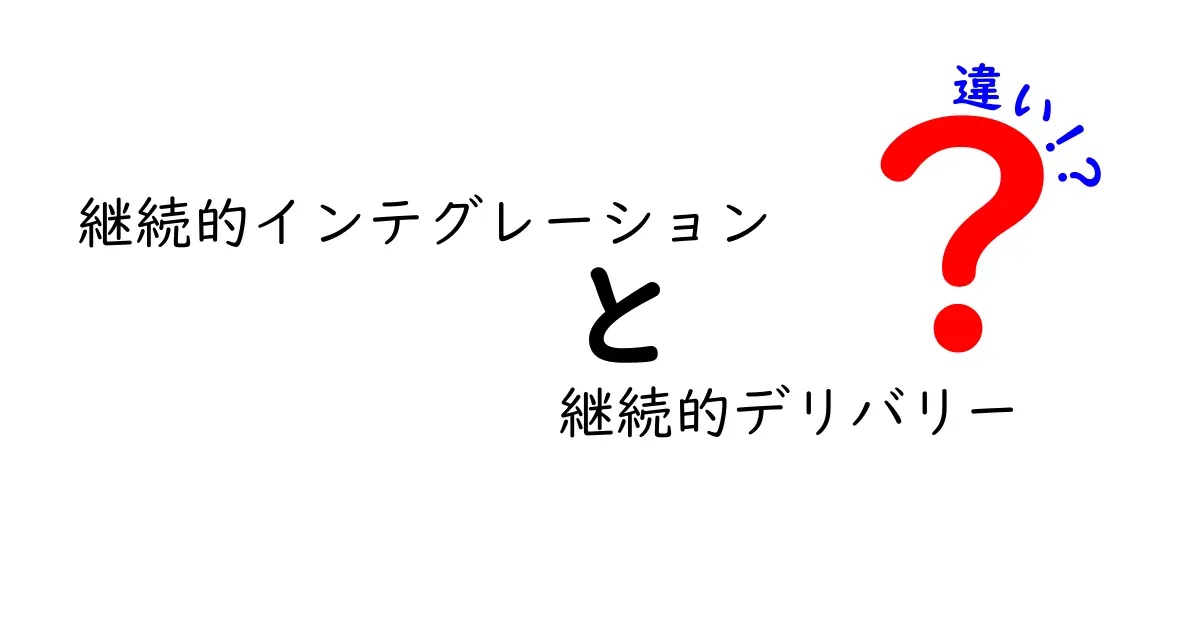

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
継続的インテグレーションと継続的デリバリーの違いを理解するための長い導入文。CIとCDはどう結びつくのか、そしてなぜ両方を正しく使い分けることが大切なのかを、現場の声と実例を交えて丁寧に解説します。CIはコードの統合と検証を自動化し、バグの早期発見や品質の安定化を目指します。一方CDは検証済みのコードを迅速に実践環境へ配置する仕組みで、リリースサイクルの短縮とデプロイの信頼性を高めます。これらは別々の概念ですが、現代の開発では互いに補完し、倉庫の在庫管理のように連携して動くべき存在です。以下の章では、実務での使い分け、導入のコツ、よくある誤解、そして表での比較を詳しく紹介します。
この章ではまずCIの基本を押さえ、続いてCDの位置づけを整理します。CIはビルドと自動テストを毎回のコード変更ごとに走らせ、失敗するとすぐに開発者に通知します。これにより、バグの拡大を防ぎ、統合時の大きな修正を避けることができます。CDはCIの成果物を受け取り、構成管理、環境設定、デプロイの自動化を通じて、本番やステージングといった様々な環境へ安定して届けることを目指します。ここで重要なのは、CDが届けるという動作を自動化する点であり、必ずしもGitのマージやレビューを置き換えるわけではない点です。
さらに、CI/CDの導入を成功させるコツとして、パイプラインの分割、テストの階層化、環境の一貫性、監視とロールバック手順の明確化などがあります。分割とは、ユニットテスト、統合テスト、受け入れテストといった段階を別々のステージに分けることです。環境の一貫性は、同じ設定で開発から本番までデプロイできるようにすることで、環境差異による問題を減らします。
CIとCDの実務上の違いを整理するポイントと、現場での使い分け方を詳しく解説します。CIの役割は主にコードの統合と自動検証にあり、開発者が小さな変更を頻繁に組み込み再現可能なテストを走らせることで品質を保ちます。CDの役割は、検証済みの成果物を自動的に本番に近い環境へ渡し、リリースを可能にする仕組みを整えることです。これらは互いに補完し、組み合わせることでデプロイの信頼性と速度を両立させます。一方で、導入の壁にはツールの選択、パイプラインの設計、権限管理、エラーハンドリングの複雑さなどがあり、初期設定には時間がかかります。適切な段階的導入と、失敗時のロールバック戦略、監視の仕組みを整えることが成功の鍵です。
最後に、現場で起こりがちな誤解として、CIはデプロイを自動化するものだという考えや、CDを導入すればすぐに全てのリリースが安定するという期待があります。しかし実際には、CIとCDは継続的な改善と運用の一部であり、組織文化や開発プロセスの成熟度とともに進化します。小さな成果から段階的に拡張することをおすすめします。
授業の合間に友達と雑談する感じで深掘りする小ネタ。継続的デリバリーは早く届けることをめざすが、同時に現場の安定性を保つことが重要という現実があります。CDは実務で非常に便利ですが、環境の複雑さや依存しているパートが多いと設定が難しくなる場面も多いです。僕の部活の開発プロジェクトでは、CDを取り入れるとリリース日感覚が身につく一方、誰が何をどう監視するかのルール作りが必要だと感じました。つまり、急ぐことと正確さのバランスを取りながら、改善を続けることが大切です。
前の記事: « 内積と行列の積の違いがすぐわかる図解と例解説





















